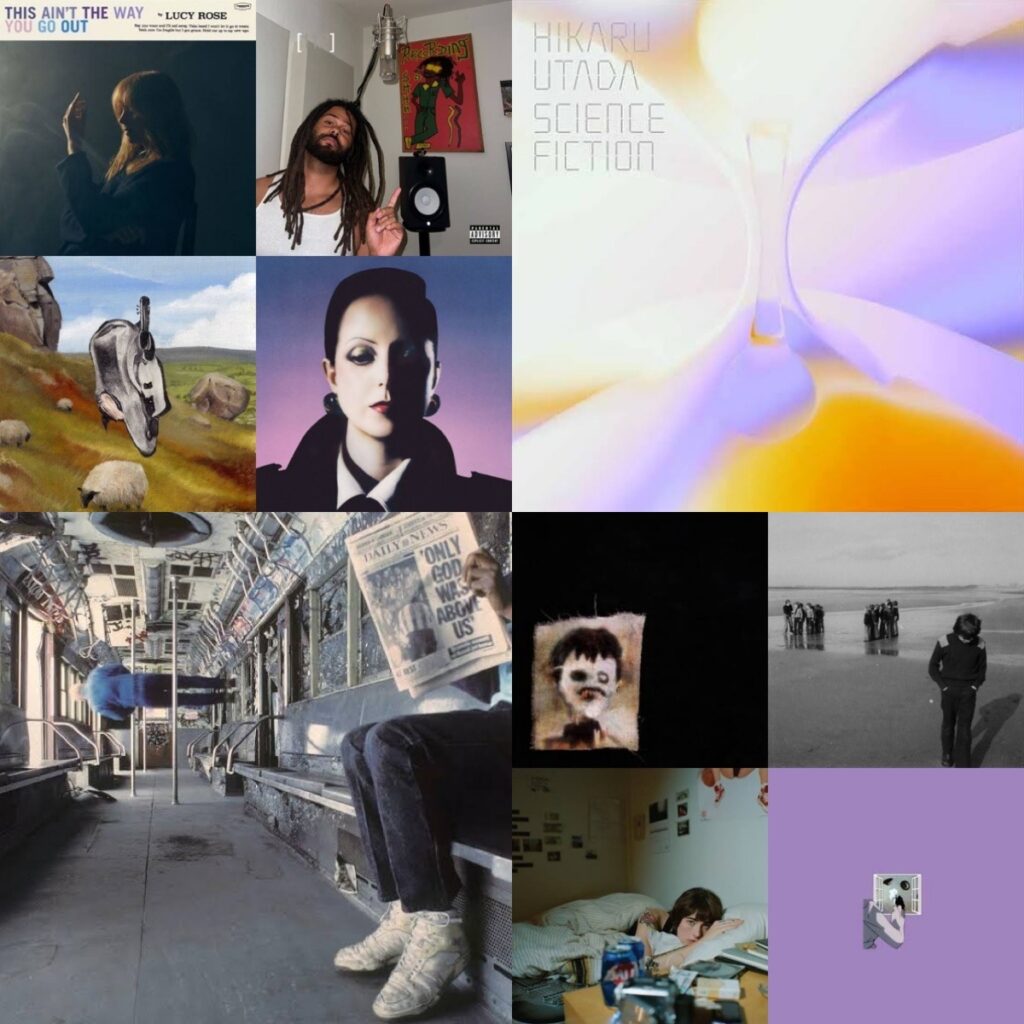
おお、1月のうちに2回も更新するなんて。ご無沙汰しております、ピエールです。今回も前回に引き続いて、「オススメ新譜10選」をやっていきましょう。4月編ですね。バックナンバーは↓からどうぞ。
毎回私の中で自信を持って10枚チョイスしてはいるんですけど、今回のセレクトに関してはいつも以上に愛着のあるものが揃ったなという手ごたえが結構ありまして。早速見ていきましょうか。
“SCIENCE FICTION”/宇多田ヒカル
まずは一番厄介な作品を片付けましょう。宇多田ヒカルのベスト・アルバム“SCIENCE FICTION”です。厄介というのはですね、何度か主張してますけど、私の中でオリジナル・アルバムか否かというのは性質上大きな違いがあるんです。まして新譜レコメンドで、既発曲の集合体を扱うなんて私の矜持からして本来あり得ないこと。
ただねぇ……これは流石に取り上げない方が不誠実ですよ。2年前“BADモード”を年間ベストに選出しましたけど、紛れもなくその延長線上、一段高いステージへ至った宇多田ヒカルを捉えた貴重なドキュメントです。もちろんベスト盤、それも誰あろう宇多田ヒカルですから、馴染み深いヒット曲が中心の内容なんですが……その大部分にリミックスが、一部楽曲では再録という措置が取られています。これがまたとんでもねえんだ。
2000年代初頭くらいのR&Bの感覚を、ハウスを通過してFloating Pointsをプロデューサーに迎えるに至る「今の宇多田ヒカル」に丁寧にアップデートしていてね。“Automatic”のリミックスなんて顕著ですよね、音の鳴り方が1999年とはまるで異質でしょ?あるいは“光”の新録、もともとのメロディ・ラインのインパクトを損なわず、サウンドの立体感が大胆に再構築されています。こんなことをされると、「ベストなんざ聴かんでええわい」派閥の私も黙るしかないんですね。
「今の宇多田ヒカル」ということだと、最新作の”BADモード”からが最多収録という点、そしてやはり Floating Pointsを起用した新曲“Electricity”も要注目です。この新曲がまた、ヴォーカルとリズムの調和に最大の個性を持つ宇多田ヒカルの2024年的最大出力みたいな傑作でね。「J-Popだし」「ベストだし」、そんな言い訳せずに黙って一旦聴いてください。その価値があることは私が保証します。
“Only God Was Above Us”/Vampire Weekend
さて、純然たる「新譜」ということになれば最大のリリースはこれでした。アメリカが誇るインディー・ロック・バンド、Vampire Weekendの5th“Only God Was Above Us”。活動期間に対して、まだこれで5枚目というのがちょっと意外でした。この辺りの時代やバンド、個人的に掘り下げが足りてない分野でもあるのでね。
そういう訳で朧げなイメージしかない中で本作を聴いたところ、驚きましたね。ここまでサウンド・プロダクションに凝ったバンドだという印象は、恥ずかしながら全くありませんでした。ブラスにストリングス、ギターにシンセサイザー、もう使えるもの全部使ってやろうというリッチなサウンドです。しかし決して華やかではない、どころか内向的で閉鎖的、荒廃したような印象すら覚えるのが鮮やかな采配。
この辺り、リズム隊がファットなのが効いてると思うんですよ。サウンドの幅を一点に収束させる屋台骨としての役割を見事に果たしていて。ただ、バンド・メンバーとしてクレジットこそされていますが、Chris BaioとChris Tomsonは実際には本作の半数ほどにしか参加していないようです。「ロック・バンド」としてそれがいいか悪いかという話は置いておくとして、その措置が結果としてこの重厚さを生んでいるんですから音楽的には正解ですよね。
リリースのタイミングで日本のリスナーもすごく沸いていましたし、実際内容もすごく充実していて。ここまで貫禄というものを感じたアルバム、今年に関しては今のところ他に思いつかないです。こういう創作に信頼が置けるバンドって、やっぱりシーンには必要だよなぁとも思うんですよね。
“Connla’s Well”/Maruja
去年の年間ベストにも選出した私のお気に入り、イギリスはマンチェスターのポストパンク・バンド、Marujaの新作”Connla’s Well”です。規格としてはEPになるので新譜レコメンドで取り扱うのはちょっと気が引けるんですけど、個人的にかなり愛着を抱きつつあるバンドですのでご紹介します。
ジャズを基調としながらも、とことんまで不穏でとことんまで苛烈なアンサンブル。系譜としてはKing Crimsonからblack midiに至るそれと同一だと思いますが、本作はロックのカタルシスというよりはやはりジャズに典型的な緊張感に追従している印象です。アンサンブルの先頭にいるのがドラムで、流石に意図的だと思うんですけどずっと先走ってるんですよね。演奏陣だけでなく、リスナーまでも振り落としかねないハードコアっぷり。
そしてその隙間を埋めるように吹き荒れるアルト・サックスが厳粛さを与え、ギターやベースはサウンドそのものとして主張するよりはドローン・ミュージック的な緊迫を生む。この息詰まる世界観が堪らないですね。かと思えば、クロージングの“Resisting Resistance”には抒情的な表情があってね。しっかり作品としての着地点を示してくれる辺り抜かりないです。まあ、この曲も道中でどんどん破滅的なアンサンブルに変化していくんですけど……
そう、この記事を準備している最中にblack midiの活動終了が話題になってしまって。まだ公式なアナウンスは出てないんですけどね。個人的にすごく期待していたバンドだっただけに寂しさも一入なんですが、Marujaはその穴を埋めてくれる逸材だと信じています。とりあえず一刻も早くフル・レングスを出してほしいですね、この緊張感と暴力性を40分以上持続できるのかはすごく気になるポイントですから。
“This Could Be Texas”/English Teacher
今回は結構ロック色が強いラインナップになりそうですね、続いてはイギリスはリーズ出身のロック・バンド、English Teacherの1st“This Could Be Texas”。デビュー作ながら全英チャートで初登場8位につけた、期待の新人です。
方向性としては、ここ数年のトレンドとなっているUKポストパンクの一群にはあります。ただまあ、この一群そのものが、特定の音楽性で結びつくというよりは「それぞれ面白いことやってるシーン」くらいの共通項でしかないんですが。English Teacherの場合、サウンドスケープの遊び心がすごく秀逸ですね。特にストリングスやシンセサイザーの扱いなんて、1stとは思えないくらいアイデアの引き出しが豊富です。
タイトル・トラックでもある“This Could Be Texas”というナンバーが個人的なフェイバリットなんですが、フォーキーで端正な正統派の作曲かと思えばいきなりプログレッシヴ・ロック的な緊張感と偏執性を剥き出しにしてくる。楽曲単位でのバラエティという範疇ではなく、もっと細かく、もっと奔放な表現性の高さ。Black Country, New Roadの1stなんかにも感じたクリエイティヴィティを彼らにも認めることができます。なんなら成熟っぷりならこちらの方が一枚上手じゃないかな。
しかもフロントがLily Fontaineという女性でね。だからサッド・ガールだ!なんて言うつもりはないんですけど、サウンドのアプローチといいバンドのアピールといい、すごく現代的な匂いを感じさせます。それこそBC,NRは2ndで一気にハねましたけど、English Teacherもそうなっても何ら不思議でないポテンシャルを持っているバンドではないかと。今後の動向が楽しみなバンドが出てきましたね。
“Fabiana Palladino”/Fabiana Palladino
こちらはFabiana Palladinoという女性シンガーのデビュー・アルバムです。名前でピンとくる方も多いと思うんですが、彼女はあのベーシスト、Pino Palladinoの実の娘。Fabianaにとっては兄にあたるRocco Palladinoともども、本作にも参加していますね。
こう書くとちょっと芸能界の臭いがしちゃうかもしれませんけど、いやいやそんなことありません。この官能的な聴き心地、とても処女作とは思えぬ天晴れな仕上がりですよ。サウンドから感じる煌めきは80’sポップスのようでもあるし、グルーヴの艶かしさはネオ・ソウル通過後といった感じでね。ここでPrinceを持ち出すのは流石に安直な気がしないでもないですけど、でも彼から繋がるR&Bの歴史の成分も確かに感じられます。
そして、それだけサウンドにこだわりを感じさせる一方で、決してプロダクション重視のアルバムという印象ではないんですよ。洗練や抑制、そういったものを強く意識している訳ですね。ここもさっき持ち出した80’sポップスとの類似かなと思うんですが、あくまでメロディにスポットを当てた構成になっています。このプロダクションがどこまで彼女自身の采配なのかは不明ですけど、こういう手心のおかげですごくスマートなアルバムになっている気がします。
彼女が寄せる関心の領域であったり、それを表面的になぞるのではなくしっかりと咀嚼してみせるセンスの高さであったり、そこをここまで清廉に表現してみせるのはなかなかできたことじゃないと思います。ここまで練られたアルバムでキャリアを始動させたことがむしろ不安になるくらい、隙のない名作ですね。
“Affection”/Bullion
良質なポップス繋がりでこちらも紹介しておきましょうか。UKエレクトロ・シーンでのアーティストとしての活躍にとどまらず、Carly Rae Jepsen筆頭に数々のアーティストのプロデューサーも務めた鬼才BullionことNathan Jenkinsの“Affection”です。
前情報だとどちらかというとクラブ寄りの音楽性っぽかったので、ちょっと身構えて聴いた部分はあったんですよ。1曲目の“A City’s Never”、これがかのAnimal Collectiveの創設者Panda Bearを迎えてのナンバーということもあって。Panda Bear関連の作品も聴きはしてますけどそこまでしっくりきてなかったのでね。ただどうです、この見事なソフィスティ・ポップは。シンセサイザーはどこまでも柔らかく高貴で、メロディは実に艶やか。
時間単位あたりの音の数であったり、あるいは楽曲の展開であったり、全体としてかなり手数は少ないサウンドスケープなんですよ。その中で電子音のあたたかい残響によってスケールをぐっと広げていく、この手法はまさしくThe Blue Nileのそれを丁寧に踏襲しているんではないでしょうか。そのうえでリズムは非常にタイトというのが、彼のダンス・ミュージック的な感性を見せてくれるポイントでもありますね。
深くリバーヴをかけたヴォーカル処理もまた絶妙にかの時代のポップスを思わせるニクいやり口でね。プロデューサーとしても辣腕を振るう彼らしい措置です。80’sリバイバルがトレンドになって久しいですけど、その中でもかなりよくできた作品なんじゃないでしょうか。
“This Ain’t The Way You Go Out”/Lucy Rose
続いてはロンドンの女性SSW、Lucy Roseで“This Ain’t The Way You Go Out”です。アニメ好きな方には、『蟲師』のエンディングに起用された人っていうと伝わるかもしれませんね。このブログの読者層にどれだけ『蟲師』をご覧の方がいるかは私にもさっぱりですが。
閑話休題、私も件の楽曲“Shiver”を遥か以前に聴いたことがあるくらいでほぼ初対面のアーティストなんですが、すごく私好みです。もうアートワークの時点でお察しいただけると思うんですけど、往年の名盤らしい古風なビジュアルでしょ?内容もそこに恥じないもので、ピアノを軸にしたソング・ライティングなんですが、これがこじんまりとしたジャズ風のものからかなり弾けたロック・ライクでアッパーなものまで、実に多彩でね。
で、その多彩な作曲に寄り添う演奏がまた秀逸です。それぞれのパートに録音的なこだわりを強く感じるんですが、ドラムはものすごく音の粒が立ったネイキッドなサウンドの一方、ベースなんか曲によっては相当輪郭をぼやけさせた独特のテイストになっていたりして。1つ1つに意図を感じるくっきりとした録音になっていて、ここまでエンジニアリングが見事だと音響的にもたっぷり楽しめます。
そういう作曲のレンジだったり録音の見事さだったりがありつつ、それでも作品としては軽やかでクラシカルなSSWアルバムに着地しているのも本作の魅力じゃないでしょうか。小難しいことを抜きに、さっぱりとした佳曲だけで構成された1枚ですからね。
“Sentiment”/Claire Rousay
こちらはアンビエント畑のアーティスト、Claire Rousayで“Sentiment”ですね。私個人、アンビエントや広い括りでのエレクトロにはあまり詳しくないんですけど、かなり実験的なアプローチをこれまで展開してきたアーティストのようです。この領域、いつか本腰据えて勉強しないとなぁとは思ってるんですけどなかなかね。
さあ、そういう訳であまり前提知識もなく聴いてみたところ、正直イメージとは随分違った印象です。特に全面的にヴォーカルをフィーチャーしているのには驚きでしたね。それも音響の中のマテリアルとしてではなく、しっかりとしたメロディを伴った形態で。そこにはたっぷりとエフェクトがかけられているのでサウンド全体と調和は図られているんですが、まずもってヴォーカル作品という事実に意表を突かれました。
そのサウンドというのも、もっと曖昧な電子音で埋め尽くされるのかと思いきや、ストリングスやギターといった実際の楽器を軸としていて、かつフィールド・レコーディング的な環境音も大胆に作中に取り入れています。ヴォーカル作品という点も加えて、全体として実に生々しい人間味を感じさせるタッチですね。それでいてどこか儚く、親密というよりは独り言を盗み聞きしてしまったような距離感を持っているような。
きっと旧来の彼女がやってきたようなエクスペリメンタルなアンビエント作品だと、今の私ではキャッチしきれないような気がするんですよ。そこをこのアルバムは、あくまでメロディを聴かせてくれますからね。そのうえで本作との比較のために彼女の諸作にも触れてみたい、そう思わせるだけの関心を引くに足る1枚です。
“Triple Digits [112]”/RiTchie
ヒップホップを扱うの、ちょっと久しぶりな気がします。かつてInjury Reserveというユニットに所属していたラッパー、RiTchieのソロ1st “Triple Digits [112]”ですね。このInjury Reserveが最後に出したアルバムが当時の年間ベストでも上位につけるくらい好きな作品だったので、結構期待値は高かったです。
で、そのInjury Reserveの最終作がものすごく挑戦的なサウンドだったんですよ。暴虐なトラックで聴き手を圧倒するような。本作もその流れを引き継ぐのかと思いきや、ユニークではあるもののかなりマイルドかつ手作り感のある質感になってます。RiTchieのラップもテンポを落とした、かなりリラックスしたフロウになっていて。そうしたサウンドのゆるさやBe Realに投稿するのかってくらい気取らないアートワークなんかも相まって、すごく自然体を感じさせるんですよ。
ただ遊び心というか、アイデアを思いつくままにトラックに落とし込む先の読めない進行をするので、ちょっとでも聴き逃そうものなら作品の向いている方向がガラッと変わってしまいます。なので自然体を感じる一方、緊張感も絶えずそこにあるんですよね。なら聴いていて疲れるかというと、アルバムが30分あまりとコンパクトにまとまっている点も貢献してすっと聴き通せてしまえる、このいい意味での軽さもまた心地よいじゃないですか。
個人的にヒップホップはサウンド重視の聴き方をしているので、想像していたサウンドとは離れていましたがこれはこれで見事にツボを突いてくれたなという印象です。残念ながらXで本作に言及している人はほぼ見かけなかったんですが、JPEGMAFIAとかが支持される日本のコア・リスナーの趣味にはかなり刺さる1枚だと思うんですけどね。
“Por cesárea”/Dillom
最後にもういっちょヒップホップから。これはアルゼンチンのアルバムですね、Dillomの2nd“Por cesárea”です。記憶が確かなら1stもリリース当時それなりに話題になって、ジャケットにも見覚えはあったんですが、正直ここで取り上げることになるアーティストとは思っていませんでした。
というのも前作が言ってしまえばUSヒップホップのメインストリームの延長線上にあるような内容だったんですよね。個人的にあまり関心を引かれるものではなかったので「非英語圏のヒップホップってこんな感じか」くらいの理解でとどまっていたんですが……ここまで化けてくるとは思いませんでした。重厚で多彩、かつ流れるようなトラック・メイキングはもう完全に別物ですからね。
壮麗なダイナミズムなんかにはヒップホップというよりはロックのエッセンスも感じますし、メロディアスな展開やインディーっぽい現代的なセンスの良さもあってね。スペイン語らしい巻き舌を強調したフロウと彼自身のくぐもった独特の声質も、そうした全体像と馴染んで鮮やかに聴こえてきます。ヒップホップに普段あまり親しまないという方にこそ聴いていただきたい音楽性じゃないかな。
前回のsonhos tomam contaでも書いた土着性から生まれる独自性、それはヒップホップのフィールドでも通用するものだとこの作品で実感しましたね。この企画ではあまり批評的な意味合いは重視しないつもりでいるんですけど、単純に私の耳に合う良質な作品が立て続けに南米から現れているのにはなんだかワクワクさせられます。
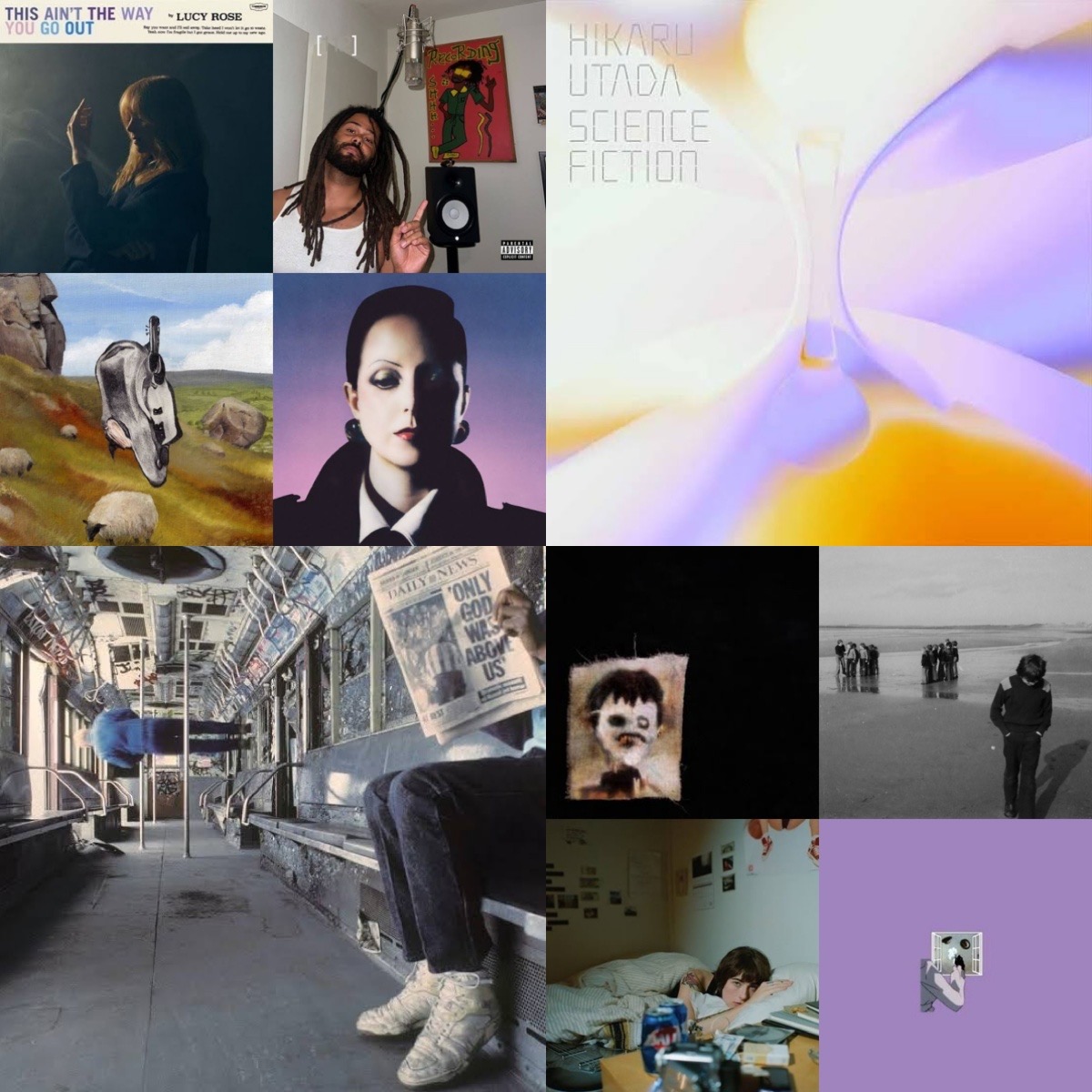


コメント