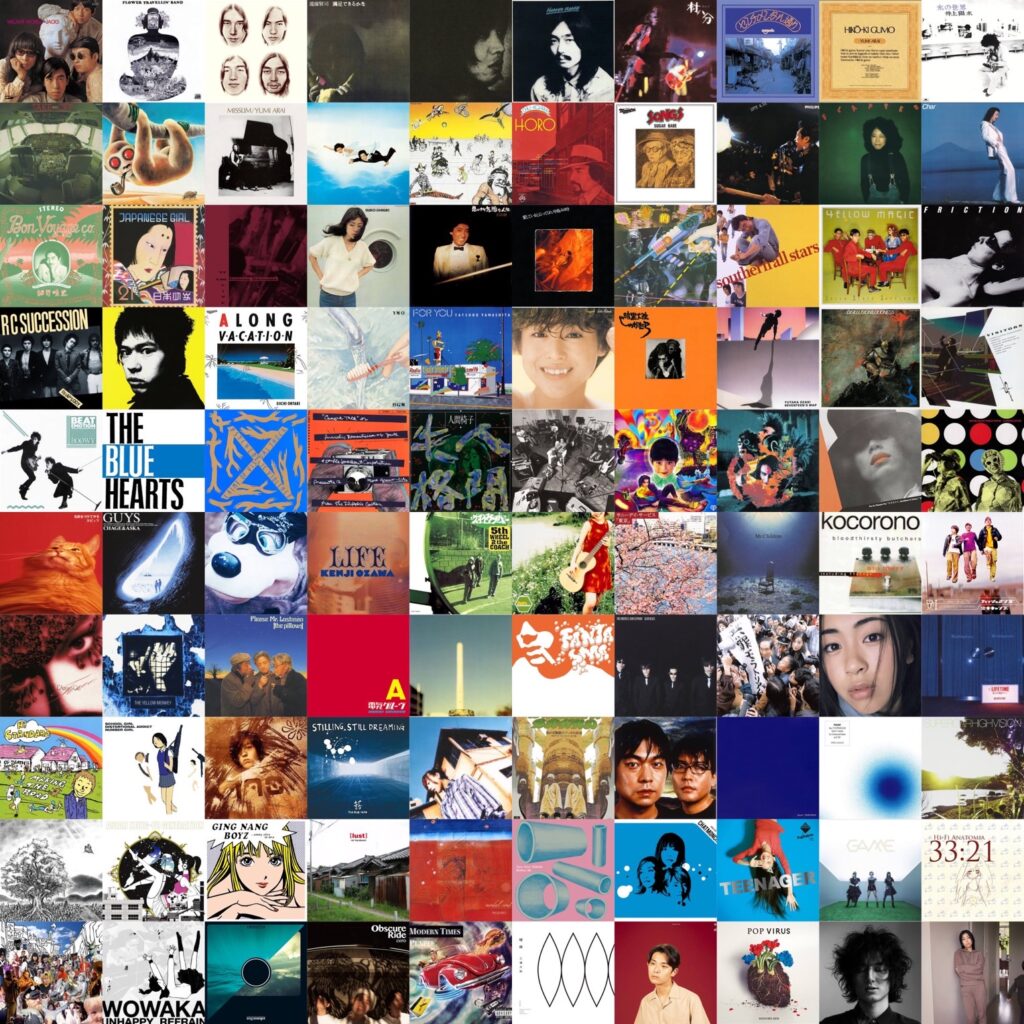
3年前に、「史上最高の洋楽名盤ランキングTOP100」という記事を投稿しました。
ありがたいことに、現在このブログで一番読まれている記事となっています。「洋楽 名盤」なんて検索しても、かなり上位に表示されてもいて。
では今回は?私の悲願でもあったオールタイム名盤ランキング第2弾、邦楽編と参りましょう。
このランキング作成にあたる基準は、自己分析や所感を含めて後日別記事にて投稿する予定です。なのでここではあくまでざっくりとした前提だけ、先に断っておこうと思います。
今回選出した100枚、そして順位の高低に関して、私個人の趣味性や愛着は(可能な限り)排除しています。あくまで「偉大」であるかどうかに着目した、客観的な批評として成立し得るランキングがこの投稿の目指すところです。その点はご承知ください。
また邦楽入門のディスク・ガイドとしても機能させるべく、ランキング中の全作品にレビューとApple Music(他のサブスク使ってらっしゃる方はすみません)のリンクも書き加えてあります。100作品分、しめて4万字の一大ボリュームになっておりますので全部読み通そうという方はどうぞ肩の力を抜いて挑んでください。各ページの冒頭に目次はあるので、ランキングの内容だけ知りたい方はそんな風に使っていただいても。
さあ、前置きはこの辺りで。私ピエールが本気で選んだ、「邦楽史上最も偉大なアルバム・ランキングTOP100」。とくとご覧あれ。
- 第100〜91位
- 第90〜81位
- 第90位『DISILLUSION〜撃剣霊化〜』/LOUDNESS (1984)
- 第89位『HELP EVER HURT NEVER』/藤井風 (2020)
- 第88位『MODERN TIMES』/PUNPEE (2017)
- 第87位『思い切り気障な人生』/沢田研二 (1977)
- 第86位『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』/銀杏BOYZ (2005)
- 第85位『SICKS』/THE YELLOW MONKEY (1997)
- 第84位『軋轢』/フリクション (1980)
- 第83位『MAKING THE ROAD』/Hi-STANDARD (1999)
- 第82位『球体』/三浦大知 (2018)
- 第81位『[lust]』/レイ・ハラカミ (2005)
第100〜91位
第100位『人間失格』/人間椅子 (1990)

バンド・ブームの時代に次々と現れた玉石混淆の中で、人間椅子は黴臭いハード・ロックを30年以上鳴らし続け今や国際的な支持を集めるに至っています。変わることなき彼らの矜持が最初に示されたのが、太宰治の傑作をその名に戴いた処女作『人間失格』。
ブラック・サバスの重苦しさ、あるいはキング・クリムゾンの無情さといった参照元を忠実に踏襲し、日本文学を引用した詩情で陰惨に描写する。所謂「ジャパメタ」とも一線を画するその独創的な世界観を支えるのは、舶来ロックへの並々ならぬ憧憬と分析、そしてそれを日本的な土着性で発露させる彼らの表現力に他なりません。
本リストで今後も度々言及することになる、「洋楽に相対する邦楽」の視点。それをハード・ロックという形式で、限りなくコアな手法ではあるものの達成したのが本作と言えるでしょう。国産ハード・ロックとして誇るべき名作。
第99位『電撃的東京』/近田春夫&ハルヲフォン (1978)

日本におけるパンク・ムーヴメントの受容の歴史は、しばしば「東京ロッカーズ」一派への言及にとどまりがちです。しかし近田春夫による『電撃的東京』は、そうした史観に新たな視座をもたらす重要な1枚。
歌謡曲をパンク・サウンドでカバーするという大胆な発想の本作ですが、そこには近田の確かな思惑があります。粗暴で直線的といった表面的な理解に収まらず、パンクがその根底に宿すフレンドリーな性格を見定め、その親しみやすさを歌謡との共通項と分析してみせたからこそ、一見かけ離れた両者に驚くべき親和性を生み出すのです。
これほどの洞察をピストルズの登場からわずか1年という期間でやってのける、その批評精神は実に鮮やか。そして歌謡という日本特有の音楽性に誇りを持ってアウトプットした事実は、邦楽通史の中で軽んじてはならないものでしょう。
第98位『Please Mr.Lostman』/the pillows (1997)

ライブハウスやロック・フェスティバルを沸かせる「ロキノン系」のバンド群が、挙ってリスペクトを表明するthe pillows。決して華々しいとは言えないキャリアの彼らが何故これほどの支持を集めるのか、その所以が会心の一撃『Please Mr.Lostman』にはあります。
シンプルなオルタナティヴ・ロックと誠実なソング・ライティングに忠実なこの作品ですが、逆境にあったバンドにとっては音楽業界への遺書とまでの思いをもって制作されています。一聴して穏やかな世界観は諦念にも似た悲壮な覚悟の表れであり、それは素朴であってエモーショナルな歌詞や山中さわおの歌唱にも克明に刻まれています。
この決死の1枚は大きなセールスに繋がることはなかったものの確かにリスナーへと届き、the pillowsは充実したキャリアを構築していくことになります。その高い作曲能力だけでなく、本作に顕著なロック・バンドの矜持を貫く姿勢そのものが、今日の彼らの評価へと繋がっているのです。
第97位『FLAPPER』/吉田美奈子 (1976)

「和製ローラ・ニーロ」の触れ込みでデビューした吉田美奈子ですが、彼女の魅力は作曲家としての才のみならずブラック・ミュージックのフィールをよく了解した歌唱にもあります。そうした、シンガーとしての吉田美奈子を切り取った名作が『FLAPPER』。
本作の作曲には吉田本人に加え、大滝詠一に細野晴臣、山下達郎や矢野顕子といったはっぴいえんど人脈が集結。それぞれの楽曲はオールディーズやファンク、フュージョンと多彩ではあるものの一貫してブラック・ミュージックでまとめ上げられ、それらを流れるように歌い上げる彼女の表現力へとフォーカスした印象を強く抱きます。
後に多くのカバーを生む大滝作の『夢で逢えたら』筆頭に、作家陣のメロディ・センスが光る国産ポップスの秀作がこの作品。はっぴいえんどから連なる文脈がその革新性ではなく、あくまで確かな才能によって評価されていることを証明する作品とも言えるでしょう。
第96位『ソルファ』/ASIAN KUNG-FU GENERATION (2004)

BUMP OF CHICKENが90年代オルタナティヴへのアンサーだったならば、ASIAN KUNG-FU GENERATIONは90年代オルタナティヴの正当後継者と言える存在。彼らの出世作『ソルファ』に、そのキャラクターはよく表れています。
ナンバーガールに代表されるギター・オルタナティヴを踏襲しながら、彼らはよりパワー・ポップ的にメロディの輪郭を強調することでキャッチーな魅力を獲得。そして『リライト』のようなアンセムから繊細なバラード、トリッキーなアンサンブルが痛快なものまで、楽曲単位でのクオリティにも目を見張るものがあります。
サウンドや歌唱に浮かぶその実直さは野暮ったくすらあるものの、だからこそストレートに初期衝動を聴き手へと突き刺すことに成功しました。2000年代のシーンが求めるロック・バンド像に応えてみせた、時代を象徴する1枚。
第95位『桜の木の下』/aiko (2000)

宇多田ヒカルや椎名林檎といった才媛、あるいは安室奈美恵や浜崎あゆみのようなスター、多くの女性が活躍していた当時のシーンの中でaikoの存在はともすると軽んじられがちです。彼女の2nd『桜の木の下』を聴けば、そのJ-Pop巧者ぶりを評価する必然性に当然気づくでしょう。
『カブトムシ』や『花火』のようなヒット曲を擁しながら、それぞれの楽曲を注意深く観察すればコード進行やメロディの運びにわずかな違和感を発見することができます。前提としてJ-Popである軽やかさに挟み込まれたその意図的な歪さは独特の緊張感を与え、ありきたりなJ-Popとは一線を画す奥深さを本作に与えています。
その技巧的な作曲を決してひけらかすことなく、恋を歌う女性シンガー・ソングライターとしての親しみも兼ね備えた彼女のバランス感覚はさりげなくも如才ない代物。1990年代以降のJ-Popの充実を語る上で、本作は本来欠かしてはならない1枚なのです。
第94位『生命力』/チャットモンチー (2007)

近年国際シーンで顕著な女性ロック・アーティストの活躍の中、日本は女性の活躍において先鞭をつけていたと評価できます。そしてことガールズ・ロックという文脈において、チャットモンチーの影響力は今日に至るまで決して無視できるものではありません。
代表曲『シャングリラ』収録のメジャー2ndである本作には、「ロキノン系」の文脈にあるギター・オルタナティヴのサウンドが充満しています。しかし女性的な繊細さや後の変幻自在のキャリアを予感させるしなやかさ、そして一癖あるポップ・センスといったバンドの個性によって確固たるオリジナリティを示してもいるのです。
東京事変で椎名林檎が見せた淫靡さとも、女性アイドルがアピールする愛嬌とも違う、チャットモンチーが鳴らした等身大の女性像は様々な後続バンドで継承されていきます。2000年代J-Rockの中でも、批評的意義において特筆すべき1枚です。
第93位『True』/L’Arc〜en〜Ciel (1996)

一口に「ヴィジュアル系」と言っても、その音楽性は広範に及びます。その中でもメロディアスでキャッチー、華やかでセクシーというジャンルのポップネスを象徴する1枚こそがL’Arc〜en〜Cielの『True』ではないでしょうか。
よりポップな音楽性を志向して制作された本作は、すべての楽曲においてメロディの主張が大きな魅力となっています。そしてその抒情的な旋律をより高めるべく、ニュー・ウェイヴやゴス・ロックの性格をそのままに、アコースティック・ギターやピアノを多用するアレンジメントはいっそうカラフルなものへと発展しているのです。
「ヴィジュアル系」として紹介されることをバンドが嫌っているのは有名な話ですが、それはあくまで音楽性を重視する彼らの矜持あってのこと。その矜持が見事芽吹いたのが本作であり、そしてある意味では皮肉なことに「ヴィジュアル系」を代表する名盤となってもいるのです。
第92位『Lifetime』/GRAPEVINE (1999)
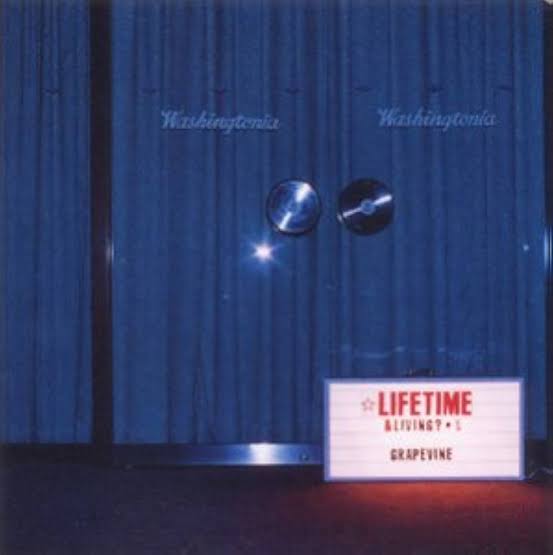
GRAPEVINEの出世作である『Lifetime』は実に不思議な1枚です。当時のJ-Popのマナーには従わず、しかし当時のロックの潮流にも背き、あくまで彼らが信ずる古き良きロック・ミュージックのスタイルによって成功を掴み取ってみせたのですから。
本作の強みとして真っ先に挙げられるのは、その飾り気のない気怠げないムードでしょう。ギター・オルタナティヴの範疇にはありつつ、バンド名からも明らかなブラック・ミュージックへの関心はバンド・サウンドのいたなさへと翻訳され、それゆえにメロディや歌唱のネガティヴな情熱をひときわ際立たせる働きをしています。
彼らが見せた切なげな情緒は2000年代のインディー・シーンにも継承されていきますが、そうした重要なエッセンスをキャリア初期に早々と鳴らした熟達は実に見事。メジャー・シーンとは距離を取りつつもバンドが長きにわたって支持されるのは、本作にも顕著な彼らの慧眼に理由があるのです。
第91位『ケダモノの嵐』/ユニコーン (1990)

メンバー全員が作曲に貢献し、それぞれに個性を発揮した自由な創作から「日本のザ・ビートルズ」と評価されることも少なくないユニコーン。そうした彼らの「日本のザ・ビートルズ」ぶりが存分に発揮された傑作が、この『ケダモノの嵐』です。
バンド初のセルフ・プロデュースということもあり、その個性はこれまで以上に躍動。ウクレレの伴奏で穏やかに開幕したかと思えば、正統派ロック・チューンからキッチュな小品、華やかなブラス・サウンドに重厚なサイケデリアといった多彩な音楽性をからかうようなユーモアを携えて次々に示す放漫さは実に天晴れです。
この作品をやはりザ・ビートルズに準えるのであれば、ユニコーンによる『ホワイト・アルバム』と呼ぶのが適切に思えます。後にソロ・アーティストとしても活躍した奥田民生のワンマンに終始せず、あくまでユニコーンとしての振れ幅をその興味の向くままにパッケージした作品です。
第90〜81位
第90位『DISILLUSION〜撃剣霊化〜』/LOUDNESS (1984)

HR/HMの流行に沸く当時のアメリカでも一定の成功を収め、世界でその名を轟かせた日本最高峰のヘヴィ・メタル・バンドLOUDNESS。初の海外ツアーを敢行したその勢いのまま、その充実を誇示するように発表されたバンドの代表作がこの4thアルバムです。
張り裂けんばかりのヴォーカル・パフォーマンス、切り刻むようなギター・リフの応酬、ダイナミックかつドラマチックな展開。本作の至るところから感じられるNWOBHMの破壊力の影響を、卓越した技巧とバンドのタフなエネルギーによって即座に国産ハード・ロックとして昇華した誇り高き1枚と言えます。
グラム・メタルに接近した次作でその名声は決定的なものになりますが、バンドのオリジンである硬派なメタル・サウンドを確立した本作こそ彼らの最高傑作に相応しい1枚。そして本作はLOUDENSSのキャリア、あるいは「ジャパメタ」の歴史だけにとどまらず、80’sHR/HMの国際シーン全体を見渡しても稀有な名盤なのです。
第89位『HELP EVER HURT NEVER』/藤井風 (2020)

岡山から彗星の如く現れ、飄々とした自然体のままにシーンの注目を掻っ攫った藤井風。その身軽な佇まいと音楽的才能を余すことなくパッケージした記念すべき1st『HELP EVER HURT NEVER』は近年のJ-Pop有数の名作です。
現代ブラック・ミュージックを反映した滑らかなトラック・メイクには近年のJ-Popのトレンドとの共通項を発見できる中、歌謡的な親しみと岡山弁をこともなげに歌唱に取り入れる飾らない表現は実に個性的。野心的な処女作というよりはむしろ、感じるままに音楽をアウトプットする老練な朗らかさを印象づけています。
近年続くJ-Popの充実をいつか振り返る時、本作の存在感は今以上に巨大なものになっていることを予感させます。サブスクリプション・サービスの普及を追い風に国際的なリスナーを獲得した背景も踏まえて、非常に今日的なJ-Pop作品と言える1枚。
第88位『MODERN TIMES』/PUNPEE (2017)

PUNPEEのラッパー/プロデューサーとしての手腕は、数々の創作や客演によって十分に証明されてきました。その彼が満を持して発表した1st『MODERN TIMES』によって、その才能の全貌は遂にベールを脱ぐことになります。
カラフルなトラック・メイキングとファニーなアイデア、そしてキャッチーなラップ。PUNPEEの面目躍如たるスキルが全編にわたって発揮される本作は、彼が愛好するSFのムードの中自由に冒険していきます。また、遥か未来の年老いたPUNPEEの回顧録というコンセプトによって流麗なストーリーが生まれている点も見事。
加山雄三をヒップに再解釈し、宇多田ヒカルを未来的にリミックスする、そのセンスをPUNPEE自身になみなみと注いでみせた成果がこの作品です。最早ヒップホップの枠組みにすら囚われぬ、玩具箱をひっくり返したような奔放さが楽しい名盤。
第87位『思い切り気障な人生』/沢田研二 (1977)

「はっぴいえんど中心史観」、あるいはロック至上主義に陥った時、見落としかねないのが我が国の歌謡文化の豊かさ。歌謡界きってのスター、「ジュリー」こと沢田研二の名作『思い切り気障な人生』は必ずや本リストに加えねばならない1枚です。
大野克夫と阿久悠というゴールデン・コンビが生み出す楽曲は、どれも色褪せぬ鮮やかさと色香を振り撒いています。そしてジュリーの表現力にもやはり注目すべきで、GSをルーツに持ちステージでもグラム・ロックの華を取り入れていた彼の感性はその歌唱にも表現され、ロック的に本作を見つめたとしても十分に評価すべき代物です。
単に秀でた歌謡作品としてであっても、この作品を肯定するのはあまりに妥当です。加えて、ニュー・ミュージックの才能が歌謡の世界へと進出するより以前からロックのセンスを歌謡の中でアピールしてきたジュリーの貢献を思えば、本作を見落とすのはあまりにナンセンス。
第86位『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』/銀杏BOYZ (2005)

銀杏BOYZほど破天荒という形容詞が似つかわしいバンドも日本にそうはいないでしょう。2作同時リリースというやはり型破りなデビューを果たした彼らですが、その2枚の1stがうちの1つ、『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』も、やはり破天荒そのもの。
前身となったGOING STEADYでのレパートリーも収録しつつ、いっそうに過激さを強めてみせる本作。当時流行の青春パンクとしても語られることが多いものの、爽やかさとは無縁の熱量と危うさで激走するハードコアなサウンドやいじらしくも変態的な歌詞は、銀杏BOYZに特異のオリジナリティと言っていいでしょう。
思わず眉を顰めたくなる破壊衝動は、しかしティーンエイジャーであればどこか共鳴するものがあることも事実。極めて賞味期限の短く、それゆえにどの時代においても若者の代弁者になり得る生々しいスケッチこそがこの1枚です。
第85位『SICKS』/THE YELLOW MONKEY (1997)

ヴォーカリストの吉井和哉自身がTHE YELLOW MONKEYの最高傑作と豪語し、キャリア最大のセールスを記録した『SICKS』。そこに刻まれるのは、遥か海の向こうのTVのシンガーが見せたようなダイナミックなロックのパワーに他なりません。
キャリア初期に顕著だったグラム・ロックからの影響や、ヘヴィなアンサンブルの強度、そしてメロディに感じる歌謡的な艶。バンドの魅力を余すことなく表現してみせた本作から感じられるタフな佇まいは、当時流行のオルタナティヴ・ロックの鋭利さよりむしろクラシック・ロックにあるある種の太々しさを継承したものでしょう。
THEE MICHELLE GUN ELEPHANTをカリスマ、Mr.Childrenをスターとするならば、THE YELOOW MONKEYは差し詰めヒーローでしょうか。そのヒロイックな存在感を体現した、威風堂々たる名盤です。
第84位『軋轢』/フリクション (1980)
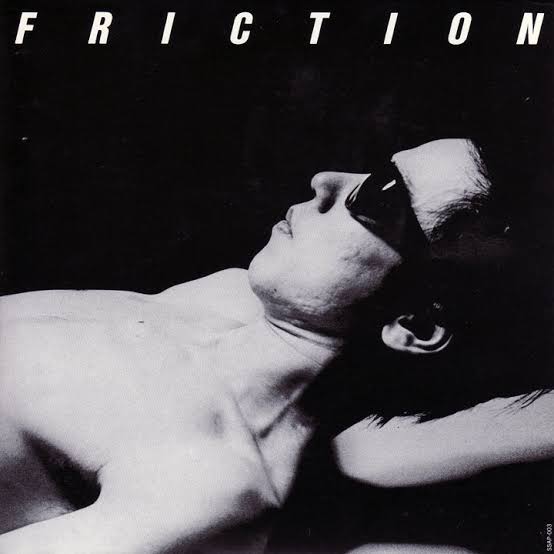
「東京ロッカーズ」の中心的存在として、日本のパンク史の中で高く評価されるフリクション。パンクがアンダーグラウンドに展開されゆくニュー・ヨークで受けた刺激をそのままにパッケージしたのが、1st『軋轢』です。
鋭利で無機質なギターは、そのバンド名とともにテレヴィジョンからの影響が強く残されています。しかし一方で単調で反復性の高い演奏やどこか気だるげで脱力したムード、あるいは坂本龍一の貢献が光る生々しくルーズなプロダクションからは、パンクのその先、ポストパンクやノー・ウェイヴとの共通点も多く発見できるでしょう。
1980年という正にパンクが羽化を果たそうとする瞬間に呼応した作品が日本から生まれ、かつ提示されたサウンドは今日的なポストパンクの文脈にも容易に接続し得る。これほどの感性の鋭さと先見の明には、脱帽する他ありません。
第83位『MAKING THE ROAD』/Hi-STANDARD (1999)
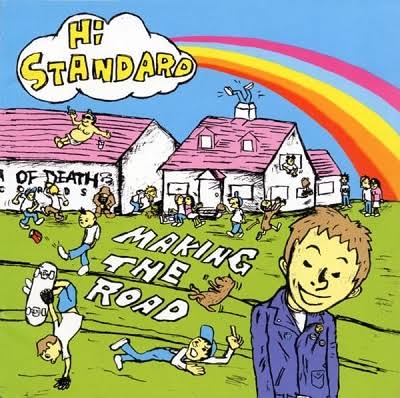
世紀末に日本のロック・シーンを盛り上げたインディーズ・バンドのムーヴメント。その中でも今日まで絶大な影響力を誇るHi-STANDARDはこともあろうにこの1枚で、自主レーベルからのミリオン・ヒットという偉業を成し遂げました。
唐突に挿入されるボサノヴァを唯一の例外として、全編通じて前のめりな2ビートで疾走するアグレッシヴなパンク・チューンの応酬。音楽的な多様性やアルバム作品としての緩急には関心を寄せず、突破力でねじ伏せる痛快な作品です。その潔さと単純明快なキャッチーさこそが、彼らが支持を集めた最大の要因でしょう。
2000年代の邦楽ロックは、英米とも離れた独自のシーンを構築していくことになります。BUMP OF CHICKENの親しみやすさやナンバーガール由来の先鋭性と並び、本作でHi-STANDARDが示した勢い任せの衝動は、その重要なルーツとして黄金に輝き続けています。
第82位『球体』/三浦大知 (2018)
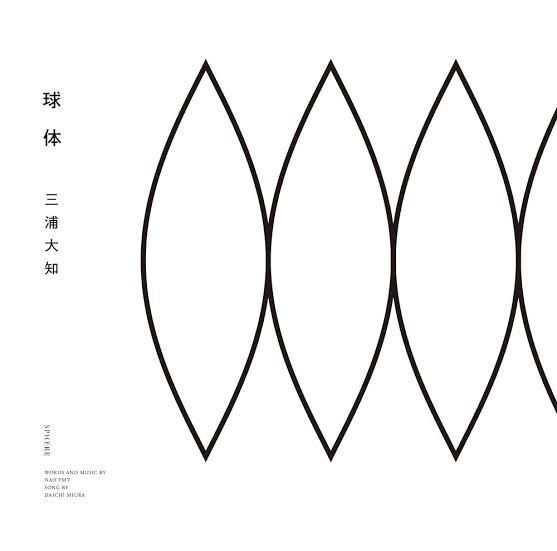
三浦大知の『球体』は、音楽とダンス・パフォーマンスを両輪とするプロジェクトとして出発した経緯を持ちます。当然パフォーマーとしても才能溢れる彼ですが、本作は単に音楽的に見つめたとしても素晴らしくコンテンポラリーなJ-Popの境地の1つと言える内容。
透明感のあるエレクトロの色彩や繊細さには、2010年代のアンビエントR&Bの咀嚼の痕跡が窺えます。しかしかのジャンルがある種パーソナルなものであったのに対し、三浦は内向性を踏まえてあくまで俯瞰的に作品へと向かい合い、作品全体にアーティスティックなムードを生み出すことに成功している点には是非とも注目すべき。
本作の実験性と達成は、洋楽への追従と独自性の獲得という邦楽史上の命題に対する2010年代的模範解答とも言える代物。ダンス・ミュージックの同時代的解釈においてK-Popが先導する現状の中、この作品が日本から生まれている事実はその可能性において示唆的とも言えるでしょう。
第81位『[lust]』/レイ・ハラカミ (2005)

レイ・ハラカミの才能はエレクトロの文脈だけでなく、細野晴臣や矢野顕子といった邦楽の重鎮からも認められる普遍的なものです。前作『Red Curb』と並び、彼のキャリア・ハイに位置づけられるのがこの作品。
彼が紡ぐ電子音は、どこまでも柔らかく夢幻的な表情を浮かべています。細かく刻まれる揺らめくようにダンサブルなビートや、ひらひらと変化する楽曲の展開が相互作用を起こすことでその揺蕩う浮遊感は寸分の狂いなく持続していき、淡くもあってかつ美麗なサウンドスケープには見事な水彩画を連想させられるのです。
この現実離れした透明感が如何に堅牢なものであるかは、細野晴臣の名曲『終わりの季節』をエレクトロニカで表現してみせる秀逸なカバーからも読み解けます。矢野顕子が「世界遺産」とまで賞賛した本作に明らかな彼の才能が、余りにも早くにこの世から失われたことは大きな損失と言えます。




コメント