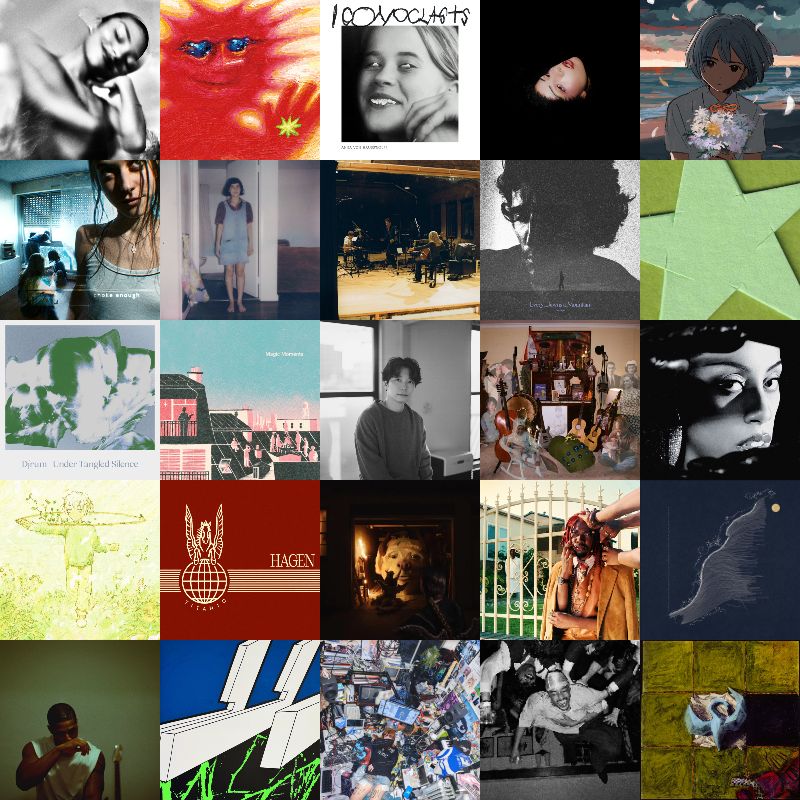
皆様、明けましておめでとうございます。2026年も、ピエールならびに「ピエールの音楽論」をよろしくお願いいたします。
年始1発目の投稿はやはりこれしかないでしょう。2025年の年間ベストです。
昨年は本当にリスナーとして満足のいく1年だったといいますか、いろんな点で成長できたような気がしています。それは旧譜との出会いのおかげでもありますけど、それ以上にやはり新譜に学んだことがとても多かった。将来自分のリスナー遍歴を振り返ったとしても、2025年は何かエポックメイキングな1年になってくれているんじゃないでしょうか。
そう思わせてくれるだけのリリースが山程あった2025年。その中から例年通り独断と偏見、そして愛に基づいて選んで参りました50枚のアルバムを、レビューと共にご紹介させていただきます。各作品、Apple MusicとSpotifyのリンクを埋め込んでおりますので、ピンと来るものや聴けていなかったもの、聴いてはいたけどそんな褒めるようなもんだったか?というものまで、よければ聴いてみてください。
……ざっくり2万字は軽く越える内容なので、前置きはこの辺で。では、ピエールの選ぶ2025年ベスト・アルバムTOP50、どうぞご覧ください!
- 第50~41位
- 第50位 “Plan 75” [EP]/The Orchestra (For Now)
- 第49位 “Sincerely,”/Kali Uchis
- 第48位 “You Are The Morning”/jasmine. 4. t
- 第47位 “宇宙旅行”/田山ショーゴ
- 第46位 “Bad Dogs”/81355
- 第45位 “合歓る – walls or bridges”/Laura day romance
- 第44位 “Son Of Spergy”/Daniel Caesar
- 第43位 “Erotica Veronica”/Miya Folick
- 第42位 “物語を終わりにしよう”/想像力の血
- 第41位 “45 Pounds”/YHWH nailgun
- 第40~31位
- 第40位 “A Danger To Ourselves”/Lucrecia Dalt
- 第39位 “Only Dust Remains”/Backxwash
- 第38位 “Hope Handwritten”/Hope Tala
- 第37位 “Let God Sort Em Out”/Clipse
- 第36位 “I Love My Computer”/Ninajirachi
- 第35位 “石の糸”/kanekoayano
- 第34位 “Deseo, Carne y Voluntad”/Candelabro
- 第33位 “Sortilège”/Preservation & Gabe ‘Nandez
- 第32位 “EUSEXUA”/FKA Twigs
- 第31位 “Through The Wall”/Rochelle Jordan
第50~41位
第50位 “Plan 75” [EP]/The Orchestra (For Now)

作品としてのフォーマットがそもそも別であることから、例年EPはランキングの対象外としてきました。しかし、このインディー・プログレッシヴ・ロック・バンドThe Orchestra (For Now)の”Plan 75″ はぜひとも依怙贔屓したい1枚です。2年前、Marujaを特例としたように。
牧歌的なアコースティックから開幕し、ピアノやストリングスの厳粛な表情が世界観を押し広げ、ミステリアスに展開したかと思えば狂気すらを飲み込んでしまう。プログレッシヴ・ロックの様式美に極めて忠実な1枚です。同じ視点から支持してきたMarujaやblack midiがフリーキーさを面白みとした一方、The Orchestra (For Now)は格調高さや嫋やかさにおいて秀でいているのも、かのジャンルの愛好家として愛おしいポイント。
2025年には続編的なEP”Plan 76″もリリースしている彼ら。プログレッシヴ・ロックにおいてなにより重視したいアルバム・メイクの才覚については現時点では言及できませんが、並々ならぬポテンシャルを感じさせてくれる戦慄のニューカマーであることは紛れもない事実です。
第49位 “Sincerely,”/Kali Uchis

ラテンとR&Bの両翼で上質な作品を世に放っているKali Uchisですが、しかしそれゆえに、個人的にはなかなかピントの合わないアーティストでもありました。最新作”Sincerely,”は、その点において、過去に触れてきた彼女の作品群の中でも最もフレンドリーなアルバムだったように思います。
彼女のバラッディアーとしての才能にフォーカスした、ロマンチックな楽曲の連続。ポピュラー音楽のグローバル化やR&Bの発展の可能性を重視するのであれば保守的にも捉えられかねない作品像ですが、そうした意識の一切を捨て、上質なヴォーカル作品として本作と向き合った時、その圧倒的なディーヴァとしての貫禄がどこまでも美しく聴こえてくるはずです。
2025年のR&BはDijon筆頭にスパイシーな作品も多く、今後のトレンドの萌芽となり得る音像が目立っていた一方で、本作のようなオーソドックスで職人気質なブラック・ミュージックへの言及は控えめだったかもしれません。よいメロディをよいヴォーカルが歌うという大原則に今一度立ち返るにはもってこいの作品では。
第48位 “You Are The Morning”/jasmine. 4. t

UK的な音、ないしUS的な音。ボーダレス化の進む昨今ですが、人や文化が国籍によってある程度規定される以上、音楽もまた然り。その中で、極めてUSインディー的なイギリスの新星、jasmine. 4. tの“You Are The Morning”には驚かされました。
バックにつくのは、あのboygenius。言わずと知れたUSインディーの才女3人ですが、オーガニックでドライ、そして広がりのあるバンド・アンサンブルに侘しげなメロディがひっそりと参加する様式は、まさしく彼女たちの得意分野と言えます。ストリングスが大きく貢献する表題曲など、アメリカーナを経由した現代USインディーの理想郷のよう。
単に私が触れた作品の傾向か、あるいはシーンの動向か、2025年はウェル・メイドなUSインディーが話題になることが少なかったように思います。jasmine. 4. tはそうした渇きに見事応える1枚だったと言えるのではないでしょうか。
第47位 “宇宙旅行”/田山ショーゴ

名は体を表すとはよくぞ言ったもので、新鋭 田山ショーゴの1st”宇宙旅行”の質感はこの4文字が的確に表現しています。しかしSpiritualizedと田山ショーゴを分つのは、本作における宇宙とは無限の空間ではなく内向的なそれを指している点。
ドリーム・ポップ/アンビエント・ポップのムードが一貫した酩酊感はもちろん見事ですが、それ以上に意識が向いてしまうのは彼の紡ぐメロディ。愛らしく切なげなメロディ・センスがこの音像の中でゆっくりと溶けてゆく様は、初期のスピッツ、あるいは“ヘッド博士の世界塔”に認められるポップネスの現代インディー的再構築と絶賛したくなる代物です。
このメロディのさりげなくも強烈な魅力、そして実のところバンド・サウンドが強調された輪郭ゆえ、ゆらゆらと広がるサウンドスケープをもってしても本作の印象は内的なものとして決着しているのです。2025年でも際立って秀逸な国産インディー・ポップでした。
第46位 “Bad Dogs”/81355

ロック/ヒップホップの二項対立は、ごく一部の老耄を除きリスナーの意識からは消え去ったと言えるでしょう。それでもなお、81355の”Bad Dogs”ほど、音楽的にその両者の均衡を示した作品には初めて触れました。
スタジオ・ワーク、あるいはコンピュータ制御の痕跡は、もちろん本作の随所にあります。その上でメロウなフロウを紡ぐのですから当然ヒップホップとして受け止めたくなるのですが、ドライなドラムやギターの柔らかさ、そしてそのダイナミズムに触れてしまうと、インディー・ロックにしか聴こえなくなってしまう。この接続をなんとも自然に果たすのですから末恐ろしい。
あまりに親しみ深いこの両者のマリアージュは、きっと過去にも例があるはず。そういった意味での先駆性にはあるいは欠けるのかもしれませんが、この手があったかと思わず膝を打ってしまった事実を重く見て、この1枚を個人的な重要作の1つに挙げたいと思います。
第45位 “合歓る – walls or bridges”/Laura day romance


2025年の初頭、Laura day romanceは2部作“合歓る”の前編”walls”で現行国産インディーの充実を物語りました。そして2025年の暮れ、Laura day romanceは後編”bridges”でその先へ歩もうとする挑戦を鳴らしてみせます。
ポスト羊文学的なギター・オルタナティヴに傾倒した前編、そしてエレクトロに起因するサウンドスケープやビートの面白さを主張した後編。ただトータリティを放棄したのではなく、2部作にする必然性がそこには確かに聴き取れます。かつ、まさしく微睡みの中を思わせる、リアリティと夢想の境界を揺蕩うようなソング・ライティングが通底している点も喜ばしい。
2026年以降、Laura day romanceの存在感はますます拡大していくことでしょう。それはSuchmosや羊文学が通った、ときに不本意なJ-Pop化と表裏一体なのかもしれません。しかしこの良心的な野心作”合歓る”2部作がある以上、このバンドが道を違えることはしばらくはなさそうです。
第44位 “Son Of Spergy”/Daniel Caesar
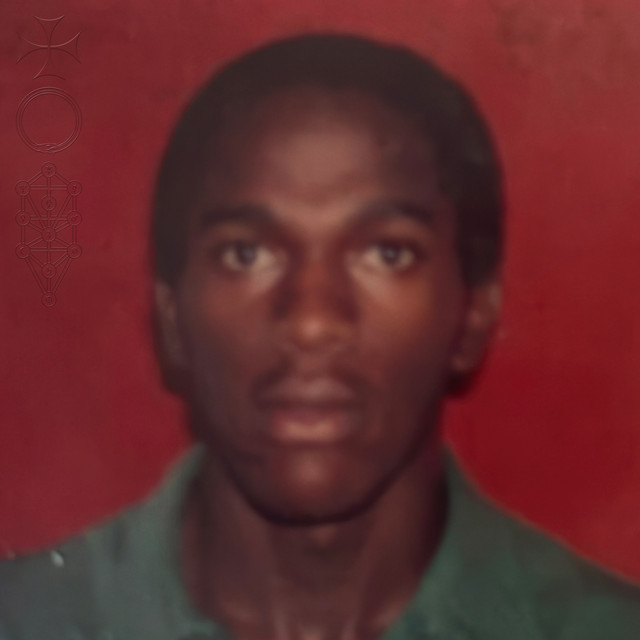
Bon IverにSamphaにBlood Orange。この錚々たる面々を従えて、Daniel Caesarは、この“Son Of Spergy”であくまで内省に終始してみせます。さながら本作は、リッチな修辞に満ちた日記帳のよう。
現代的なR&Bやゴスペル、ロマンチックなサイケデリアにも立ち寄りながら、その軸となるのはフォーキーな弾き語りというスタイル。前作“Never Enough”で示したアンビバレントな奥行も見事でしたが、彼はこの作品で1つのフォームを手繰り寄せました。それがフォークというのはやや意外でしたが、味わい深い佳作の並んだ出来栄えはSSWアルバムとして上質です。
その顔ぶれや、またDaniel Caesar自身トレンドセッターになり得る逸材であることを踏まえれば、やや小規模にまとまってしまった感があるのは事実でしょう。しかし、そのこじんまりしたパーソナルな音楽こそが狙いなのですから、私もごく個人的に、本作を愛聴することにします。
第43位 “Erotica Veronica”/Miya Folick

冒頭の”Erotica”を聴けば、なるほど繊細さと純朴なメロディ・センスで聴かせるインディー・フォークかと、そう”Erotica Veronica”を解釈することでしょう。それがいかに短慮であるか、Miya Folickは手を尽くして語りかけてくれます。
キュートなシンセサイザーやフォークと呼ぶにはポジティヴすぎるポップ・センスが飛び出したかと思えば、”Fist”ではスケールの上昇とともに情念的な歌声を聴かせるオルタナティヴ・ロックを表現。クローゼットを引っ掻き回してお気に入りの1着を探すように、気ままにフォーク/ポップ/ロックを行き来する様が痛快です。
そしてなお痛快なのが、そのどれもがMiya Folickによく映えている点。スタイルや音楽性に振り回されることなく、あくまで気ままに、今日のインディー・シーンにおける女性の活躍をダイジェストした秀逸な1枚では。
第42位 “物語を終わりにしよう”/想像力の血
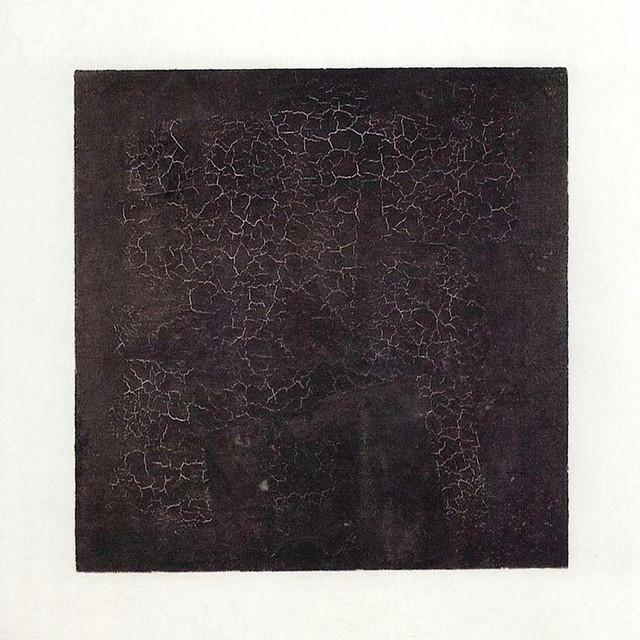
佐藤優介(カメラ=万年筆)のソロ・プロジェクト、想像力の血。本名義での1stアルバムで早速”物語を終わりにしよう”と提言してしまう大胆不敵ぶりは、エクスペリメンタルJ-Popと表現したい本作の音像を聴けば、より直截的に伝わってくるでしょう。
どの楽曲にも注目に値するトリックが仕掛けられており、ストリングスかあらデジタル・ノイズまで、プロダクション上の遊び心に満ちた1枚であることは明白です。その反動としてメロディの主張は弱くなり、種々のいたずらごころの中に埋没しているよう。彼のSSWとしての才能は後景化しているようでもありますが、実態はむしろ逆。
彼がやんちゃに振る舞ってみせればその分だけ、このアルバムにおけるポップネスが空気のように前提として機能していることに気づかされます。ポップであることをサウンドの大胆さのエクスキューズにしてしまう、意外にも堅実な作品でもあるのでしょう。J-Popのカルト名作として、長く聴かれ継ぐべき作品です。
第41位 “45 Pounds”/YHWH nailgun
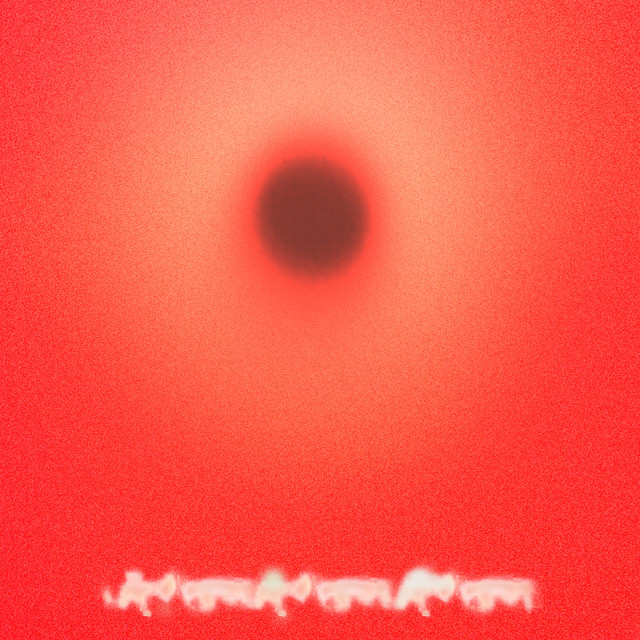
2025年は、ロックを面白がることが少なかったように思います。その中にあって、形骸化されたジャンル名としてでない「オルタナティヴ」を鳴らしたYHWH nailgunの”45 Pounds”は、ぜひとも記憶に留めておきたい1枚。
散弾銃のごとき無情なビートが襲い掛かり、シンセサイザーやギターはサウンド・メイクのどぎつさを隠そうとせず、ヴォーカルはそれらと交わることなく独自に嘯いている……無表情な躍動感、支離滅裂な理性といった矛盾を表現する様は、Talking Headsがデジタルに武装して暴動を起こしているかのようです。ことユニークさにおいては、2025年でも出色の仕上がりでは。
ポストパンク、エクスペリメンタル、それこそオルタナティヴ、本作をラベリングすることはこれらの語彙によって一旦は可能です。ただ、その行為は本作の爆裂な個性を陳腐化するに過ぎません。21分にわたる機銃掃射に打ちのめされれば、もう十二分に本作は掴み取れるのですから。
第40~31位
第40位 “A Danger To Ourselves”/Lucrecia Dalt

前作”¡ay!”での賞賛によって、私にとってお目通りの叶ったコロンビア出身の鬼才Lucrecia Dalt。その彼女の新作というだけで心弾みますが、まさか”A Danger To Ourselves”でパートナーシップを結んだのがかのDavid Sylvianとは。
前作時点で彼女の大胆さは明らかでしたが、無情なインダストリアルからドラマチックな弦楽まで、その凍てついたサウンドへの執心は依然として容赦がありません。その中で展開されるアンビエント的な瞬間や個性的に跳ね回る電子音に、そしてそこから不気味に生じるリラックスに、David Sylvianの生き霊を見てしまうのは先入観からくる幻視では決してないでしょう。
これほどまでに緻密難解に構築されたアルバムでありながら、あくまでDaltは歌い続けている点も私にとっては重要な事実。あまりに味気ない結びの虚無感も、本作がプロダクション的な実験であればあり得ない印象でしょう。この作品もまた、2025年に出会えた素晴らしいポップスの1つ。
第39位 “Only Dust Remains”/Backxwash

ザンビアに生まれ、現在はカナダ モントリオールを拠点とするラッパー Backxwash。自身のXで彼女はアナーキストを自称していますが、コンシャスと呼ぶには苛烈なそのポジションは、土着とハードコアに思わずむせ返る”Only Dust Remains”を聴けば合点のいくところでしょう。
トラップ・メタルのエッジをアフリカンな生命力で包み込み、それすらを突き破ってアブストラクトに畳み掛け、なお追いすがるように母なる大地と宗教的なニュアンスが迫り来る、この両輪で進行する展開の圧迫感たるや。それらを従え、吐き捨てるようなフロウで主張する貫禄と気迫は、アルバムの突破力をいっそうブーストしています。
民族性、ロック的、濃度。これらのテーマが連想させるのは、昨年Tyler, The Creatorがドロップした”CHROMAKOPIA”のリード曲”Noid”の色調です。あちらよりいっそうストイックでいっそうタフ、そして比にならぬほどアンダーグラウンドな本作は、2025年ヒップホップの重要な収穫の1つ。
第38位 “Hope Handwritten”/Hope Tala

Hope Talaのデビュー・アルバムは、当初2021年には発表される手筈だったと言います。しかし彼女は妥協を許さず、4年にわたる洗練を自身に課しました。結果として、この”Hope Handwritten”のきめ細やかさが生まれたのですから天晴な采配。
ベースとなるのはUKらしい格調を伴ったネオ・ソウルですが、彼女はそのシックなムードにボサノヴァを持ち込みました。囁くような彼女の歌声やアコースティック・ギターの爪弾きからは羽が生えたような軽やかさが感じられ、またSSW然とした身近さもふとした瞬間によぎっていきます。
2025年のイギリスでブラック・ミュージックのフィールに基づく女性シンガーとなると、もう1人のディーヴァが今年は話題を掻っ攫った感もあります。その一方、思わず手に取ってしまうキュートでフレンドリーな名盤として、本作も忘れたくはないものです。
第37位 “Let God Sort Em Out”/Clipse
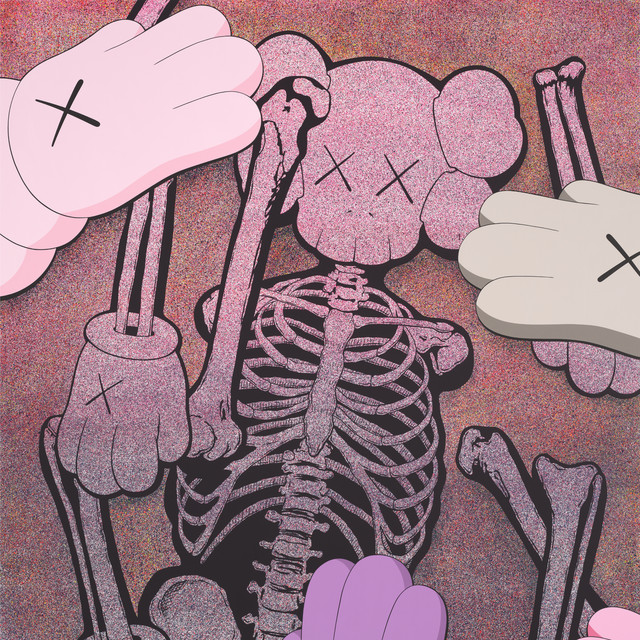
USチャートのトップ40からヒップホップが姿を消した。2025年における大きなニュースとして記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。その中で、Pusha TとMaliceのタッグClipseが”Let God Sort Em Out”で帰還を果たしたことは、多くのヒップホップ・ファンにとって拠り所となる吉報だったに違いありません。
本作におけるMVPはやはりPharrell Williams。痺れるフックと豊かなグルーヴが同居した巧みなトラック・メイクが遺憾なく発揮され、Clipseのプレゼンスとの相性はもはや言うまでもありません。加えて客演するのがTyler, The CreatorにKendrick Lamar、そしてNasというゴージャスぶりなのですから、ヒップホップ勝利の法的式を完遂した全方面的にハイ・レベルなヒップホップ・アルバムとなっています。
もっとも、ベテランがどれだけ気を吐いたとしても、シーンの活発化には血気盛んな若者が不可欠。本作がそのカンフル剤となるかどうかは定かではありませんが、何もトラップだけがヒップホップではないということを、流石の貫禄を伴ってシーンに叩きつけた重厚な名盤であることは事実。
第36位 “I Love My Computer”/Ninajirachi

オーストラリアの女性DJ、Ninajirachiの”I Love My Computer”は残酷な1枚とも言えるでしょう。2010年代はもはやリバイバルの対象であり、ビビッドな電子音はノスタルジーをすら含む代物であることを証明してしまうという意味で。
EDMやハイパーポップといった、10sを彩った電子音楽の賑やかさを彼女は巧妙に掴み取っています。その一方、雑多な自室に横たわる彼女のポートレートの印象通り、ベッドルーム的なアプローチから生じるパーソナルな質感も同居しているのが見事。クラブで轟くダンス・ミュージックとしても、インディー・エレクトロニカとしても秀逸な作品にまとめ上げているのです。
2024年の「BRAT Summer」を受け、2025年においても様々な示唆が提示された現代エレクトロ。その一方で、”I Love My Computer”という宣言に違わぬ単純な無邪気さが痛快な本作も、同時に記憶に留めておく価値があるのでは。
第35位 “石の糸”/kanekoayano

ロックはなにもバンドにこだわらずとも表現可能、そのことはカネコアヤノ自身がよく承知しているところでしょう。その彼女だからこそ、kanekoayano名義での初となるバンド作品”石の糸”での差別化が鮮やかに映えているのです。
ファジーなギターに無表情のドラム、鳴らされるバンド・サウンドは実にぶっきらぼうです。そこに挟み込まれるサイケデリアがカネコアヤノの個性的な歌声と重なることで、彼女が元来得意とする圧倒的なリアリティは非実存のヴェールを纏い、過去作にはなかった温度感を獲得するに至っています。
しかしその非実存のヴェールが、彼女の才能のシルエットをむしろ際立たせている点はぜひ注目すべき。全てを背負うSSWではなく、バンドという形態であるからこそ放たれたであろう、彼女の新たなる代表作。
第34位 “Deseo, Carne y Voluntad”/Candelabro

模倣、咀嚼、再構築の手順でシーンが構築され、アーティストの影響が確立されるのであれば、チリのインディー・バンドCandelabroの”Deseo, Carne y Voluntad”は、バンド自身と同時にBlack Country, New Roadの名声をも高めてしまいかねない作品でした。
金管楽器も交えつつ、時に牧歌的、時に狂気的に展開されるインディー・ロック。まさしくBC,NRが1stから2ndにかけて示したサウンドを踏襲しながらも、茶目っ気や情熱といったCandelabroならではの表情も当然存在しています。これすなわち、模倣、咀嚼、再構築の手続をすでに完了し、サウス・ロンドンから遠く離れたチリでウィンドミル・シーンを再現しているということ。
新譜のリリースをチェックしはじめて4年になりますが、こうもダイレクトな影響が音像に刻まれた例に出会えたのは初めてのことのように思います。それも、地理的な接続が一切なく。「トロピカーナ」に明らかな南米大陸の貪欲さと理解度が、インディー・ロックの時代においても健在であることを聴かせてくれた絶好の1枚。
第33位 “Sortilège”/Preservation & Gabe ‘Nandez

Mos DefにBilly Woods、NYで暗躍する鬼才ラッパーの背後にはPreservationの姿も確かにあります。彼がGabe ‘Nandezとタッグを組んでリリースした”Sortilège”も、やはりと言うべきか、不吉に蠢くヒップホップの名作でした。
サックスやピアノが這い回る生々しいトラックは、ブラック・ミュージックの持つ猥雑さを厭らしくもドープに表現。Gabe ‘Nandezのくぐもったフロウがそこへとまとわりついて生まれるブラックネス、その埃っぽさとどこか醒めた温度感は、ある時期のSly Stoneをすら彷彿とさせる仕上がりです。
紛れもなくアンダーグラウンドな作品ではある一方、本作の黒さはよくよく聴くとオーセンティックな類のものでもあります。ソウル/R&B的な感性のチャンネルで立ち向かったとしても、面白い表情が見えてくる1枚なのでは。
第32位 “EUSEXUA”/FKA Twigs

FKA TwigsがしばしばBjörkと比較されるのは、ごく自然な接続として受け止めてきました。その上で、彼女は久方ぶりのアルバム・メイクとなった”EUSEXUA”で、”Ray Of Light”の時期のMadonnaをも巻き込み、エレクトロ・ダンスをしなやかに演じてみせました。
それこそBjörkとも繋がるであろうエクスペリメンタルな切れ味がこれまでのFKA Twigsには目立ちましたが、本作は格段にキャッチーにまとまっています。エレクトロが静かに跳ね回る中にあって、彼女のヴォーカルは凛とした面持ちを崩すことなく、メロディの方面からも楽しむことが容易に可能。
モノクロームのようでカラフルでもある、実に独特な色彩感覚の電子音はやはり流石の手腕ですが、それをこうもポップに出力できるアーティストだとは思っておりませんでした。今にして思えば、個人的に大いにエレクトロづいた2025年の前触れだったのかもしれません。
第31位 “Through The Wall”/Rochelle Jordan

シンプルなアートワークに写された、Rochelle Jordanの鋭い眼光。その吸い込まれそうな妖艶さと力強いしなやかさを、2025年屈指のダンス・ミュージックであった本作”Through The Wall”は余すことなく表現しています。
ビートはシャープに主張しつつ、淑やかなエレクトロが包み込むように広がることで、静かに体を揺らしたくなるシックなダンサビリティを展開。加えて、作品に寄り添った抑制的な振る舞いでこそありますが、Jordanのヴォーカルにフォーカスした「歌モノ」でもあり、UKガラージのようなクラブ・シーンとも接続しつつも聴き味としてはたいへんにポップに仕上がっています。
ディープで内向きな作品ながらどこかディスコを連想させられるのは、そのキャッチーさゆえに直感的に楽しめる音楽だからなのでしょう。この直感を、ポップ・スターの膂力をもって外向きに放射したBeyoncéの傑作”Renaissance”と対比して語りたくなるのは私だけでしょうか。

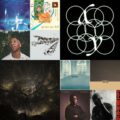
コメント