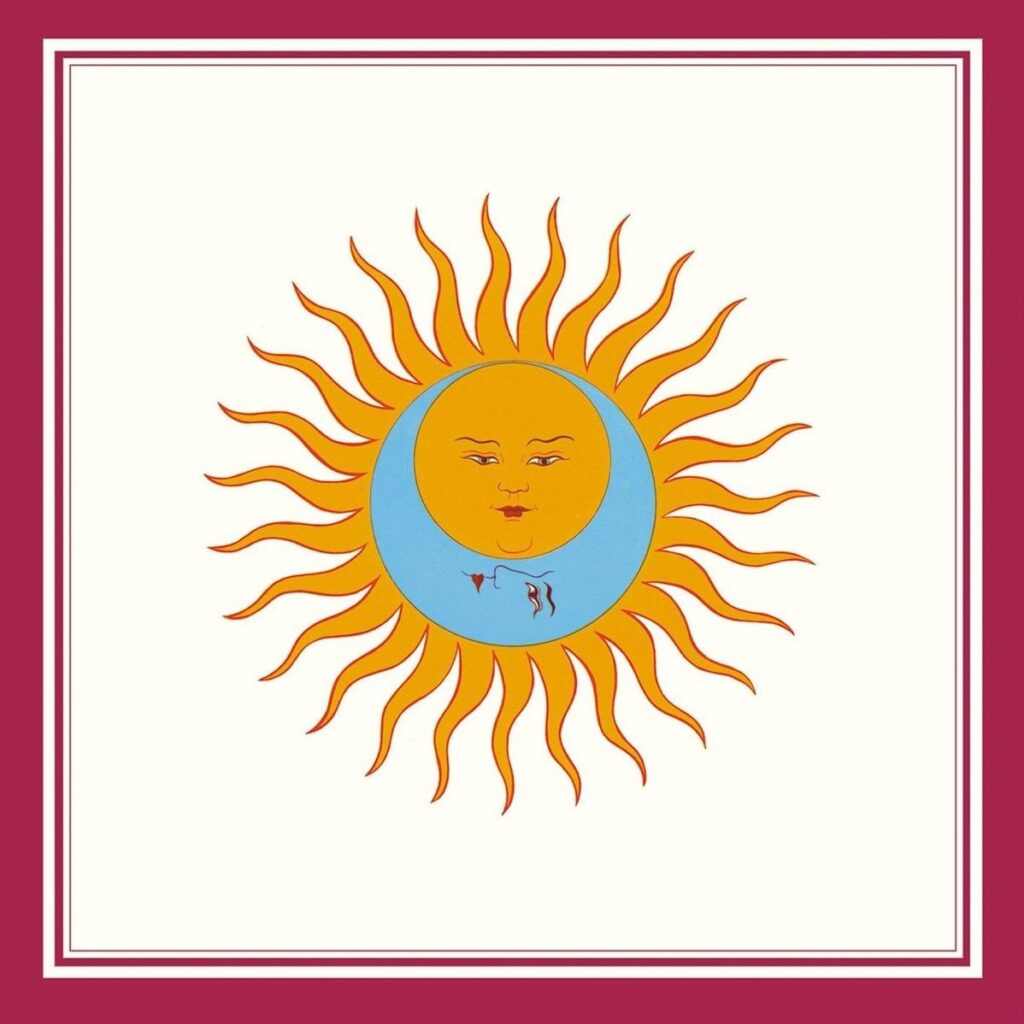
先日、といっても結構前の話ですけど、キング・クリムゾンの来日公演に足を運びまして。
今回の来日で都合3度目となる彼らのコンサートでしたが、いやはや圧巻でしたね。そもそも2021年にキング・クリムゾンを拝めるとは思っていませんでしたから。色んな意味で。
で、ブログの方も大きな企画をいくつか終えて、通常運営のアルバム・レビューに戻るタイミングだったので、ちょうどいい機会ですし今回はキング・クリムゾンのレビューと参りましょう。今回扱うのは『太陽と戦慄』。
個人的にクリムゾンで一番好きなアルバムなんですよね。ええ、いの一番にレビューを敢行した『クリムゾン・キングの宮殿』以上に。
なぜ私がこの作品をクリムゾン最愛の作品としているのか、その辺りも踏まえつつ、この作品を紐解いていきましょう。
『太陽と戦慄』参加メンバー
まずはこの作品が制作された経緯から見ていきましょうか。
プログレ界隈では有名な話ですが、実は本作発表以前に一度クリムゾンは解散しているんですよ。作品でいうと『アイランズ』発表のタイミングですね。
理由としてはよくあるアレですよ、「音楽性の違い」って奴です。バンドの核であるロバート・フリップはその辺かなり神経質な人物なので、必然の解散といったところでしょう。
ただ、そのフリップに衝撃を与えたのがビル・ブラフォード。当時プログレッシヴ・ロックの雄、イエスのドラマーだった人物です。(イエスの名盤『危機』のレビューはこちらから。)
さっきも言ったようにフリップは音楽に妥協を許さない、悪く言えばワガママな人物ですから、彼のドラムに惚れ込んでからの動きは迅速ですよ。すぐにブラフォードをイエスから引き抜き、腕利きのミュージシャンを集めて新生キング・クリムゾン結成に乗り出します。
そうして集まったメンバーが、ギターのロバート・フリップ、ドラムのビル・ブラフォードに加えて、ベース・ヴォーカルのジョン・ウェットン、ヴァイオリンのデヴィッド・クロス、そしてパーカッションのジェイミー・ミューアという布陣です。
そしてこの布陣こそ、キング・クリムゾンの数ある編成のうち最良のラインナップなんですよ。もう苛烈と言ってもいいひりついた演奏、それこそフリップの理想だった訳ですが、それを完全に表現できる完璧な面々です。
「キング・クリムゾン」の確立
各楽曲について見ていく前に、ここも大事なポイントです。この『太陽と戦慄』は、今日に至るまで続くキング・クリムゾンのレガシーを決定づけた作品なんですよ。
より具体的に言語化すると、「ジャズの延長線上にあるメタリックなグルーヴ」、この確立を果たしたのが『太陽と戦慄』だと思っています。
それまでのクリムゾンって、『21世紀の精神異常者』のイメージが先行しがちですけど、シンフォニックな展開も多いバンドだったんですよ。楽曲で挙げていくと『エピタフ』や『クリムゾン・キングの宮殿』、それに『ピース』や『アイランズ』なんかですね。
ただ、この『太陽と戦慄』に至ってはその色彩がぐっと減退しています。というより、あるにはあるんですけど苛烈さや無機質さがそれをかき消してしまっている。
で、本作以降のクリムゾンって無機質さを妙味としたサウンドを展開していくじゃないですか。それは1980年代の『ディシプリン』期もそうだし、「ヌーヴォ・メタル」期にしてもそう。
その方向性って、本作の成功があったからこそだと思うんですよ。あるいは、フリップの思い描いていたサウンドをようやく実現できたのが本作だったというべきか。
そう、キング・クリムゾンの重要なターニング・ポイントこそがこの『太陽と戦慄』なんですよね。
余談〜『太陽と戦慄』という邦題について〜
これも一応触れておきましょう。『太陽と戦慄』という世にも素晴らしい邦題についてです。
プログレの世界における邦題ってかなり重要な存在ですよね。『狂気』に『原子心母』、『危機』に『怪奇骨董音楽箱』、素晴らしい邦題揃いのジャンルです。当時のレーベル担当者の努力が垣間見えますね。
そしてこの『太陽と戦慄』も例に漏れず名邦題といっていいものだと思うんですけど、これかなり独創性高いんですよ。なにせ原題の”Larks’ Tongues In Aspic”を直訳すると「雲雀の舌のゼリー寄せ」ですから。
中国の宮廷料理がモチーフらしいんですけど、流石に「キング・クリムゾンの新譜!『雲雀の舌のゼリー寄せ』!」では売れないじゃないですか。そこでアートワークに描かれた太陽のイラストに着想を得て、『太陽と戦慄』と。
当のフリップはこのタイトルにあまり納得していないらしいんですけど、日本人ならおそらく1人の漏れなく邦題の方で扱うと思いますから。だって『太陽と戦慄』の「太陽と戦慄」感すごくないですか?このキレキレのセンス、外山恵一氏には感謝しかありません。
作品解説
さて、そろそろ中身を見ていきましょう。今回も『宮殿』のレビュー同様、楽曲それぞれにコメントしていくスタイルで。何しろ6曲しかないですからね。
『太陽と戦慄 パートI』
開幕を告げるのは表題曲、『太陽と戦慄』組曲の第1章です。
この曲のイントロ、いいですよね。どこか中華王朝を彷彿とさせるエスニックなカリンバが煌めき、鳥のさえずりのようなヴァイオリンが遠くに聴こえる。と思えば小川のせせらぎにも似たシンバルが挿入されます。
……このパートが終わるまで、実に3分余り。普通のバンドならこれで1曲な訳ですからね。いやあ、惚れ惚れするほどプログレです。
で、ここからですよね。ヴァイオリンが突如として登場し、風向きが変わります。フリップのギターも満を持して参加、冷酷な緊張感が作品を満たしていきます。
そして、その緊張の糸がプツリと切れたかのように展開されるは轟音のアンサンブル。しかし、このアンサンブルもすっと身を引き、緊張感を醸成するヴァイオリンに道を譲る……そしてまたしても轟音。この「静と動」の表現、もう卓抜していますね。
そこからは如何にもキング・クリムゾンな、ポリリズムの応酬です。まあまあ何やってるかわからないんですが、聴きものはリズム隊でしょうね。ジョン・ウェットンとビル・ブラフォード、それにジェイミー・ミューアの3人です。
この緊張感って、ほんの僅かにでも綻びがあると表現できないはずなんです。プレイヤーには尋常ならざる集中力とスキルが求められる。それに応えて余りある、激しくも無機質なアンサンブル。お見事です。
後半からはヴァイオリンとパーカッションを軸に据えた静謐な展開に。イントロ同様、アジアンなテイストを感じさせるサウンドには思わず唸ってしまいます。ここにもやはり、本作最大の魅力である「静と動」の妙を発見できますね。
これで終わると思いました?もう一山あるに決まってるでしょ、プログレですよ?
フリップのギターとクロスのヴァイオリンが先ほどまでの叙情性を搔き消し、不穏さを演出するようにゆっくりとやってきます。そしてそのカタルシスがまたも爆発……不穏なムードを残したまま終幕です。
ここまで実に13分。大曲と呼ぶに相応しいですね。ただ、退屈さとは無縁です。少なくともプログレ・ファンにとってはね。特殊な訓練を受けていない方は3分間のイントロでぐっすりでしょう。そして轟音で叩き起こされることでしょう。
執拗なまでに「静と動」を行き交う展開。これはそれまでのクリムゾンにはなかった手法です。それを表現できるのは、このラインナップなればこそ。一分の隙もない苛烈さと美麗さの共存には寒気すら覚えますよ。
……あ、ちなみにインストゥルメンタルです。13分インストなんてザラですからね。これくらいで根をあげてると『チューブラー・ベルズ』聴けませんよ。
『土曜日の本』〜『放浪者』
1曲目があまりにヘヴィなので、ここはまとめておこうと思います。A面に残る2曲、『土曜日の本』と『放浪者』ですね。
性質としてはかなり近い楽曲だと思うんですよね。旧来のクリムゾンのモードを継承した、シンフォニックな作りのナンバーです。「静と動」でいうと「静」を強調したセクションですね。
これがまたニクいところで。『太陽と戦慄 パートI』のヘヴィネスをバンドも了解しているからこそ、ここで一息つかせようというんです。こういう、作品として聴かせる心配り、アルバムで聴くことが当たり前の時代ならではですよね。
『土曜日の本』は本当にこじんまりした楽曲なんですけど、『放浪者』は実は8分弱くらいあります。ただサラリとした印象があるのも事実で、それはどういうことかというと、ジョン・ウェットンの歌声にカラクリがあると個人的には見ていて。
ようやくシンガーとしてのウェットンに言及できますが、彼の歌声って素晴らしいと思いませんか?男性的な艶がある、すごく温かみのある歌声。徹底的に冷酷な序曲で凍てついた世界観をゆっくりと溶かすような作用があるように思います。
もちろんそこにはヴァイオリンや、叙情的なギターも一役買っていますが。そうそう、『放浪者』で聴けるフリップのギターのトーン、後の大名曲『スターレス』にそのまま接続できるものだと思います。あの曲の前半部も沈痛ながら叙情的ですからね。この曲が『スターレス』に発展した、というのは贔屓しすぎですけど。
『イージー・マネー』
ここからレコードではB面です。後半戦の開幕は名曲『イージー・マネー』。
イントロの非情なまでにヘヴィなギター・リフもインパクトがありますが、それ以上に意識を持っていくのがウェットンのスキャットですね。気味が悪いくらいキャッチーです。クリムゾンにキャッチーさはかけらも求めてませんが、それでも耳を引きますね。
さっきウェットンのヴォーカルを温かみがあるなんて表現しましたが、この曲では打って変わって楽曲の冷酷さに寄り添う冷たさと迫力を見せています。この振れ幅も、彼のシンガーとしての凄さですね。あくまで作品に奉仕する、楽器としての歌声というか。
この曲の面白いところって、歌が入ってきてからのリズムですよね。一聴する限りでは変拍子っぽいんですけど、ちゃんとリズム追いかけると実はこれただの4拍子なんです。
そこもこの曲のとっつきやすさ、気味の悪いキャッチーさに貢献しているんじゃないでしょうか。「歌モノ」と言ってしまえる構成なんですよ。『太陽と戦慄』の中で最も暗い楽曲だというのにね。
『トーキング・ドラム』
アルバムも終盤、ここで登場するのが『トーキング・ドラム』です。
タイトルの由来は西アフリカで伝統的な鼓の演奏法から。イントロで披露される、ジェイミー・ミューアのパーカッション・プレイがこの奏法を用いているようです。
このパーカッション、本当に素晴らしいんですよね。打楽器でありながらテンションを自在に操り、音階を生み出しています。トーキングドラムという奏法が元々声調の模倣からきたものらしいのでそうなるのは当然と言えば当然なんですが、まさしく妙技と呼ぶ他ありません。
ここでミューアの功績についても軽く触れておきましょうか。彼って実は本作のアンサンブルにおいてかなり重要な存在なんですよ。
ブラフォードの激情と冷酷さが共存したタイトなドラムに、細かさやけけたましさを追加する見事なプレイです。それこそ『太陽と戦慄 パートI』でも彼の役割って決して小さくありませんよ。
残念ながらクリムゾンへの参加は本作のみ、というか本作発表以前に音楽界から身を引いてしまったのが惜しい逸材です。理由は仏道の修行に入るからとかなんとか。如何にもな理由ですね。
さて、楽曲としてはこれは次曲へのプレリュードとしての機能を持っていると思います。クリムゾンってそういう舞台装置的な楽曲好きですよね。例えば『宮殿』における『ムーンチャイルド』もそうだし、『アイランズ』にはそのものズバリ『プレリュード』という楽曲が収録されていますから。
この曲が持つ意味、それは緊張感の醸成です。ギターとヴァイオリンの絡み合いによるスリリングな音像なんですが、意図的に展開が抑圧されていると思うんですよ。思わず息の詰まる、逃げ場のない緊張感と圧力の演出。聴き手はいつになれば解放されるのかともがき苦しむ訳ですね。
勘のいい方はもうお気づきでしょう。その緊張感からの解放、それこそが次曲を導くものであり、本作のフィナーレの序章なのです。本当に用意周到というか、フリップの掌の上で転がされてしまいますね。何百回聴いてもここでテンションがマックスになってしまいます。ああ悔しい。
『太陽と戦慄 パートII』
『トーキング・ドラム』でこれ以上なく緻密に練り上げた閉塞感、それを切り裂くように慟哭の如きギターが意識の外からやってきます。それを鬨の声とばかりに始まるのが、最終曲『太陽と戦慄パートII』。
『ムーンチャイルド』の困惑を解き放つ『クリムゾン・キングの宮殿』のドラム・フィルも素晴らしいですけど、カタルシスではこちらに軍配が上がると思うんですよね。何しろ、この楽曲も凄まじい緊張感を伴ったものですから。一気に開けて聴き手を癒すのではなく、追い打ちをかけるような非情さ。
どうです、このリフの凶悪さ。「史上最高のリフ」なんてテーマの特集は枚挙に暇がありませんが、この曲をほぼ見かけないのは不見識としか言いようがないと思います。
リフ自体はかなりシンプルなんですけど、これでもかと言わんばかりの変拍子がいいですね。リフにまとわりつくブラフォードのドラムも常軌を逸しています。とてつもない緊張感を纏いつつも、フレージングで楽曲に混迷の色彩を加えている。なんたることでしょう。
ブラフォードは元々イエスのドラマーだったって話はさっきもしましたが、イエスというバンドがシンフォニックな雄大さを個性としたクラシック音楽的バンドであったのに対して、ブラフォードはジャズ出身のドラマーなんです。
そしてクリムゾン(≒フリップ)もジャズの即興演奏や緊張感を重要なルーツとしていますから。両者の相性は言うまでもないんですよね。それにしたってこの鬼気迫るアンサンブルは異常ですけど。
で、実はこの曲もやってることは『トーキング・ドラム』と同じなんですよ。つまり、楽曲全体を通じて緊張のヴォルテージをジリジリと上げていくんです。緊張感の形成と破壊、それを1曲の中で大きな振れ幅でやってのける『パートI』とは違って、『パートII』は小さな波によって緊張感を増していくんです。「来るべき時」のために。
楽曲の最終盤なんてもう狂気的ですよ。もうブラフォードの手数たるや尋常ではない。複雑極まりない構成の中で、凄絶なプレイを披露しています。そこに負けじと神経質な旋律で応えるクロスのヴァイオリン、相変わらず凶悪なフリップのギター。そしてウェットンのベースとミューアのパーカッションがこれらを糊付けしていくんです。どうです、この完全無欠っぷり。
でもアルバムのフィナーレですから、どこかで解決しなくちゃいけない。ここまでやってフェード・アウトは流石に竜頭蛇尾が過ぎますからね。さあどうなるかと固唾を呑んでしまう訳ですが、その解決は呆気にとられるほどシンプルです。
先ほど如何にも思わせぶりに書いた「来たるべき時」、それがここです。コーダにあたる部分ですね。終幕を予言するドラム・ロールの直後、アンサンブルが爆発四散し超新星爆発かのような爆音が轟きます。
言葉にすると乱暴に聞こえますけど、実際に聴いてみてください、これっきゃないと思わせてしまう圧巻のコーダですから。そこには感動なんてものはない、爆心地に置き去りにされた聴き手の茫然自失だけが残ります。これを狙ってやってるんですからとんでもないんですよね。
まとめ
久しぶりのアルバム・レビュー、ついつい筆が乗ってしまいました。お楽しみいただけましたか?
『宮殿』との比較が多かったと思うんですけど、クリムゾンってアルバムの様式美が結構はっきりしてるので、どうしても比較対象が出てきがちなんですよね。良し悪しという意味での比較ではなく、よりわかりやすく説明するための措置とご理解ください。
途中でも書きましたが、以降のクリムゾンのサウンドはおおよそこの作品の方向性を軸に決定されています。実際、『太陽と戦慄』組曲は続編も発表されていますからね。『レベル・ファイヴ』を含めるとパートVまで制作されていますから、どれだけ重要なレパートリーかは明らかです。
そういう方向性の確立、それはこの作品の出来栄えを端的に証明する材料でもあります。手応えがあったからこそ、その方向に進んだ訳で。
何回聴いても、タイトルの通り「戦慄」を覚える。そんな作品なかなかありません。その「戦慄」を求めて何度も何度も聴いてしまいますし、だからこそこの作品を最高作だと見なしているんです。是非ともこの作品を今一度聴いていただけたらと思います。サブスクにはないですけど、それはご愛嬌ということで。それではまた。
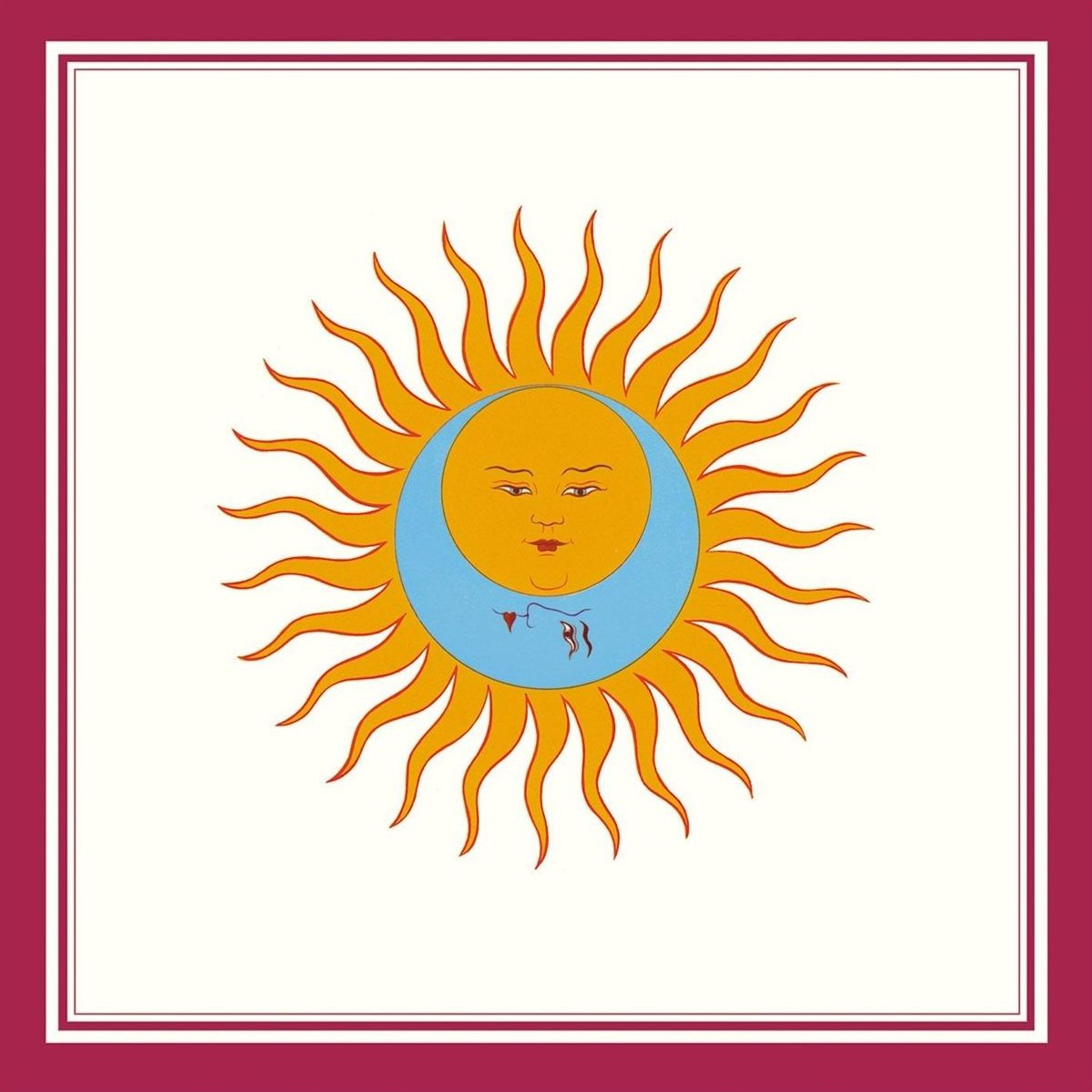



コメント