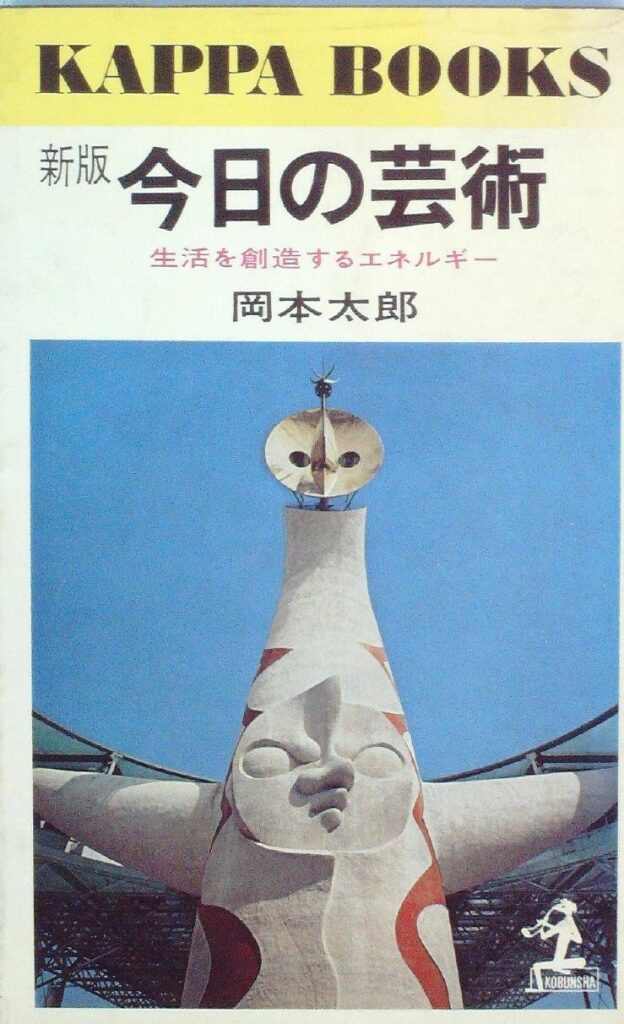
今回はみの氏の『戦いの音楽史』に続いて書評です。日本を代表する芸術家、岡本太郎が1954年に著した『今日の芸術』、こちらを紹介していきましょう。
そもそも私がこの本の存在を知ったのって、この前紹介したみの氏のYouTubeなんですよね。
彼が音楽を評論するにあたって何度もこの本から引用しているのを見て、実際に手に取ってみようと思った訳です。
とはいえこのブログはあくまで音楽を扱っていますし、音楽を軸に、この不朽の名著を私なりに解釈していきたいと思います。それでは参りましょう。
『今日の芸術』とは
「今日の芸術は、うまくあってはならない。きれいであってはならない。ここちよくあってはならない」。―斬新な画風と発言で大衆を魅了しつづけた岡本太郎。この書は、刊行当時、人々に衝撃を与え、ベストセラーとなった。彼が伝えようとしたものは何か?時を超え、新鮮な感動を呼び起こす「伝説」の名著、ついに復刻。
光文社サイトより引用
本著の内容をものすごくざっくばらんに要約すると、「芸術はみんなのもんだ、偉ぶった権威主義はクソ喰らえ、誰もが芸術家だし、そうあらねばならない」、こういった具合でしょうか。
タイトルで『今日の芸術』と銘打っていますから、岡本の芸術観が全編にわたって主張されている訳ですが、これがもういわゆる「芸術」の認識とはまるで違ったものなんです。我々が持っている思い込みや先入観をことごとく打倒していく、ちょっと不安になるくらいに大胆で痛快な主張。
彼の主張を引用しながら、それらをポピュラー音楽の世界に当てはめた時どういった理解になるのかという部分に迫っていきたいと思います。
「なぜ、芸術があるのか」
第1章「なぜ、芸術はあるのか」で、岡本は最も本質的な問いたてにいきなり答えてみせます。その問いとは
「芸術とは何か」
とんでもなく不敵な導入だと思いませんか?インテリ同士が暗い研究室でヒソヒソ語り合うような、難解で、なんとなく一般人である我々にとっては遠い世界のお話。ここからまず示してやろうという訳です。
単刀直入に言って、岡本はこの答えを「人間にとって不可欠なもの」としています。なんだか拍子抜けですね、そういうわかったような口ぶりなら私にだってできそうなもんです。ただ、もちろんそう言い捨てて終わりなんてことはありません。
この答えを述べてから、岡本は現代人(といっても1954年当時の「現代」であることは要注意。悲しいかな岡本の指摘はほとんどの部分で2021年的「現代」にも通用してしまいますが)の心に巣食う虚無感に言及していきます。
心の底からしたいことができていない、気休めの娯楽で紛らわせて、本当のよろこびを感じずに日々を惰性で過ごしている、と。どうです、恐ろしいほど思い当たる節あるでしょ?繰り返して言いますがこの本は1954年出版ですからね。
そしてその渇きを癒す手段こそが芸術、彼の言葉を借りれば
「失われた自分を回復するためのもっとも純粋で、猛烈な営み」
『今日の芸術』より引用
であると、そういうんですね。芸術をなにか小難しいものとして捉えるんではなくて、あくまで自分自身の問題として認識することが何よりも先決だと。
この「芸術は人間の生き方そのものに深く関係している」というテーゼは、この著作を貫くもっとも重要な主張です。読み進める上で、ここを常に意識する必要はある気がしますね。
「八の字」とカテゴライズ
第2章「わからないということ」の中で、岡本は「八の字」の呪縛を手厳しく批判しています。
この「八の字」というのは「富士山」を極限まで簡潔に記号化したもので、その「八の字」にはもはや富士山との関連性を見出すことはできないけれど、それを美しいものだと鵜呑みにしてしまっているのだ、こういう指摘です。
これを平たく言えば「美意識への先入観」だと思うんですよ、これまでの経験の蓄積が、「こういう特徴があれば美しい、優れたものである」という本質的でない指標を生んでしまう、この危険な発想が根付いていることに岡本は憤慨しています。
これ、音楽を鑑賞する我々もよくよく考えなければならない問題だと思います。
例えば音楽ジャンル、メタルでもポスト・ロックでもアンビエントでもいいんですが、そこには一定の性質があります。その性質に反応して、反射的に、あるいは無批判にいいものだと認識してしまっていませんか?少なくとも私はそういう傾向が自分自身にあることを否定できません。
ここを読んでいて、「君のそういったものの見方はまったく本質的ではない」と岡本先生にお叱りを受けたような気分になりました。そういう形骸化した部分ではなく、もっと作品そのものに向かい合わねばならない、そういうことなんでしょう。
デヴィッド・ボウイが体現した「精神の若さ」
第3章「新しいということは、何か」では、岡本は芸術の世界に存在する新旧世代の深い対立構造に言及していきます。
権威を獲得した旧世代が、新たな価値観を提示する新世代を凝り固まった不遜さではねつける。かつてはその旧世代も、同じように彼らにとっての権威を打倒した新世代だったはずなのに。これはもはや芸術に限った話ではありませんね、ごくごくありふれた日常にもこういった構造は浸透してしまっています。
ここに補足として岡本は、この新旧というのは単なる年齢のことではないと言っています。例え老年であろうと常に挑戦的で意欲的、新たな価値観に好意的な人間は新世代の側にあるし、その逆も然りということですね。
ここを読んでいて、私の頭にある人物の顔がクッキリと浮かんできました。
デヴィッド・ボウイです。1970年代からロック・シーンのカリスマとして活躍し、2016年に急逝するまで常に己を維新し続けた彼の姿勢は、紛れもなく岡本の言うところの新世代、「若さと新鮮さの陣営」そのもの。
ボウイのキャリアって本当に一度だって立ち止まることをしなかったじゃないですか。成功を捨て去っては次の音楽に挑戦し、さらに別の挑戦、そういう存在でした。
遺作となってしまった『★』にしたって、余命いくばくの伝説的ミュージシャンが残すような作品じゃなかった訳でしょ?最新の音楽トレンドを貪欲に吸収して、最後の最後まで「デヴィッド・ボウイ」をアップデートし続けた。彼こそ岡本の提示する芸術家像に相応しい存在なんですね。
「流行」を批判する愚かしさ
同じく第3章なんですけど、「新しいものへのひがみ」というトピックの中で岡本はまたしても旧態依然とした権威主義に噛みつきます。
その内容はというと、新しいものを「単なる流行だ、いつかは廃れる」と一蹴する人種に対する批判です。ここ、個人的に一番後ろめたい気持ちになった部分なんですよね。クラシカルな音楽を基本的に愛聴している身からすると、なくそうなくそうと思っても流行りの音楽に対してほんの少しは穿った見方をしてしまいますから。
そういう、私を含めた見る目のない人間に岡本は実に端的に論破してみせます。
「しかし、考えてごらんなさい。流行でない何がありますか。」
『今日の芸術』より引用
もうとてつもないショックでした。雷に打たれたような、そんな衝撃。「確かにそうだよな……」とぐうの音も出ませんでしたね。
私が如何にも大事そうに褒めそやすビートルズにしたってプログレにしたって、当時は流行最先端の音楽だった訳じゃないですか。そこに古色蒼然とした厳しさ、あえて厳しく表現すると権威が乗っかった途端に、それは流行じゃなかったかのように思い込むのがどれだけ愚かなことか。ものすごく反省させられました。
日本の芸術家よ、世界的たれ
まだまだ第3章へのリファレンスを続けさせてもらいます。これもすごく印象的だった主張なんですが
「今日、われわれ日本の芸術家は、むこうがこちらのものを取り入れて芸術革命をやったよりもはるかに先鋭に、欧米その他、世界じゅうの芸術形式のあらゆる課題を自分のものとしてつかみとり、自主的に新しいものをつくりあげるという段階に当然きているのです。」
『今日の芸術』より引用
邦楽がどんどん世界に発信される時代になっているのは明らかですよね。シティ・ポップのリバイバルがその一番わかりやすい例だと思うんですけど、サブスクやYouTubeの発展は日本が音楽輸出国になる土壌を既に作り上げています。
ただ、ここで肝心なのが「あらゆる課題を自分のものとしてつかみとり、自主的に新しいものをつくりあげる」、ここのところじゃないでしょうか。
ONE OK ROCKを例に出してみましょうか。日本で絶大な人気を博するロック・バンドだった彼らは、近年その活動の舞台をアメリカへ移しつつありますよね。音楽も英詞にして、より世界的なトレンドに追従した音楽を展開している。
これ自体はまったく悪いことではないと思うんですよね、ただあくまで、この「芸術」という観点から見たときに、これは果たしてアプローチとして正しいのか、そう思うわけです。欧米の音楽を取り入れるだけならば、この「自主的に新しいものをつくりあげる」という姿勢には欠いてしまう。
ここで我々が本当に意識すべきは、King Gnuや星野源といった現在日本国内で活躍するアーティストではないでしょうか。
King Gnuはケンドリック・ラマーからの影響を公言していますし、星野源はディアンジェロを音楽制作の参考にしています。その上で、彼らの音楽はどこまでも邦楽的。まさしく、岡本太郎が主張する日本のアーティストが到達すべき境地に、ポピュラー音楽というフィールドで到達していますよね。
この、日本人であることに自覚的であり、かつ世界的な感覚を有しているミュージシャンが日本国内において人気を集めるというのは本当に希望が持てる現状だと思うんですよ。彼らの活躍は数年後の日本音楽を質、あるいは精神性の部分において大きくアップデートしてくれると信じています。
アヴァンギャルド=NYパンク、モダニズム=ロンドン・パンク
これで第3章の話は最後にしましょう。まだまだ書きたいことはあるんですがこのままでは私が1冊本を書いた方が手っ取り早いくらいになってしまうので……
第3章の終わりに、岡本はアヴァンギャルドとモダニズムの対比を試みます。
「独自に先端的な課題をつくりあげ前進していく芸術家はアヴァンギャルド(前衛)です。これにたいして、それを上手にこなして、より容易な型とし、一般によろこばれるのはモダニズム(近代主義)です。」
『今日の芸術』より引用
岡本曰く、芸術家は流行を生み出すと共に、その流行の外側にいる。常に批判的に、流行が生む惰性的な価値観をよしとせず、さらに新しい方向へと邁進する存在である。他方、モダニスト(岡本は決して彼らのことを芸術家とは表現していません)は、そうした流行をより洗練させ、受容しやすいものに加工する、こういった違いがあるというのですね。
ここでポピュラー音楽の歴史に注目してみると、重要なムーヴメントの1つにパンクというものがあると思います。大衆化したロックをより表現としてピュアなものにすべくニュー・ヨークで生まれたパンクは、程なくしてロンドンに渡り、セックス・ピストルズの登場と共にUKロックに巨大な爪痕を残しました。
今ではパンクのパブリック・イメージといえばピストルズでしょうし、ロンドンこそがシーンの中心だったという誤解も広まっている感もありますが、この岡本の主張にのっとれば、極めて過激でアヴァンギャルドに思えるロンドン・パンクこそ、モダニズムの最たる例であることが見えてきます。
「新しいといわれたら、それはもうすでに新しいのではない」
『今日の芸術』より引用
と岡本は逆説的な持論を展開しますが、まったく画期的なピストルズは、この岡本の論からすれば新しくはないんです。
それに、ピストルズが実際にはマルコム・マクラーレンの巧妙なマーケティングによって登場した作為的な存在であったことはロック史の中で有名な話ですが、こういった事実も、モダニズムが持つ「流行の洗練と大衆化」という性質に奇妙なほど一致しているように個人的には思えます。
そして、そのロンドン・パンクの元ネタでありながら、決してロンドン・パンクほどに注目される機会の多くないNYパンクこそ、アヴァンギャルドで先鋭的なアートだと言えるのではないでしょうか。
そのルーツにザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドがあるというのも示唆的ですよね。彼らこそポピュラー音楽におけるアヴァンギャルドの最初期の存在ですし、元々彼らは音楽でなく芸術全般を志向するコミュニティ出身ですから。
念のため言っておきますが、これは決してNYパンクこそ優位で、ピストルズが評価するに値しないという主張ではありません。芸術として捉えた時に、両者の意義は世間一般の認識とズレが存在しているということが言いたいんです。
まとめ
音楽レビューではない投稿なので本来なら短めの記事でパパッと紹介すべきではあったんですが、あまりに内容が濃密だったので初のシリーズでお届けします。ひとまずこの記事では第3章までを扱いました。
まだまだ語るべきテーマはあるんですが、この1冊が如何に音楽を鑑賞する上で新鮮な気づきを与えてくれるかは伝わったんじゃないでしょうか?こういう驚きが、この後も山ほど登場してきます。
次回は本書の紹介にもある「芸術はうまくあってはならない」というとんでもない宣言、この辺りから始めていきたいと思います。お楽しみに。

 今日の芸術~時代を創造するものは誰か~ (光文社知恵の森文庫)
今日の芸術~時代を創造するものは誰か~ (光文社知恵の森文庫)
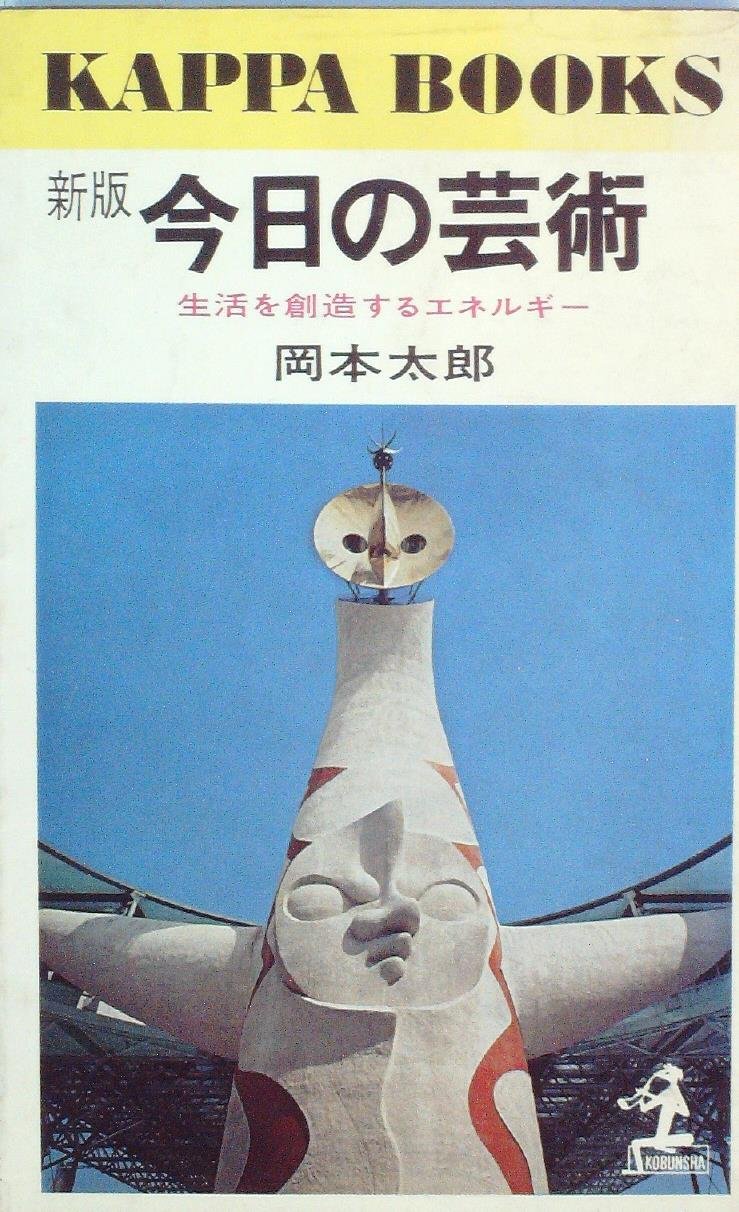


コメント