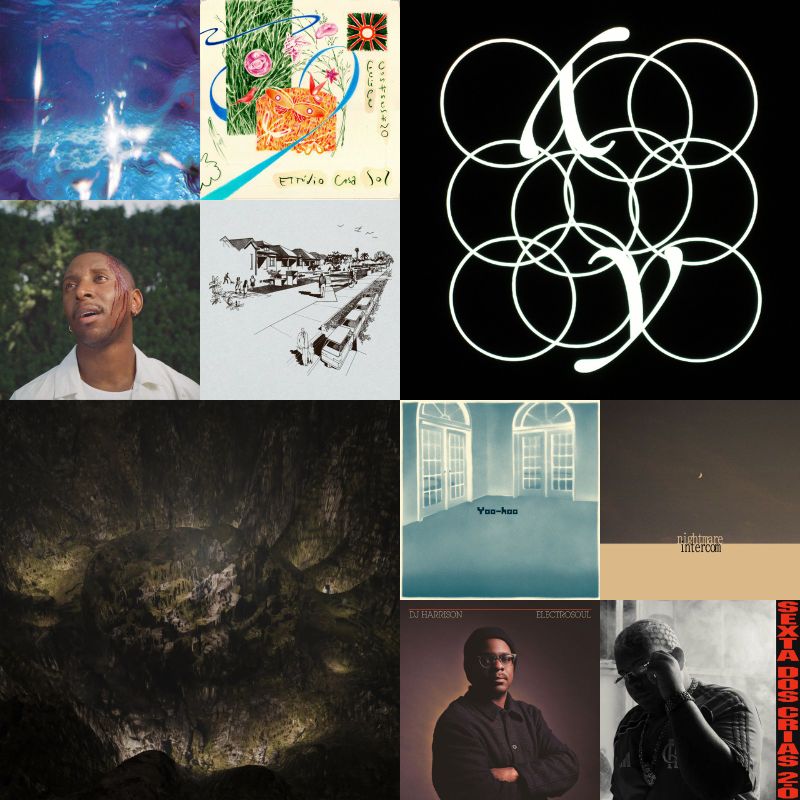
さあ、今年も1ヶ月が終わりました。ということは、この企画が始まるわけです。月例の「オススメ新譜10選」ですね。昨年までのバックナンバーは↓からどうぞ。
2024年は1~11月編まで完走(とんでもない遅延を挟みつつ)、2025年はしれっと10~11月編をパスするという、まあ言ってしまえばだらしない進行をしてきたこの企画ですが、2026年こそ、しっかりオンタイムで記録していきたいと思います。本気です。……年末の私が情けなく言い訳する様子もたやすく想像できてしまいますが。
閑話休題、1月から気になる話題はたくさん飛び込んできましたね。Harry StylesやMitski、それにFriko!といった信頼できるアーティストが次々にニュー・アルバムの制作を発表しています。それぞれのリリース・タイミングでしっかりレコメンドできる内容であることをぜひとも期待したいものですが、1月リリースも見逃せませんよ。
1月の新譜って、年間ベストなんかでもみんなうっかり忘れちゃって顧みられないこともままあるじゃないですか。そうならなかった昨年のFKA twigsは流石でしたけど、裏を返せばあれくらいのネーム・バリューと作品のインパクトがないとなかなか厳しいものがあるということ。
ですのでこの投稿でしっかりとレコメンドして、今回扱う10枚を読んでくださった皆様の記憶に残せていければと思います。それでは早速参りましょう、2026年一発目の「オススメ新譜10選」、こんなラインナップです。
“My Ghosts Go Ghost”/By Storm
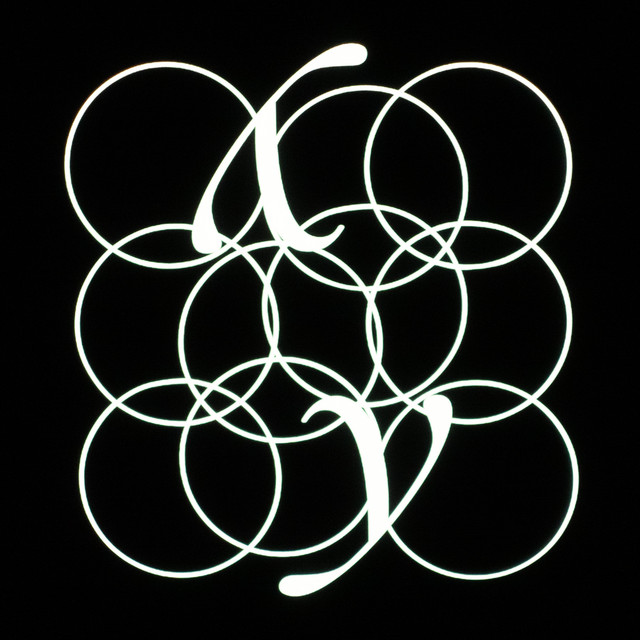
1月のハイライトは間違いなくこの1枚、どころか年間ベスト行きもほぼ確定と、この時点で言い切ってしまっていいでしょうね。ヒップホップ・グループ Injury Reserveの新たな名義、By Stormとしての再出発を飾った1枚、“My Ghosts Go Ghost”です。
Injury ReserveはメンバーのStepa J. Groggsと死別したことで、2021年の“By The Time I Get To Phoenix”(当時の年間ベストにも選んでおります、こちらも傑作!)で活動に一旦の終止符を打ちました。で、その最終作に顕著なんですが、彼らの個性はグリッチなんかも登場する電子的な圧力、混沌としたアイデアの奔流にありました。本作でもそうしたカオスは継続してはいるんですが……その深度はちょっと過去の比ではありませんね。
その途方もない深み、奈落へと落ちていく過程で、本作は様々なテクスチャとすれ違います。それは冒頭で感じられるフォークのことでもあり、“Double Trio 2”でのフリーキーなジャズのことでもあり、またbilly woodsが客演した“Best Interest”の不吉極まる室内楽でもある。こうしたジャンルの吸収……とも違うな、もっと貪欲で節操がない、捕食とでも言いたくなる、そんなアプローチを取りながら、孤高のアンダーグラウンド・ヒップホップとしてのトラックメイクを描ききってしまうんですからもう圧巻ですよ。
このジャンルというものへの態度、どうにも昨年のQuadecaと重なって思えるのは私だけでしょうか?音像そのものが似ているというわけではないですが、やりたがっていることがね。2026年のはじめの1ヶ月で、そういう「今何が起こっているのか」を聴かせてくれるような作品に出会えたのはなんとも幸先のいい話です。冒頭でも書きました通り、是非とも年末に思い出されるべき1枚であることは間違いないでしょうね。
“nightmare intercom”/Kaho Matsui

とあるフォロワーさんが「デジタルとアコースティック」というのが20’sのテーマでは?という話をよくされているんですが、私自身2025年はそれを実感できる作品にいくつも出会った気がします。その延長線上として、1月1日にリリースされたKaho Matsuiの“nightmare intercom“は秀逸だったように思いますね。
かなり抽象度の高い音像であることは事実として、生々しく歪んだギターの音色の気味のよさであるとか、無骨に主張するドラムの大胆さであるとか、そういうラウドな質感があるんですよね。この手のサウンド・プロダクションにおける近年の重要作に、Cassandra Jenkinsの“An Overview On Phenomenal Nature”があると個人的には感じているんですが、あれをもっと解像度を下げてアンビエントの曖昧さを押し出したような、そんな印象を受けます。
それでいてエレクトロによる彩色、コンピューター仕事のそれというよりは、作品のステージをわずかにフィクショナルなものに演出するエフェクト的な効果なんですが、これも心憎いですよ。アンサンブルの存在感にこの手心が加わることで、作品像がいい意味でブレている。このメリハリというにはあまりに些細な揺らぎが、作品への没入感を高めるのに一役買っています。
あまりこういう感想を抱くことはこれまでなかったんですが、これはぜひとも屋外で聴いてほしい作品ですね。音の隙間が多いので、外で聴くとなんでもないノイズ、公園で子供が元気にはしゃぐ声だったり喫茶店のキッチンが立てる物音だったり、そういうものがすっと入り込んで作品と一体化する感覚があります。こういう楽しみ方がそれこそアンビエントの妙味なのかなと、門外漢ながら思ったりする訳ですよ。
“Aquáticos”/Fabiano Do Nascimento & E Ruscha V
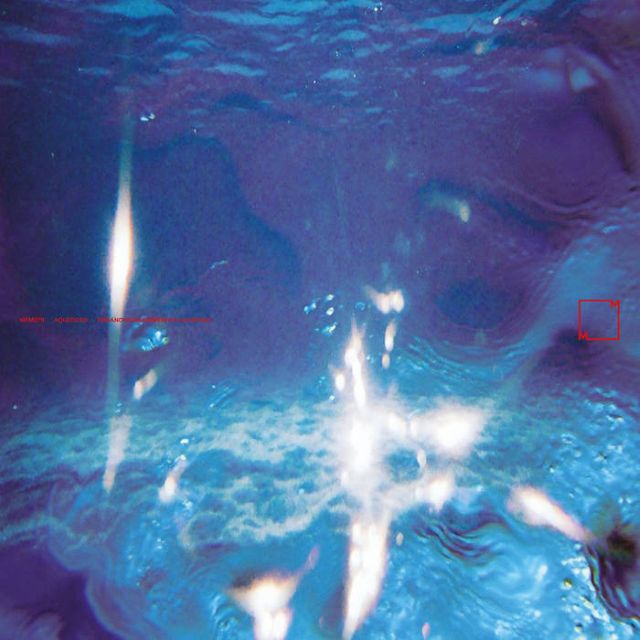
リオデジャネイロにルーツを持ち、現在はLAと東京が拠点だというFabiano Do Nascimento。Nascimentoの名を見ればブラジル系であることは多くの音楽ファンなら察せられるところですね。そんな彼がシューゲイズ・バンドMedicineのメンバーでもあるE Ruscha Vと制作したアンビエント作品が、この“Aquáticos”。
アートワークを見た時点で明らかな「水」というモチーフ。アルバム・タイトルもポルトガル語で「水の」という意味だそうですが、言葉にするまでもなく、それは音像にも存分に表現されています。ギターによるコミュニケーションを軸としながら、深く、しかし穏やかに水底へ沈んでいくような明度の高い電子音が周囲を取り囲んでいますからね。
それにやはり、ギターというロック・リスナーにとっても馴染み深い類の楽器のリアリティが感じられるのも親近感を覚えるポイントですよ。弦を爪弾く音が場合によってはかなり生々しく録音されていて、水というモチーフから連想される果てしなさやその絶望感という方面に舵を切らず、あくまで安らかに鑑賞できます。イメージを容易く惹起させるプロダクションの妙とあわせて、「何を聴けばいいのか」がクリアになっていますからね。
いきなりアンビエントの話ばっかりで、お前ホントに去年kurayamisakaをベタ褒めしてた奴と同一人物か?ともなりかねないでしょうが、2作に共通するのは、それでも楽しめちゃう明示的で雄弁なアンビエントだということ。もういっそギター・アルバムとして聴いちゃえばいいんです、そういう楽しみ方にも十二分に耐えうる肉体的な名作でもありますから。
“ヤッホー”/坂本慎太郎

続いては国内の話題作。坂本慎太郎の“ヤッホー”ですね。昨年末から先行曲はリリースされていて、相変わらず厭な音楽やってるなぁと感じたんですが、アルバム全体で通して触れるとこの印象はますます強くなりました。それと同時に、なにやら坂本慎太郎というアーティストへの理解がぐっと深まった気にもなれる1枚で。
演奏は素朴、サイケデリックにレイドバックしたソウル・ミュージックのムードが一貫していて、楽曲の展開やメロディも実にオーソドックス。なのに聴いていて居心地が悪い。この居心地の悪さというのは彼の持ち味ではありますけど、本作はなまじっかシンプルなだけにいっそう際立って感じられます。彼の甘ったるい歌声は間違いなくこの厭らしさに資するものではありつつ、やはりその最大の要因は歌詞なのかなと。
“ああ僕は 耐えられ ない どこまでも澄み切った どこまでも整った どこまでも無邪気な 正義”は本作の真骨頂と言えるラインだと思うんですが、やんわりと、ふわふわとして、それでいてえげつない「指摘」の数々。平易な言い回しに終始するからこそ、その鋭さにゾッとさせられますね。ここ数年、多くの「まともな」(この表現もマズイでしょうか?)人々が抱いているであろう焦燥感や不安、生きにくさみたいなものを鷲掴みにしてきます。この辺りについては素晴らしいインタビューがありますので共有しておきます。このライターさん、いつもいい仕事をされるんだよなぁ……

で、こういうモチーフを、攻撃や批判、あるいは悲嘆や諦念といった何かしらの温度を伴うのではなく、あくまで「常温」で届けてくる。これぞ坂本慎太郎節ですね。彼の生んだ数々の名盤でも最高の1枚”空洞です”も「常温」の作品ですけど、ある意味ではソーシャルでもあり、ある意味ではパーソナル(この2つは不可分なものではありますが)でもある本作をすら、そうしたトーンで音像とともにうっかり溶け出したかのようにやってのけるのが流石です。
“It Could Be Worse”/Samm Henshaw

UKソウルがここ数年素晴らしい成果を上げていることは、新譜をチェックされている方なら当然ご存知のはず。2025年であればOlivia Deanの大ヒットもありましたよね。2026年もSaultがアルバムを発表し、Jessie Wareが新曲をドロップと早速勢いづいていますが、その流れでSamm Henshawの“It Could Be Worse”もぜひ聴いていただきたいです。
2曲目の“Closer”、もうやることなすこと“What’s Going On ?”の世界観で笑っちゃいますよ。この曲に顕著ですが、古き良きソウル/R&Bのマナーに忠実な1枚なんですね。真摯でありつつスウィートでもある、つまりはMarvin GayeやAl Greenにも通ずるHenshawの歌声がそもそもソウル・クラシック的なところに加え、グルーヴの捉え方であったり、ストリングスやハーモニーの味つけであったり、これがいちいち技ありでね。
彼のキャリアそのものはヒップホップとも結びついたものなんですけど、本作では全てのサウンドを実際の演奏によって表現し、徹底的にヴィンテージな質感にこだわったと言います。その成果が見事に出ているし、前作“Unitdy Soul”もあわせてチェックしてみたんですが、今回の方が彼のヴォーカリストとしての魅力をより引き出せている印象です。とはいえ”Unitdy Soul”のジャズやヒップボップも主張する作風は、それはそれですこぶる名盤ではありましたが。
そうそう、ちょっと話逸れるんですが「自分は全然新譜とか聴こうってならなくて……どうすれば新譜に向き合えるんでしょうか?」みたいなことを、Xの質問箱や個人的な友人から聞かれたりするんですよ。確かに、よくわかんない横文字いっぱい出てきてよくわかんないことやってて、ハードル高く感じちゃいますよね。分かります。でも、新譜って何もそういう最先端をキャッチするためだけのものじゃないですから。少なくともこの”It Could Be Worse”は、70’sソウルの名盤が聴きたい気分の時にしっくりくる1枚なのでね。そう気負わず、いい音楽らしいから聴いてみるかでいいと思います。
“Sexta dos Crias 2.0″/DJ Ramon Sucessc

……舌の根も乾かぬうちに、よくわかんない横文字いっぱい出てくるよくわかんないことやってる作品を紹介します。DJ Ramon Sucesscの“Sexta dos Crias 2.0”、ジャンルとしては「バイレ・ファンキ」というものらしいですよ。1980年代のブラジルで成立したダンス・ミュージックとのことです。不勉強ながら、ジャンル名すら聞いたことなかったですね。あな広大なりやポピュラー音楽……
さて、このバイレ・ファンキですが、xavisphoneというアーティストの“balança e paixão”という作品のレコメンドがXで回ってきましてね。聴いてみたらばこれがまたちんぷんかんぷんだけどとんでもない圧力で聴かせる怪作で、何気ない感想をポストしたら不思議なことに伸びまして。そこから色々調べているうちに、なんでもRate Your Musicの2026年チャートの暫定首位(今はさっき紹介したBy Stormですね、納得です)もこのバイレ・ファンキだっていうじゃないですか。それこそがこの”Sexta dos Crias 2.0″です。
xavisphoneにも感じたつんのめったようなビート、これがバイレ・ファンキの個性なのかな?ただこちらは「ファンク150BPM」という名前の通りハイ・テンポなサブ・ジャンルに属するものらしく、つんのめりながら転がり込んでそのまま暴れ回る勢いが痛快です。そして何より、プロダクションのテンションの高さが異常。15分オーバーのトラックを2つ収録したのみの作品ですけど、BPMだけでなく楽曲の展開もとにかくラディカルでトゥー・マッチなので、ついていくだけでせいいっぱい。聴いていて相当疲れますが、その分退屈とは無縁のスリルが持続しています。
ここまでの書きぶりで人を選ぶ作品であることは伝わっているとかとは思いますが、話題性の意味でも、そしてもちろん作品のクオリティという意味でも、チャレンジする価値は絶対にある作品です。それに、未知の音楽に「喰らう」気持ちよさっていうのも、間違いなく新譜を聴く醍醐味ですからね。Samm HenshawとDJ Ramon Sucesscを並べてレコメンドしてるの、すごく自己満足ですけどかなりグッときます。

“ElectroSoul”/DJ Harrison

……どうです?このブラック・コンテンポラリー感満載のジャケットは。1980年のマイナー盤だと言って紹介すればそれなりの人数騙せそうな気がします。ところがどっこい、紛れもなく2026年の新譜でございますね。こちらはソウルの総本山、US産のブラック・ミュージックです。DJ Harrisonで“ElectroSoul”。
イントロを担う“Fresh Squeezed Drum”からの“OG Players”、このダイナミックな威勢のよさですっかりブラック・コンテンポラリーのことなんて忘れちゃいますよ。ただ、そこからはネオ・ソウルやヒップホップ、そしてそのルーツたるR&Bクラシックやジャズを軸にしたしっとりした作風に向かっていきます。正直、”OG Players”のようにハードでドライヴした(それこそロック的にも楽しめそうな)R&Bで1枚バシッと書いてほしかったと感じてしまいはしますが、何しろそこからも気持ちいいんだ。
このDJ Harrisonという人物、Butcher Brownというバンドの中心人物でもありトラックメイカーとしても高名なようでして。つまりは自身をアピールすることにさほど頓着のないスタイルのようで、例えば本作で最もスモーキーかつクラシカルな1曲 “It’s All Love”は 名うてのUKジャズ・シンガーであるYazmin Laceyをヴォーカルにフィーチャー。その他にもYaya BayやPink Siifu、Fly Anakinといった、新譜ウォッチャーなら思わず唸る人選によって、アイデアの手数を誇りながら良質なソウル・ミュージックを提供してくるんですね。
最初にやや揶揄するようにブラック・コンテンポラリーとは言いましたが、現代の鬼才を揃えてトラック・メイキング的で簡潔なアプローチで組み立てたR&B、これはブラコン愛好家にも届いてほしい1枚ですよ。ソウルの気持ちいいポイントを巧みで(文字面通りに)コンテンポラリーな編集手腕によってコンパクトに切り貼りした、相当に満足度の高いブラック・ミュージックだと感じます。
“Wahj”/Toni Geitani
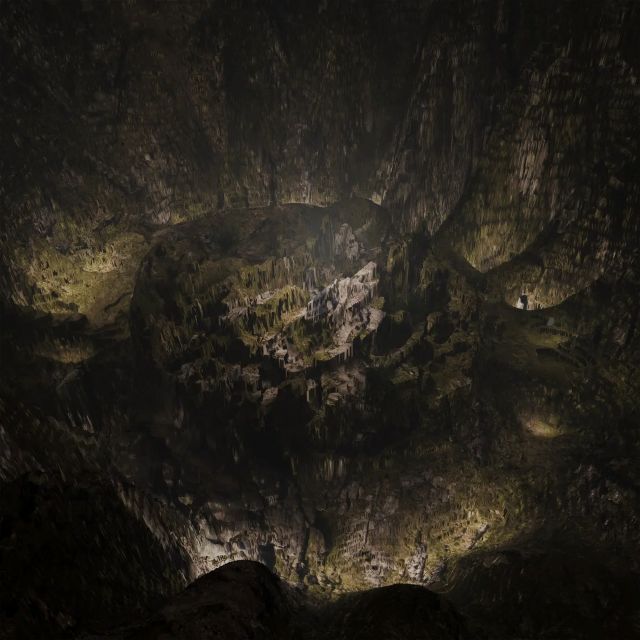
レバノン出身(このブログにレバノンの文字列が登場するのはおそらく初です)、現在はアムステルダムに拠点を置くToni Geitaniの“Wahj”。1月の新譜でも、一撃のインパクトだけならこれを超える作品はなかったように思いますね。エレクトロと室内楽のエキゾチックな接続として、脳裏に強烈にこびりつく主張の激しい1枚でした。
エレクトロや室内楽をジャンルとして引いてみたもののヴォーカルの役割はかなり大きい作品なんですが、まあどこを切り取っても過剰にドラスティックなんですよ。どこかサウンドトラック的だと私は感じたんですが、それもこの劇的な性格に由来するのでしょう。しかも、物語における情感のピークの瞬間に鳴っていそうな類の大仰さ、それが70分以上容赦なく降り注ぐわけですから、そりゃあインパクト抜群ですよね。
これほど劇的で、そして厳粛なまでの1音1音の凄みがありながら、サウンドスケープが発散していくという訳でもない。むしろ一点に収束していく、さながら蟻地獄のような引力がそこにはあります。その引力のコアとなるのは、やはりそのアラビックな個性。彼のヴォーカリゼーションにしろ、ジャジーなスウィングを伴う“Ruwaydan Ruwaydan”のアウトロで吹き荒れる管楽の音色にしろ、しっかりとリスナーの意識を引きつけるものになっていますね。
とあるフォロワーさんは本作のことを「プログレッシヴだ」とも形容されていましたが、なるほどそういう受容体もあるかと膝を打ちましたね。とはいえどのみち長いし重たいしアラビア~ンだし、気軽にすすめられるような内容ではもちろんないんですが……それでも強くオススメしたい作品です。重厚で満足感のある作品を聴きたい気分のときなんかにはピッタリじゃないかな。
“Estúdio Casa Sol”/Felipe Continentino

重たい作品の後ですから、ここらで一息つきましょう。言わずと知れたMPBの聖地の1つ、ブラジルはミナス出身のドラマー、Felipe Continentinoで“Estúdio Casa Sol”。Apple Musicには彼個人の名義の作品はこの1枚っきりなんですが、Bandcampを見るにセルフタイトル作に始まり、本作で5作目となるようです。
MPB特有の柔らかな温もりがありつつ、ジャズの冷静な知性もあり、アンビエントの透明感もあり、とにかく耳に優しい1枚という印象ですね。アンサンブルの1つ1つが、さりげなくも実に気が利いていて。4曲目の“Serra do Riacho”なんてのはアコースティック・ギターとドラムの掛け合いだけで進行する楽曲で、どちらも目立ったことはしてないんですけど、ぐっとくるフレーズを親密な距離感で聴かせてくれています。そこから仄明るいエレクトロ・ナンバー“Tide”へと繋がる流れも美しいですね。
じっくりと聴かせるタイプのアルバムで、今触れたように聴きどころもさりげないものばかり。こういう作品って聴き手に一定の緊張感を要求することが多いと思うんですが、そこにミナスの風、それこそMPBの金字塔“Clube da Esquina”にも通ずる風土があることで、サウンドの上でもリスナーの意識の上でも肩の力を抜けているのもいい仕事してます。アコースティック・ギターが軸になっているのももちろん大きな要因でしょうけど、それだけでこの朗らかさみたいな成分ってなかなか出ないと思うので。
MPB、ジャズ、アンビエントというジャンル名を出しましたが、この辺って軒並みロック/ポップスのリスナーには距離のあるジャンルだと思うんですよね。なにしろ私自身まだまだ遠くから眺める程度の理解にとどまっているので。その3つを上手く融和させて、しかも聴きやすくブレンドしてくれているんですからお誂え向きじゃないですか。作品の温度感同様、ぜひリラックスして聴いてほしいですね。
“Shaking Hand”/Shaking Hand

危うく2026年第1号からロックを選び損ねるところでしたよ。最後になんとか魅力的な1枚を紹介することができます。マンチェスターの3ピース・バンド、Shaking Handの1stアルバム“Shaking Hand”。処女作をセルフ・タイトルにする、その若々しさが眩しいと感じてしまう己の老いを感じますね。
淡々としたリズムとギターのアルペジオを軸にした、疎なアンサンブルの広がるオルタナティヴ・ロック。まあ、はっきり言って典型的ですよ。新鮮さという意味では今回ご紹介した他の9枚とは比べるらくもないでしょう。でも、その馴染みのあるスタイルの習熟が1stにしてかなり高い水準にあるんですよね。わざわざ突拍子のないことをせずとも、ニュアンスの捻りで説得力を持たせられるだけの語彙の豊富さがあるというか。“In For A…Proud!”のギターなんて、なかなか冴えてますよ。
テンションの起伏に乏しいジリジリとしたサウンドスケープは、あのSlintの傑作“Spiderland”なんかとも重なる瞬間があったりして。Bandcampを見ると案の定リファレンスにSlintの名前があって思わずニヤリとしてしまいましたが、その他にも Sonic YouthやPavementも挙げられていて、まあ要するにそういうことです。地下室で展開されるギター・オルタナティヴの系譜ですね。そこにエモ的な頼りないメロディが乗っかるんですから、悪くないでしょう?
さっきも書いた通り、これといって新鮮なアルバムではないので、なかなか2026年の新譜として記憶されにくいのかなとは思います。ただ、それはそれとしてギター・オルタナが好きな人ならまず間違いなく反応できる良質な1枚であることも事実ですからね。バイレ・ファンキがなんだと言ってみたところで、結局私は1人のロック・リスナーでもあるわけですから、これからもこういう作品をしっかりメンションしていきたいです。

コメント