
オアシスの全作品ランキングやら邦楽名盤ランキングやら、ちょっと大きい企画を立て続けにやってしまったせいで放置気味でしたがこっちもぼちぼち進行しましょう。新譜月間レコメンド、今回は5月編ですね。バックナンバーは↓からどうぞ。
5月もかなり騒がれるリリースが多かった印象ですけど、もうずいぶん時間が経ってしまいましたからね。こちらで振り返っていただけるとよろしいのではないかと思います。それでは早速、どうぞ。
“HIT ME HARD AND SOFT”/Billie Eilish
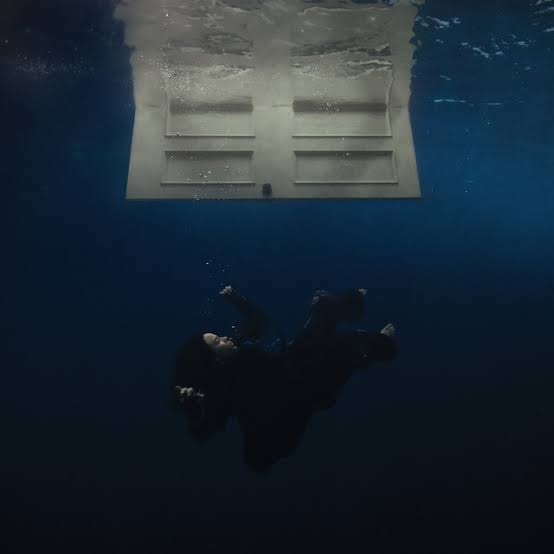
5月のリリース最大の目玉はやはりこの1枚、現行シーンで最も注目を集める才能の1人、Billie Eilishによる“HIT ME HARD AND SOFT”ですね。ちょっとこれは、私にとって衝撃的な1枚でした。
というのも、正直に言って私はこの数年間のBillie Eilishへの大絶賛にイマイチついていけてなかったんですよ。何故こんなダークでフラットな音楽が今ヒットするのかも分からなかったし、色んな評論を読んでもピンと来なかった。これは1stにしろ2ndにしろそうなんですけど、このアルバムでようやく私の中で彼女の才能を掴めたような気がします。より詳細に言えば、彼女の持つポップネスに気づくことができたと言うべきでしょうか。
スピリチュアルな内向性を示した2ndと地続きというよりは、もっと人間的な深淵を感じさせた1stに近いテイストではあると思います。ただ、メロディにより人間味が強まり、サウンド面でも淡々とした密室音楽でありながらフックがハッキリとしている。それは優美な序曲“SKINNY”であったり、あるいはアルバム後半の展開なんかに顕著な部分ですよね。クラシカルでもありコンテンポラリーでもあり未来的でもある、そんなすごく複雑でいて興味を惹かれるサウンドです。
2ndの時点でわずかに感じた、「キャリアのこのタイミングで、こんなにディープな方向に進んで大丈夫か?」という不安。それを上手く彼女のオリジナリティと融合させ、そしてさらに高次の表現できるまとめた本作って今後の彼女の経歴においても大きな意味を持つような気がしてます。デビューからほんの10年足らずで、エキセントリックな天才少女から風格あるアーティストとしての輪郭を獲得してしまった訳ですからね。
“A Dream Is All We Know”/The Lemon Twigs
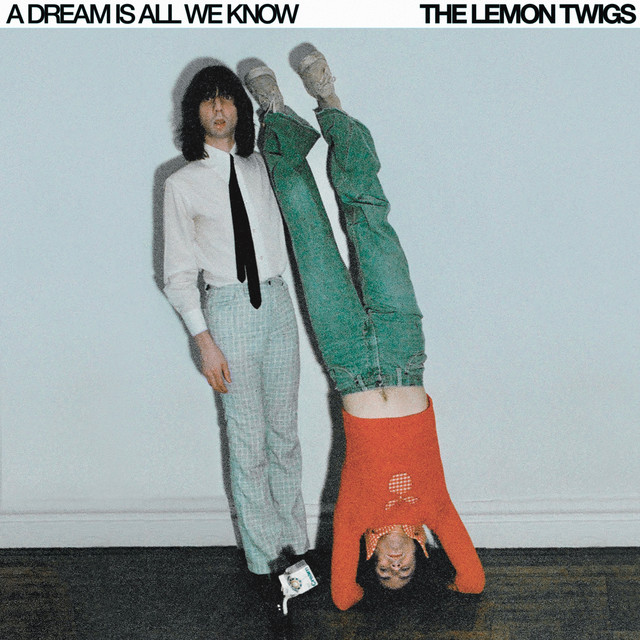
個人的に2024年で最も待ち望んだ作品という感じですね、昨年の”Everything Harmony”は年間ベストでも第2位につけた、Brian/Michael D’Addarioの兄弟からなるデュオ、The Lemon Twigsが早速の新譜“A Dream Is All We Know”をリリースです。
再生するや否や「あれ?間違えてThe Beach Boys流してたかな」と錯覚するレベルで、驚異的に1960年代のロック/ポップスに接近した音楽性。ここまで完全に模倣するのって本当に恐るべきことで、リズム・セクションの平べったさやちょっとわざとらしいハーモニー・ワーク、どれをとってもまるで現代的ではないじゃないですか。でも不思議なことに、どの60’sディスク・ガイドを隈なく見渡してもこの作品は見つからないんです。
今作はさらに一歩踏み込んだ印象もあって、ホーン・セクション、あるいはキーボードやギターといった上物の使い方なんかにいっそうの気配りを感じましたね。“Peppermint Roses”のサウンドにすごく分かりやすいと思うんですけど、レトロはレトロですけど鋭角的と言いますか。この辺、クラシカルな音楽というよりは現代シーンにより関心を持つリスナー層にもリーチできるものじゃないでしょうか。
実際のところ、こういう痛烈なオマージュって面白くはあっても言葉を選ばなければ一発芸になりかねない面もあると思います。ただ、The Lemon Twigsはそうならない。何故なら、彼らが憧れる過去の伝説がそうであったように、彼らもまた本質であるソング・ライティングが天晴れだから。やろうと思えばもうちょっと現代インディーに寄り添った作曲もやれるはずなんですよ、実際1stの頃とかそういう風ですしね。あくまで、彼ら自身で選び取った表現としてのこの温故知新。相変わらず素晴らしいアルバムでした。
“Lives Outgrown”/Beth Gibbons

こちらはビッグ・ネームの作品ですね、トリップホップ・ムーヴメントの代表格、Portisheadのリード・シンガーのBeth Gibbonsによる、実に20年以上ぶりのソロ2nd“Lives Outgrown”。今作を引っさげてフジロックに出演したことも記憶に新しいのではないでしょうか。
さてさて、これはいい意味で裏切られた1枚でした。Portisheadの先入観があるものですから、静謐と冷酷が充満するエレクトロ・サウンドを想定していたんですけどね。蓋を開けるとなんとアコースティックなインディー・フォークときましたよ。ただこれが恐ろしく相性がいい。フォークではあるんですけど、さっき書いた静謐と冷酷、この個性がそっくりそのまま反映されています。
むしろアコースティックなアンサンブルが、かえって不吉な生々しさを演出している部分も大きいですよね。インパクトのある鳴りをしたドラムや、緊張感をもたらすストリングスやブラスに顕著な部分です。Portisheadが凍てついた雪原とするならば、この作品は差し詰め禍々しい原生林といったところでしょうか。原生林の恐ろしさをとくと堪能した、その結びに待つ”Whispering Love”がやけに穏やかなのも個人的にすごく気に入っているポイントで。
そしてGibbonsのディーヴァとしての気品、これもやはり素晴らしいです。トリップホップというスタイルはどうしてもサウンドに意識が向きがちですけど、よく考えればその中でシンガーとして主張できる彼女の表現力はそもそもずば抜けているはずなんですよ。そこのところを長らく気づけていませんでしたが、思わずハッとさせられる1枚でした。
“Fearless Movement”/Kamasi Washington

同じく大御所のリリースが続きます。ThubdercatにKendrick LamarにFlying Lotusに、ジャンルを越えあらゆるブラック・ミュージックで存在を示す現代最高峰のジャズ・マンKamasi Washingtonの“Fearless Movement”。ソロ作品としてはご無沙汰だったようですね。
ジャズってどうしても苦手意識が払拭できない分野ではあるんですが、今さっき書いたようにWashingtonに関してはそういう記号的なジャンルを超越した普遍性がありますから。おっかなびっくり聴いたもののすごくエキサイティングできました。冒頭を飾る9分越えの大曲”Lesanu”での圧巻のグルーヴと民族的な色彩は、この表現が適切かわからないですけどキャッチーですらあって。前のめりな躍動感が、アルバムの世界へと一気にリスナーを引き込むようですよね。
そこからもThundercatにGeorge Clinton総帥、そしてOutkastのAndré 3000、Terrace Martinと縦横無尽の客演を交えて展開されるブラック・ミュージックの密度たるや尋常ではありません。音の空白を楽しむジャズやソウルの方法論ではなく、とにもかくにも肉体的なプレイとブラックネスで畳み掛けるハイ・カロリーな作風です。それでも楽曲単位でしっかり起承転結をつけて完結させる掌握力は、ジャズに特有の才能のような気もしますね。あくまで理性的に明後日の方向に行くからこそ、きっちり元のところに帰ってくる。
そしてKamasi Washingtonの特質であるスピリチュアルな厳かさもしっかり主張されていてね。それはラップをインサートしようとヴォーカルを招こうと、崩れることなくコンセプトとして提示されます。1時間半にも及ぶ長大な作品ではあるんですが、一瞬たりともその官能的な魅力を失うことなく進行するので退屈さとは無縁ですし、グルーヴ主体の音楽を好む人は問答無用で聴くべき1枚じゃないでしょうか。
“破爛酒店”/王若琳

さて、ここまで如何にもな大御所が続きましたが、5月のフェイバリットは実はこの1枚です。台湾の女性アーティスト、王若琳による“破爛酒店”ですね。彼女、2009年のデビュー以来本作を含めて12枚のアルバムを発表しているかなり息の長いアーティストで、アジア圏ではかなり評価されているようなんですが。私は本作で初めてその名を知ることになりました。
そんでもってこれがすげえんだ。ロックあり、ジャズあり、エレクトロニカあり、実にカラフルで万華鏡のような作品でね。楽曲それぞれが強烈な個性を発揮していて、それらをコンパクトにまとめて矢継ぎ早に展開するという構造なんですが、一見破茶滅茶なようでまったく破綻していない。それどころか高度な集中力によって、アルバムとしてのストーリーを完結させることに成功しています。こういう力業の名作、個人的に大好きなんですよね。
思うに、その集中力を成立させるキーワードがノスタルジーなのではないかと。ジャンルそのものはちぐはぐな方向ながら、どの楽曲にも古き良きポップスの作法とでも言うべきものが通底している。肉体的なサウンドの楽曲もそうなんですけど、特に電子音の扱いに明白な部分だと思っていて、80’sに入るか入らないかくらいのプログレッシヴ・ロックのキーボード・プレイ、あるいは往年のゲーム・ミュージック的な装いを感じるんですよ。“MOTHER”のサウンドトラックとかあの辺です。
ノスタルジーでまとめあげられた混沌という意味では、3月編で触れたCindy Leeの“Diamond Jubilee”にも似た表情のアルバムなんですよね。あそこまで野心的ではなく、もっと心地よくポップネスを保全しながらの同系統という感じではありますが。で、あっちも年間ベスト候補だなんて書きましたけど、この”破爛酒店”もかなり高い順位でご紹介することになる気がします。
“Ten Fold”/Yaya Bey

正統派なソウル/R&B作品、2024年の新譜ではまだ紹介していなかったような気がします。Beyoncéの新譜もちょっと例外的なサウンドでしたからね。そんな中、Yaya Beyの“Ten Fold”はこれぞブラック・ミュージックというセクシーな名作でした。前作”Remember Your North Star”もなかなかいい作品だったので、期待値は高かったんですが見事クリアです。
ベースとなるのはやはりネオ・ソウルで、官能的な肉体性とグルーヴを全面に押し出したサウンドです。その方向性は前作でも取られていたんですが、あちらは堅実がゆえの単調さ、ありがちなネオ・ソウルの佳作というポジションに収まってしまった感もあったんですよね。ただ今作では、ネオ・ソウルの構成要素の1つであるヒップホップ的な意匠をジャズ畑のミュージシャンの感性で代替することで、よりアダルティで魅力的なものに発展させています。
この手心によって、グルーヴの有機性においてより強固になるとともに、彼女の歌声がいっそう映える結果になっているのがいいじゃないですか。アーシーでスモーキー、低音域で真価を発揮する渋いヴォーカルはヒップホップよりジャズの方がやはり相性がいい。さきほど触れたアダルティな質感を歌声の面でも増強していますね。そして歌唱と演奏の相互作用というのは、まさしくクラシカルなソウルが度々披露してきた特権のようなものですから。
女性ネオ・ソウルとなるとErykah Baduが真っ先に連想されますが、彼女よりは幾らか骨太、しかしD’Angeloほどにマッチョでもないという絶妙な塩梅。決して派手な作品ではないんですけど、2024年のブラック・ミュージックを振り返る時に多くの人に回想されるような良質な作品であることは保証していいでしょうね。
“Here In The Pitch”/Jessica Pratt

今回フォークからはこの作品を。Jessica Prattの6年ぶりとなるニュー・アルバム“Here In The Pitch”です。10’sから活動していて、キャリア初期にはフリー・フォーク的なアプローチで評価を集めた人物、とのことですね。フリー・フォークというとアレです、初期Animal Collectiveなんかの文脈です。
実際彼女はAnimal Collectiveの創設者であるPanda Bearの“Person Pitch”を、最高の作品とコメントしているみたいでね。であればそういったエクスペリメンタルな方向性なのかと思いきや、ものすごくトラッドなアルバムでした。SSWというカテゴリでも、Scott WalkerであったりNick Drakeであったり、一癖ある職人気質な侘しさを継承しているイメージですね。アコースティックなサウンドスケープは上品にまとめられつつ、全体に厳かな空気が漂っている辺りが如何にもオーセンティックなアルバムといった風格。
面白いのが、本作における着想の1つにあの“Pet Sounds”があるとのことなんです。確かにバロック・ポップとまではいかないまでも、控えめなオーケストレーションによる装飾や、それこそ前述の厳かさというのはその辺りが源流なのかもしれません。思えばAnimal Collectiveの最高傑作“Merriweather Post Pavilion”だって、「21世紀の”Pet Sounds”」とされている訳ですから、そういったファミリー・ツリーが構築できるという考察もできるかもしれないですよね。
ただ、”Pet Sounds”や”Merriweather〜”ほどに難解という訳でもないのがこの作品の良心的なところ。あくまでフォーク・アルバムとしてじっくりと世界観に浸ることのできる余地が即座に感じられる、そういうフレンドリーさも発揮していますから。インディー・フォークというよりはもっとクラシカルな、古典に触れるような心持ちで聴くとより楽しめる1枚な気がします。
“Night Reign”/Arooj Aftab

この作品も言いようによってはフォークと言えるんでしょうか?サウジアラビア生まれのパキスタン人という肩書きの女性SSW、Arooj Aftabの“Night Reign”。ソロ名義の前作にあたる”Vulture Prince”でグラミー最優秀新人賞にもノミネートした、期待のアーティストです。
「夜の君臨」、なんとも好奇心をくすぐるタイトルじゃないですか。そしてそれは見事に作品の性質を言い当ててもいます。作品全体には夜の帳が下りたようなたっぷりとした闇の情緒があり、その中で密やかに蠢くように進行していきますから。それは時としてジャズであり、時としてフォークであり、また時としてソウルでもあって。さらには、そこにはウルドゥー語を交えた歌唱やその東洋的な旋律もあってエスニックな匂いも漂っている。
そしてこのエスニックな成分と真っ向から対立するはずの、都会的なムード。これが見事に作品の中で調和しているんですから鮮やかですよ。「都会の夜」なんていうのはモチーフとしては結構ありがちなものですけど、彼女の個性によってどこかストレンジな、いい意味で歪められた情景として本作に閉じ込められているような印象を覚えます。それはひょっとすると、彼女の出自に由来するある種の疎外感、NYを外側から見つめる視点によるものなのかもしれません。
今年は結構日英米以外からもレコメンドしている意識はあるんですが(とはいえほとんどブラジルですけどね)、そこにこういう作品を加えられるのは嬉しいことです。彼女自身ワールド・ミュージックの立場からの表現を一つのテーマとしているようですが、無事私の心には突き刺さってしまいました。
“#RICHAXXHAITIAN”/Mach-Hommy

続いてはヒップホップを。ハイチ系のラッパー、Mach-Hommyで“#RICHAXXHAITIAN”です。私はヒップホップに決して明るくないので、Xでのレコメンドを見て発見したクチです。で、周辺情報をリサーチしたんですが……この人、その情報のほとんどが謎に包まれた人物のようですね。なんならそのリリックすらオフィシャルには明かされてないものがほとんどで。
それはともかく、作品についてです。ファットな黒さを感じるトラックがまずは耳を引きますね。蠢くようなベース・ラインに、やや後ろノリのドラムが生むグルーヴ。これらが作品に重厚感を与えるとともに、サックスやピアノによるジャズ調の味つけはどれもミステリアスな表情があって、本作の核となる部分をより奥の方へと押し込めるかのよう。それがまた聴いていて好奇心を刺激されるんですけどね。
とまあ、かなりコッテリとしたヒップホップ・アルバムではあるんですが、不思議と聴き疲れしないのが上手いなと。それは作品全体のトーンが今さっき書いたような謎めいたムードによって統一されている点や、トラックの主張が激しすぎず存外すっきりまとめられている点、そして彼の作品にしては例外的らしいんですが客演をかなり積極的に招くことでラップの上で個性をつけている点なんかが根拠になっていると思います。客演ということなら、個人的にはあのBlack Thoughtをフィーチャーした“COPY COLD”がベストかな。
あくまで聴き味の上でということならば、あの“To Pimp A Butterfly”を連想する瞬間すらある作品です。それってあの作品でヒップホップの抵抗感を払拭できた私にとって、ものすごく嬉しい類似なんですよね。少なくとも今のところ、ヒップホップに関してはトップ・クラスに気に入っている1枚です。
“人工島”/電球

最後に3月編のdawntに続いて、日本のインディー・シーンからご紹介しましょう。シューゲイズ・バンド、電球の1st“人工島”です。
シューゲイズとは書きましたけど、サウンドとしてはノイズ・ミュージックの要素も大いにありますね。どちらも騒音(と一般的には解釈されるであろう音)によって作品を塗り潰すという手法は共通してるんですが、シューゲイズはそもそもがバンド・ミュージックであり、ノイズはどちらかというと電子音楽じゃないですか。いわば、有機性の有無という点で隔たりがあるスタイルだと私は認識しています。
そこの橋渡しがお見事なんですよね。前提としてロック・バンドの音ではあるんですけど、ギター由来ではないもっとインダストリアルなノイズも至るところで鳴っていて、ときにはサンプリングによる無機性の演出もあって。それに、シューゲイズの典型であるところの「騒音の中で儚げに紡がれるメロディの甘さ」というのは本作ではかなり控えめ。ヴォーカルはあるんですけど、いかんせん周りがやかましすぎてほぼ埋没してますからね。
これはもう是非とも耳を痛めない限界のレベルまでボリュームを上げて聴いていただきたいです。物理的にも精神的にも結構ストレスフルな作品鑑賞にはなると思うんですけど、それゆえに聴き終えた後のカタルシスが並大抵ではありません。ノイズの快感は永遠に続いてほしいと思う一方、聴き終えて無音になった時の夢から醒めたような感覚も素晴らしく心地よいですから。
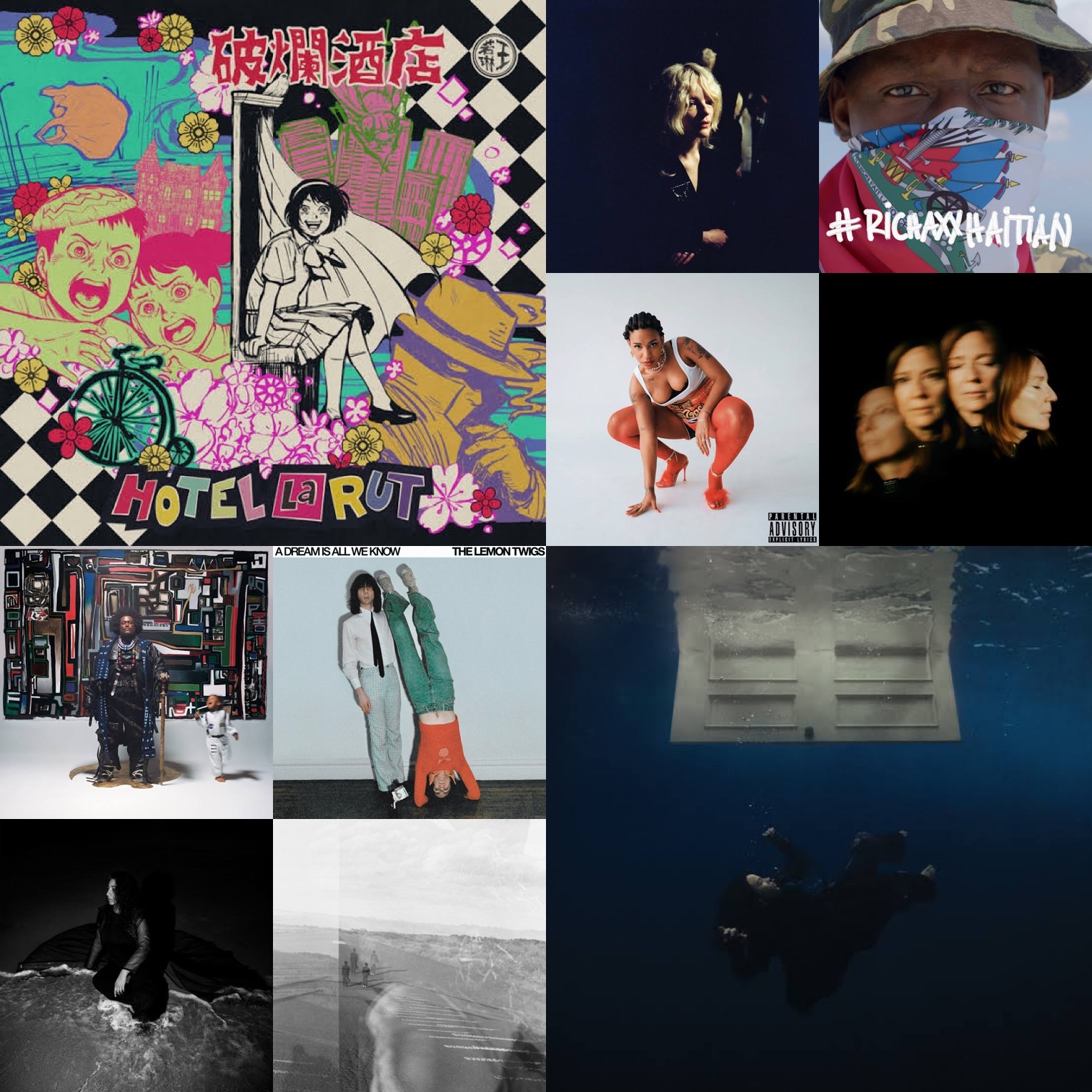


コメント