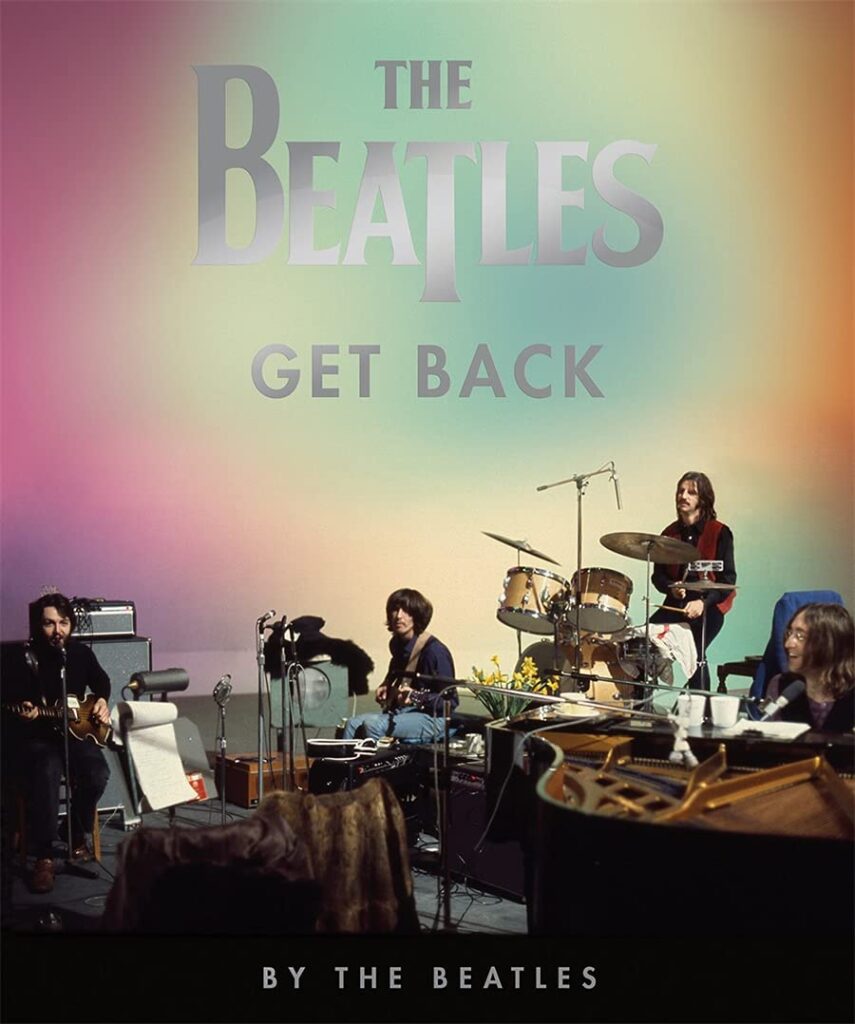
遅ればせながら、ようやく『ザ・ビートルズ: Get Back』を視聴できました。
いやあ、よかった!シンプルにドキュメンタリーとして秀逸ですし、何しろその対象がザ・ビートルズですからね。
当初は劇場公開予定でしたが、今にして思うと映像配信でよかったですね。この膨大なマテリアルを2時間やそこらにまとめられてしまうのは少し味気ないですから。おかげで見るのは相当骨が折れましたけど。もうちょっとしたタイムスリップですよ。
で、見ていて思ったのが、この映像作品って「群像劇」だなと。ザ・ビートルズという極めて民主主義的なアーティスト(作品内でポールも「全員賛成じゃないと話が進まないのがおかしい」とくだを巻いています)に、極めて親密かつフラットに寄り添っているんですよ。
ここでは、メンバー4人にフォーカスしつつ、印象に残ったシーンや感想をつらつらと書いてみましょうか。
①ポール・マッカートニー/残酷なまでの才能
「ゲット・バック・セッション」の、特に初期における中心人物は間違いなくポールなんですね。そのパワーバランスは後期ザ・ビートルズにおける彼の作曲を見れば明らかではあるんですけど。
ただ、その才能というのをいざ映像として克明に見せつけられると、もう残酷で。
すごく印象的なのが、このプロジェクトのテーマにも掲げられた『ゲット・バック』の作曲シーンですね。リンゴとジョージが見守る中、ヘフナーをかき鳴らして作曲していきます。最初はとりとめもない鼻歌なんですけど、それが見る見るうちに我々も知るところの『ゲット・バック』になっていくんです。
畏怖、というものをあそこまではっきり感じたのは人生でも初めてですよ。すごいとか感動を通り越してちょっと怖い。こんなのと才能を比較されるジョージが如何に苦しいか、想像に難くないです。
このセッションでポールが持ってきた楽曲をちょっと振り返りましょうか。アルバム『レット・イット・ビー』収録の楽曲は当然として、『マックスウェルズ・シルヴァー・ハンマー』や『オー!ダーリン』、『ゴールデン・スランバー』といった『アビー・ロード』に収録されることとなる楽曲、それから『バック・シート』に『アナザー・デイ』のような解散後ソロで発表する楽曲まで。
どこまで温めていたアイデアでどこまでセッション中の作曲なのかはわからないですけど、質と量がもうとんでもない。
で、この才能を振り撒きながら、彼はバンド存続のため強引にイニシアチブを取りにいくんです。特にジョージにはかなり厳しい物言いをして、バンドの空気をかなり悪化させています。
ただ、それも悪気がないのが余計に残酷なんですよ。ポールはザ・ビートルズを存続させたいが一心で名曲を書き殴り、ジョージの演奏に文句をつける。パート1で顕著な構造ですけど、見ていて本当に辛い瞬間でした。
②ジョン・レノン/最後までザ・ビートルズのリーダーだった男
続いてジョン・レノンですね。この時期のレノンって心身共にかなりボロボロなんですよ。ヘロインにも手を出して、セッション前半はちょっと廃人に近い空気すらあります。
そこで救いとなったのがオノ・ヨーコなんですね。スタジオでも正に一心同体、常にジョンの隣にいます。それゆえオノ・ヨーコは「ザ・ビートルズを解散に追いやった魔女」のような扱いを受けることになるんですけど、これはまったくの誤解です。少なくとも彼女の側から何かした訳ではないですからね。
話を戻しましょうか。さっきも言った通りセッション前半でのジョンはろくに曲も書いてこないし(と言いつつも『ドント・レット・ミー・ダウン』なんて傑作を書いてはいるんですけど)、モチベーションもほとんどない。遅刻もしょっちゅうでね。
ただ、スタジオをトゥイッケナムからアップルに移して以降、特にビリー・プレストンがセッションに参加してからは一気に覇気を取り戻します。ここからのジョン、まさしく「ザ・ビートルズのリーダー」ですよ。
ジョンがウェットに富んだジョークを飛ばし、バンドの空気を引っ張る。そこにポールが乗っかって、ジョージとリンゴがついていく……きっと初期の彼らもこんな感じだったんでしょうね。
スタジオの空気も朗らかになっていって、創作も目に見えて活気付きます。こういう状況をジョンは「プレストンのおかげだ」なんて言ってましたけど、それ以上にジョンの復活が大きかったんじゃないかな。どこまでいっても彼はバンドの支柱でしたから。
③ジョージ・ハリスン/苦悩する第3の天才
さっきこの作品を「群像劇」って表現しましたが、個人的に一番感情移入しちゃったのがジョージですね。
この時期、多分ジョン以上にザ・ビートルズへの関心がなかったのがジョージだと思うんです。この時期のジョージも相当脂乗ってるんですけど、流石にポール・マッカートニーには敵わない。最年少ということもあってどうにもバンド内で軽んじられる。そういう状況へのフラストレーションはあったでしょうから。
この作品のハイライトは間違いなく「ルーフトップ・コンサート」なんですけど、ドラマとしてのピークはジョージの脱退騒動なんですよね。セッション中にいきなり「もう辞める」と。
すごく緊張感が走るシーンです。ポールは涙を流すほど狼狽しているし、リンゴも多くを語らないものの辛そうですし。ただ、ジョージの気持ちを考えればあまりに妥当なんですよ。
だって『サムシング』や『オール・シングス・マスト・パス』のような楽曲は構想としてあるんですよ?でもスタジオではまともに取り合ってもらえない。セッションではポールに逐一文句をつけられる。そりゃやる気も失せるでしょ。
メンバー総出で説得に出て、なんとか元の鞘に収まるんですけど、それ以降もはっきり言ってジョージの楽曲への扱いはかなり雑です。ソロ活動をジョンに提案しても一蹴されてね。『オールド・ブラウン・シュー』に『アイ・ミー・マイン』に、いい曲できてるんですけどねぇ……
こういうジョージの苦悩って、それこそザ・ビートルズ解散の要因として語り草ではあるんですけど、ドキュメンタリーとして見てしまうとすごく生々しいというか、真に迫るものがあります。
④リンゴ・スター/「ルーフトップ・コンサート」の立役者
最後にリンゴ。ただ彼、この映像の中であまり多くを語らないんですよ。如何にも彼らしい、一歩引いた立ち位置からバンドの行く末を見守っています。
この時期のリンゴは音楽より映画制作に熱意があった、なんて話もたまに見ますけど、少なくともこのセッションにはポールの次に前向きでしたよ。
悪く言っちゃえば存在感の薄いリンゴですけど、ものすごく印象的なシーンがあって。伝説となった「ルーフトップ・コンサート」の開催の是非でバンドが揉めている時の一幕ですね。
ジョンとポールの意見がぶつかって、ジョンはとりあえず今やれるもんでやろうと言うものの、ポールは曲をきっちり作ってから、今は時期尚早と反論。周りの大人達もそれぞれの都合がある訳で、議論はかなり難航します。ジョージはだんまりでね。
そこにいきなりリンゴがこう言うんですよ、「やりたい」と。
この映像作品で最も感動的なシーン、ここじゃないでしょうか。この一言をきっかけに、ジョンが「俺も」と乗っかり、ポールも「ならやろう」と。ジョージも仕方ないなという感じで開催に同意します。
リンゴって柔和でユーモアがあって、バンド存続に貢献した人格者という認識が一般的ですし、事実作品内でもそういう性格は随所に見て取れるんですけど、このシーンで彼もまたビートルであることが浮き彫りになるというか。他のメンバーも全員リンゴについてきたのがまた泣けます。
伝説の「ルーフトップ・コンサート」
で、ですよ。こういう群像劇、人間ドラマとしてもこの映像作品は秀逸なんですけど、やっぱりハイライトのここを語らずにはいられません。1969年1月30日、アップル社ビルの屋上で開催されたザ・ビートルズ最後のライヴ・パフォーマンス、通称「ルーフトップ・コンサート」です。
ザ・ビートルズのレガシーの中でも非常に巨大なトピックですし、伝説として今でも語り継がれるこのライヴなんですけど、やっぱりとんでもなくカッコいい!
「ゲット・バック・セッション」って、結構おふざけ半分な演奏も多かったんですよ。真面目にやってるテイクもあるんですけど、バンドの持ち曲を如何にもおチャラけてやってみたり、オールディーズのカバーしたりね。
ただどうです、1曲目の『ゲット・バック』が始まった瞬間のあのキレキレのロックンロール。陳腐な表現を敢えて使いますけど、世界最高のロック・バンドってこういうことですよ。
このライヴ自体は今回が初出でもないので、見たことあるものがほとんどなんですが、6時間以上にわたる人間ドラマの末に見る「ルーフトップ・コンサート」は流石に感慨深いものがありましたね。
大好きなシーンは沢山あるんですけど、1つだけ選ぶなら警官の突入以降でしょうか。屋上に警察が入ってきたのを見た瞬間、ポールが絶叫するんですよ。ものすっごく嬉しそうに。この悪ガキ感、堪らなくカッコいいです。
でもって「ルーフトップ・コンサート」のフィナーレ、3度目となる『ゲット・バック』の演奏ですよね。業を煮やした警官がアンプの電源を落とすことを命じて、ギターの音が止まってしまいます。
ここから全員に見所があるのが奇跡的なんですよね。まずはリンゴ、音が鳴らなくなり戸惑うフロントの3人を尻目に、あの3連のスネア・ビートを刻み続けます。それも仏頂面で。「無視だ無視」と言わんばかりのふてぶてしさ、いやぁロックだ。
お次はジョージのターンです。アンプの電源を切られたことに気づくと、警官が見ている目の前で勝手にアンプの電源を入れ直し、やはり無視して演奏を再開。パンクですらありますよね。
続きましてはポールです。そもそも警官に向かって『ゲット・バック』なんて当て擦りもいいとこなんですけど、
You’ve been playing on the roofs again,
and you know your Momma doesn’t like it,
she’s gonna have you arrested!
また屋上でやってんのか?
ママはいい気がしないだろうぜ
逮捕されちまうぞ!
『ゲット・バック』(「ルーフトップ・コンサート」テイク3)より引用(抄訳;ピエール)
とアドリブで歌ってみせます。ロック・スター感がハンパじゃないんですよねココ。
そのまま演奏終了、締めくくりはジョンの「これでオーディションに合格していれば幸いです」という最高のジョークです。これ、バンドがデビュー前にオーディションに落ち続けたことへの皮肉なんですよ。こういうエスプリの効いたユーモア、ジョン・レノンのカリスマ性の重要な根拠ですよね。
まとめ
今回は『ザ・ビートルズ: ゲット・バック』のレビューでした。
そもそも、ザ・ビートルズにここまで接近した映像というのがおそらく史上初なんですよね。『アンソロジー』シリーズはあくまで資料集ですし。
ザ・ビートルズが人類文化史上に残る偉人であることを思えば、この作品は単にビートルマニア垂涎の秘蔵映像以上の価値があるもののような気がしています。
人間ドラマとしても、音楽ドキュメンタリーとしても、文化資料としても、これ以上なく優れた作品です。改めて、ピーター・ジャクソン監督を筆頭とした本作に携わった全ての方に感謝と敬意を示したいと思います。
……で、この映像作品を見たからにはビートルズ熱が再燃する訳です。私の音楽体験上、ビートルズ熱が鎮火した試しはないんですけどね。次回もこのテーマに沿った記事を予定しています。それではまた次回お会いしましょう。
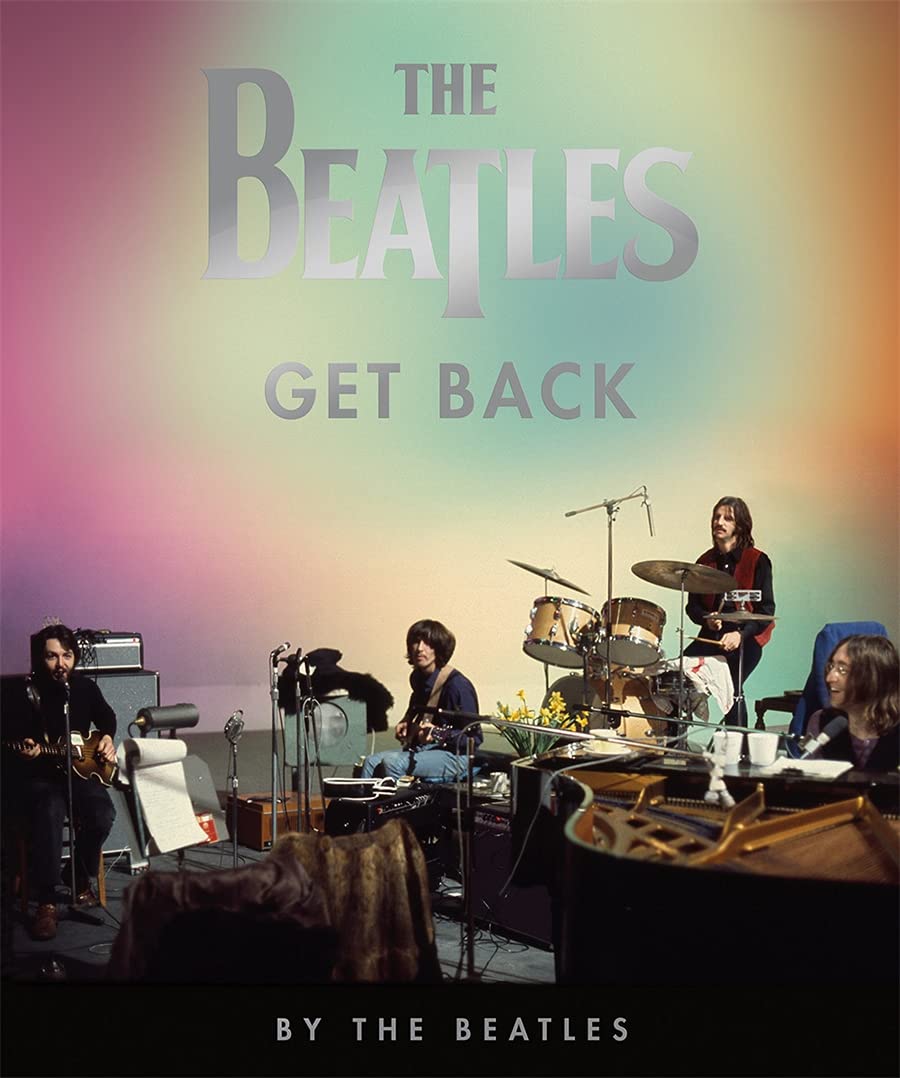



コメント
[…] 前回に引き続き、「ゲット・バック・セッション」に関してです。 […]