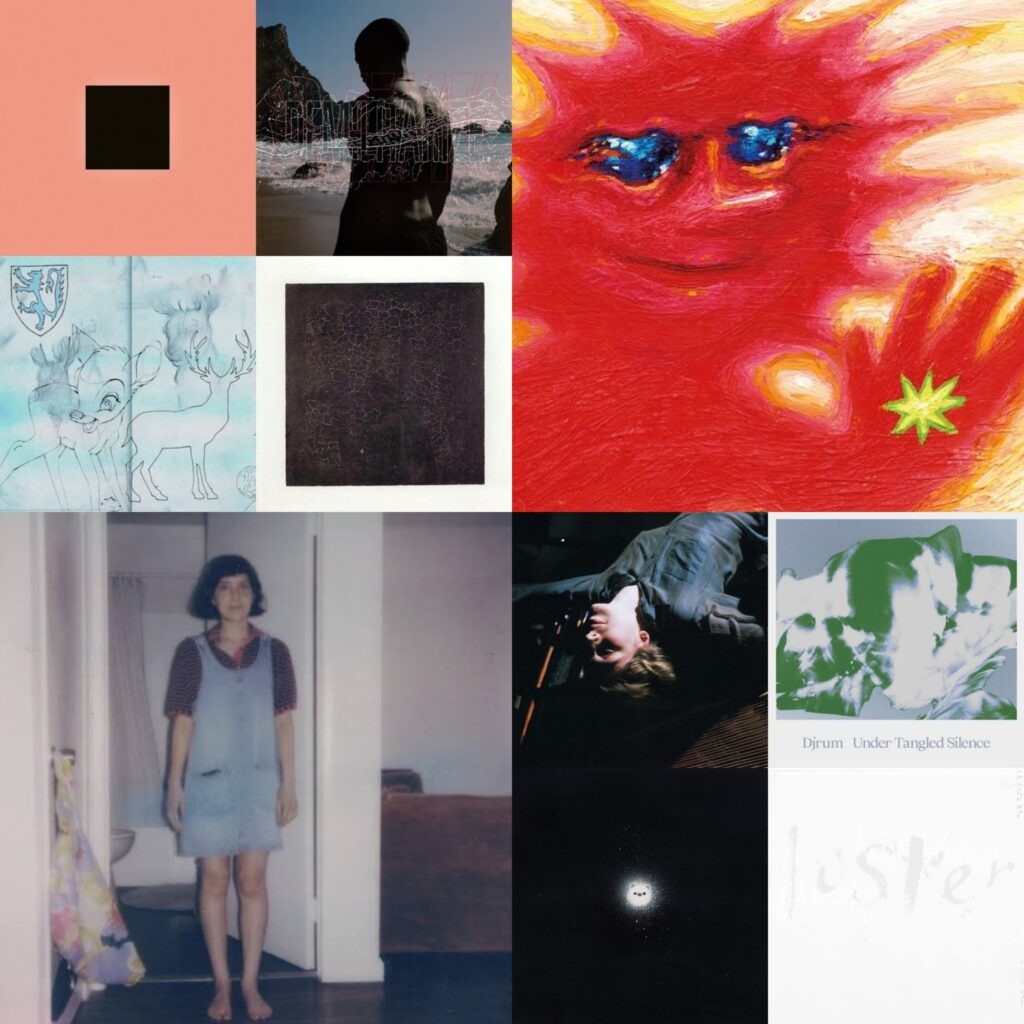
じわじわと昨年までの遅刻癖を取り戻しつつある今日この頃。なんとか2週間のディレイで止めましょう。今回は月例の「オススメ新譜10選」、4月編です。バックナンバーは↓からどうぞ。
いやぁ、4月は凄まじい1ヶ月でしたね。とにかくいい作品が多かった。環境の変化もあってなかなか時間が取れず、遠巻きに眺めていた節はあったんですが、それでも毎週何かしらのお祭り騒ぎになっていた印象です。
遅ればせながら、このピエールもそのお祭り騒ぎに便乗するとしましょう。例によってベタな作品も多いんですが、きちんと己の耳で選んだ4月のレコメンド10選。いざ参ります。
“Forever Howlong”/Black Country, New Road

……流石にこれを真っ先に語らないのは不誠実かな。4月の数ある名作の中で、これはちょっと格別でした。“For The First Time”でサウス・ロンドン・シーンの充実を物語り、続く“Ants From Up There”で20’sのArcade Fireにまで上り詰めたBlack Country, New Road。そんな彼ら彼女らの待望、あらゆる意味で待望の新作“Forever Howlong”です。
というのも、賢明なる皆様ならばご存知かと思いますが、大傑作2ndのリリースと時を同じくしてリード・ヴォーカルのIsaac Woodが脱退してしまったんですよ。致命傷になりかねないこの出来事を受けて、バンドはステージで2ndの楽曲を封印。全く新しいBC, NRの再建を決意します。その道程は“Live At Bush Hall”で聴くこともできますが、私としてはやはりスタジオ・ワークでその姿を確かめたかったんです。そうして期待と不安の入り混じる中この”Forever Howlong”に触れてみたらば。途方もない名作じゃないですか!
ヴォーカル・パートの空席をガールズ・メンバー3人で代わる代わる補うという試み。これがバンドの若々しい狂気を柔らかな気品へとブラッシュ・アップしています。オーガニックな温もりは2ndでも感じられましたが、流石にここまで嫋やかではありませんでしたからね。しかしそこには“For The Cold Country”なんかに聴こえてくる神経質さや貪欲さもはっきりと残っていて、同時にイギリス流のポップ・センスまで乗っかってくる。これが悪いはずがないんです。
そう、イギリス流のポップ・センス、これがすごく私にとっては大事でした。“Hunky Dory”や“The Yes Album”、もう少し時代を遡れば(これ以上?)”Oddesay And Oracle”のある種の楽曲で聴ける、やや浮世離れしていていけ好かない、そしてだからこそ愛おしいそれですから。さっき”Ants From Up There”でのBC, NRをArcade Fireに準えましたが、ここにきてUK文化系ロックという正統な位置に収まっていった感覚です。危うい発言かもしれませんが、人間が必ず何かしらの国家や文化に帰属する以上、その特質は活かせるに越したことはありません。
ただ、歴史に名を残すのは2ndなんだろうし、ややこしい(がゆえに気高い)ロック・ファンは1stを支持するだろうし。ちょっとまだ批評的な立ち位置の見えてこない1枚ではありますよね。それはBC, NRの今後のキャリアにも言えちゃうことですが……それでも、ここで胸を張って言っておきます。私にとっての目下キャリア・ベストはこれっきゃありません。よくぞ、よくぞこんな傑作を作り仰せたものです……文句なく、4月の個人的ベストですね。
“SABLE, fABLE”/Bon Iver

マンスリー・レコメンドの1作目に挙げる作品には個人的に大きな意味があるんですが、これは4月でさえなければその栄光に足る1枚でした。今やUSインディー・フォークの1つのルーツと言っていいでしょう、Bon IverことJustin Vernonの6年ぶりとなる帰還“SABLE, fABLE”です。この新譜レコメンドを始めてから何度も何度もUSインディー・フォークについて触れてきましたが、いよいよ真打の登場ですよ。
2部作という構成を取る本作、まずは昨年リリースされていたEPを原型にした“SABLE”から始まります。一貫して侘しく、孤独に貫かれたインディー・フォークといった趣で、キャリア初期の“For Emma, Forever Ago”を彷彿とさせる質感ですね。しかし事態は“AWARDS SEASON”の結びから“fABLE”サイドへ移ると一変し、ゴスペルやソウル、ソフト・ロックにエレクトロニカと極めてカラフルかつハートウォーミングなサウンドへと転換します。それは例えて言うならば、厳しい冬を抜け、麗らかな春の訪れを寿ぐかのよう。
既に発表していた”SABLE”から繋げることで、このコントラストを映えさせるのはニクい仕掛けですね。そしてこうした穏やかな傾向というのもBon Iverがかつてから持ち合わせていたものではあるんですが、そこに参加したアーティストがまた鋭い。Dijonやmk.geeといった面々ですよ。特にmk.geeなんて去年の1stが大絶賛され、台風の目になるかと期待されていた俊英。そんな彼を早速フック・アップする抜け目のなさもそうですし、彼のキャラクターを引き出しつつも見事にBon Iverの世界観の中でコントロールしている手腕が何より鮮やか。
まさかたった1年で、mk.geeからダイレクトにBon Iverに繋がる文脈が発生するとは思っていませんでした。その辺りも踏まえて、最早フォークがどうこうという狭い領域で語るべき作品ではなく、今日のインディー・シーンの魅力を余すことなく表現した包括的な名盤と評価すべきかなと。間違いなく2025年を代表する1枚になるでしょうし、Bon Iverのキャリアにとっても重大な作品として語られることになるでしょう。
“Demilitarize”/Nazar

ちょっとアンダーグラウンドなところをいくと、こちらも話題作でした。アンゴラのアーティストNazarによる“Demilitarize”。私は初めて知るアーティストだったんですが、なんでも新型コロナに罹患し生死の間を彷徨った経験に基づいた作品とのことで、触れ込みからして相当にダークな作品であることは想像に難くありません。
音楽性としては……ダーク・アンビエントになるのかな?やはり暗い作品ではありますよ。アブストラクトな電子音がコラージュ的に配置され、肉体性らしい肉体性はハミングのような生気のない歌唱がうっすらと聴こえてくる程度。かなりミステリアスで、リスナーに努力を要求するタイプの作品なんですが、モチーフには日本が誇る傑作『攻殻機動隊』があるらしく。なるほど、かの作品のスリリングな閉塞感と底知れぬSFの世界観は確かにリンクするものがありそうです。
そして、先ほどのダーク・アンビエントというラベリングにやや自信がなかったのは、本作のリズムに原因があります。こちらも難解に蠢きつつ、しかしある種の躍動感、本作のムードに照らせば暗い独房の中でもがいているようなネガティヴなそれではあるんですが、が感じられます。これはアンゴラのダンス音楽であるクドゥーロというものを下敷きにしているようですね。じゃあ本作で踊れるのかと訊かれると断じてノーではありますが、オルタナティヴR&B的でコンテンポラリーな質感に寄与している側面ではあるのかな。
レビューなんかではCocteau TwinsやFrank Oceanなんて名前が挙がっていましたが、個人的に連想したのは何故だか“Kid A”。極端に残忍で、極端に閉ざされていて、極端に身体性を剥ぎ取り、その結果としてビートだけがくっきりとした孤独な音楽作品として成立している点において近しいものを感じました。私が”Kid A”シンパなことは定期的に主張していますが、であれば当然本作もフェイバリットになる訳です。
“Luster”/Maria Somerville

こちらは名門レーベル4ADより、アイルランドのアーティストMaria Somervilleの2nd“Luster”。2019年リリースの1st”All My People”で既に注目を集めていたアーティストのようです。なので待望の2ndということになるのかな。ただ2019年というと、私がまだ「レディヘ?ああ若手バンドね興味ない」くらいの舐めた態度を取っていた時期なので、残念ながら今回が初めましてにはなります。どの口が”Kid A”シンパとかほざいているのか、というご指摘は受け付けませんよ。
さて、4ADというと皆さんそれぞれに思い入れはあることかと思いますが、本作は広く言われているようにリリースと同時に4ADクラシックとなる風格を携えた1枚ですね。なにしろレーベル黎明期の重要アーティスト、Cocteau TwinsのDNAをこんなにもはっきりと継承しているんですから。雲海のように広がるシンセサイザーは荘厳なまでにドリーミーで、アンビエント的と言っていい次元で作品を包み込んでいます。ドラムのビートがガイドになっていたり、ギターがさりげなく登場したり、アンサンブルと呼べるものも用意はされているんですが、そんなのお構いなしです。
そしてヴォーカル、ここもまたCocteau Twins的です。天使の歌声とまで謳われた Elizabeth Fraserにも肉薄する清浄でどこか物憂げな歌唱は、しかしサウンドスケープに比較すればリアリティの成分を生んでいて。ここにリスナーが没入する余白を感じます。ヴィジョンとして連想されるのは深い霧が立ち込めた湖。果てしない広大さと美への畏怖を抱きつつ、まるで彼女の歌声は小舟のように、我々にドリーム・ポップの極致へ漕ぎ出でることを許してくれるんですね。ここまで夢幻的な作品なのに聴きやすいというのは、ここのところが大きいと思っています。
さっきのNazarでもCocteau Twinsの名前が挙がりましたが、彼女たちも近年頻繁にメンションされる存在です。でもそれってシューゲイズのエリアからのことも多くて、個人的にそれは導線として如何なものかと思っていました。近いところにはいますけど、サウンドの質感は別ですからね。でも本作は文句なくCocteau Twinsに繋がる1枚だし、ドリーム・ポップの魅力をきっちり描写したお手本のような作品だと思います。お手本にしてはよくできすぎなんですけどね。
“Lorings”/Salami Rose Joe Louis

ドリーム・ポップ繋がりで4月はもう1枚。調べているとドリーム・ポップという触れ込みをしばしば目にしましたからね。女性アーティスト/プロデューサーSalami Rose Joe Louisで“Lorings”。ただ、こっちはMaria Somervilleがやったような神秘性1本釣りという作風ではなく、もっと多角的なアプローチが聴こえてくる作品です。レーベルはあのFlying Lotus率いるBrainfeederということで、察しのいい方はこの時点で彼女の野心に気づくのではないかと思います。
まあ、私はそこまで鋭くないので。この作品を手に取った理由は極めてミーハーです。ジャケットがいい!今のところ2025年ベスト・アートワークですよ。で、実際聴いたらまたこれがいいんだな。ごく控えめながらきめ細やかなR&Bやジャズのグルーヴ感、エレクトロの侘しくも研ぎ澄まされた響き、どれを取っても磨き上げられた天晴れなサウンド・プロダクション。加えて、そこに必要以上の気負いを感じない点も素敵です。ジャケットに意識を引っ張られすぎなのかもしれませんけど、本当にあの部屋の中で鳴っていそうな、不思議な実存の響きがあります。
思うに、ヴォーカルに感じられるつんとした表現、これが効いてるのかなと。その凛とした佇まいはドリーム・ポップのそれにも近しいんですが、それよりはフレンチ・ポップ的と言った方が正確な気がしています。サウンドの構築とは別の角度で作品に参加してくるので、まさに部屋/住人の関係値に近い、不可分にして本質的に独立した構造が生まれていると分析しました。最近Serge Gainsbourgに凝っていまして、おフランスの高貴さに敏感になっていたところだったのも個人的に追い風でしたね。
冴えたサウンド・メイク、その中に感じられる人間的な輪郭の強さ、そして繰り返しになりますがジャケットのムード。あの“BADモード”を連想したのは私だけでしょうか?音楽性そのものは離れていますけど、閉じ込められている匂いや意思はかなり類似しているような気がするんですよね。注目作だらけの4月でしたが、案外年の瀬に持て囃されているのはこの1枚だったりするかもしれません。少なくとも私はそうする予定ですよ。
“Terra Infirma”/deer park

続いてもエレクトロの分野から。やはり2025年、かなり電子音楽が充実していますね。ロック小僧の私にここまでレコメンドさせるんですから。NYの……バンドなのかな?調べても奈良公園ばっかりヒットするので詳しいところは分からずじまいなんですが、ともあれdeer parkの“Terra Infirma”。シングルやEPでのリリースが多いようで、アルバムとしてはこれが2作目のようです。
ただ、エレクトロではありつつも極めてロック的な気配のする1枚ではあるんですよね。なにしろ、ギターがカッコいい。アルバム前半なんて、エレクトロというよりギター・オルタナティヴとして語るべきサウンドですからね。ポストパンク的な血の気の引いたトーンで、淡々と進行する不吉さがいいじゃないですか。ただ、そこと並行してシンセサイザーは後方から包み込むように鳴ってはいて、それがどんどんと膨張して作品を飲み込んでいく、そんな構造を取っています。
そのスイッチのタイミングがはっきりと聴き取れるのが“Overshot”という曲かな。ギターも鳴ってはいるけれど、サウンドの勢力関係でいけば電子音が逆転してメーンになっていますよね。そして“Counting Hands”なんて曲に至れば、坂本龍一を思い出させるピアノ・エレクトロにまで振り切っていって、ラストの“Parasite In My Passenger Seat”なんて純度100%のエレクトロ・ダンスでしょう?この推移を違和感なく一筆書きしてしまえる表現力、結構とんでもないことです。
まるでアハ体験のように知らず知らずに変化するものだから、ここのところに気づくのに時間がかかりましたけどね。そしてその手腕を全くひけらかさない、というよりは自覚がないのか、さりげなさがズルいなぁと思わされます。ロック・リスナーの意識、そしてエレクトロ新参者の好奇心、私の中にあるこの両方の感性を刺激してくれる見事な作品だったと思います。
“Under Tangled Silence”/Djrum

ということで、エレクトロ新参者のピエールは無邪気にもう1枚エレクトロからレコメンドしますよ。なんと扱ったアルバムの半数を電子音楽が占めるという異常事態です。それだけ、私のような門外漢にまで刺しにくる作品が多かったということです。しかも、ここにきてUKハウス。Djrumで“Under Tangled Silence”です。大丈夫かな、私UKのエレクトロFloating Pointsしか知らないんですけど。
……全然大丈夫でした。むしろ大好物でしたね。まだエレクトロから得た感動を具に言語化できるだけの視野は私にはないんですけど、音の粒の1つ1つに洗練と意味を染み込ませた、理性の張り詰めた1枚ということは伝わってきます。前半でいえば、まったくのピアノ・ソナタ的な“Unweaving”からシームレスに移行する“L’Ancienne”で、徐々に害意に満ちた電子音がピアノの機嫌を損なわせ、気がつけばトライバルな享楽にまで至ってみせる。かと思えばその静謐な気品は“Galaxy In Silence”にも継承されていて……すげえなぁ。
ここまで知性が躍動する作品、ちょっと類例が引いてこれませんね。このアルバムを聴いていて、踊ろうなんて気にはちっともなりません。むしろその逆、じっと身を潜めて、片時も見失うことなく動向を追いかけるのに必死です。でも当のサウンドは気まぐれに、しかしやはり知的に漫遊していやがる。これ、どういう背景があるんでしょう。それこそさっき引き合いに出した Floating Points”の“Cascade”なんかは暴力的にダンサブルでしたが、あちらと違ってもっと屋内の音楽ではありますし。クラシック音楽の素養があることはなんとなく聴こえてはきますが……
でもさっき書いたように、トライバルな荒々しさも確かに本作のエッセンスではあって。冷静な西洋的音楽と残虐な民族性を、知性でひと繋ぎにする……ああ、道理で私が好きな訳です。このアルバム、ハウスの手法を用いた“Larks’ Tongues In Aspic”なんですね。こんな時にまでプログレッシヴ・ロックの話をしたがるなんて気持ち悪いという意見には同意しますが、私が捉えた周波数はかなり近いところにあるのは事実ですから。ということで、プログレ・リスナーのあなたも無視できない1枚ですよ。ぜひとも。
“E”/Eliana Glass

うん、とはいえそろそろ情念の籠った生音が恋しくなってきた頃じゃないですか?奇遇ですね、私もですよ。そんなあなたと私にお誂え向きの1枚がこちら、オーストラリア出身で現在はニュー・ヨークで活動している女性シンガー/ピアニスト、Eliana Glassの1st“E”です。少なくとも2025年に入ってから、ここまでジャズ的なアルバムを紹介するのは初でしょうか。
恨めしそうなウッド・ベースのもったいぶった響き、どれだけ健やかな心持ちであろうとたちまち鬱々とさせてしまう不吉に澄み切った歌声、宵闇を歩くための細い蝋燭のように揺らめくピアノ……堪らないですね、何から何まで楽しくない。一貫して厭らしく、それゆえに隙のない1枚です。“Good Friends Call Me E”での大胆さに富んだドラムの知的な勇ましさをも、彼女が差し向ける絶望の前では虚無的に聴こえてきます。作品を夜の世界に閉じ込めてしまう恐るべき魔力、一朝一夕ではなし得ない見事な代物ですよ。
比較的直近でこのテイストには覚えがあるなと思えば、Arooj Aftabによく似ているんですね。彼女もまた、アメリカの外からやってきた出自を持ち、NYに住まい、濃密な闇を主題としたジャズ的作品を残しています。昨年2024年の名盤、“The Night Reign”です。ただ、あちらには実験性やエスニックな濃度という仕掛けがあったのに対し、Glassはさらにジャズに集中してみせ、凍てつくような美で作品を武装している。そしてこのオーセンティックっぷりが、さらに作品の触れ難さに拍車をかけるという容赦のなさがあります。
とまあ、ここまでくればお分かりでしょう。聴き手を選ぶ作品だと思います。それに聴くシチュエーションも。陽が高いうちに聴いてもちっとも響かないと思うんですよね。その分、日の出に怯えながら微睡む深夜との相性は格別。大した意味もなくセンチになっていたりすればなおのことよいでしょう。でもそんな時間って、実は結構普遍的なものだったりするじゃないですか。そんな孤独な夜のサウンドトラックとして、申し分ない作品が現れました。まだ聴かれてないという方は、いっそここぞという憂鬱まで寝かせてみてもいいかもしれせんよ。
“石の糸”/kanekoayano

国内からは流石にまずこの1枚でしょうかね。日本全国100万人のサブカル・ボーイとサブカル・ガールから絶大な支持を集めるSSW、カネコアヤノの初となるバンド名義作品、kanekoayanoで“石の糸”。リリース数時間前にゲリラ的にアナウンスされ、インターネットが随分と慌ただしくなったのを覚えています。いや、みんなカネコアヤノ好きすぎるでしょう……
と、こんなリアクションする程度には、実を言いますとカネコアヤノに対してはやや距離感があったのは事実でして。そりゃあいいアーティストだけども、ここまでの注目と支持に繋がるものは見つけられていなかったんですよね。ただ、そんな私をすらねじ伏せる素晴らしい1枚でした。ざらつきながらもドロドロに溶けたサイケ・テイストに、クラウトロック的な几帳面な変態性、やってることは『空洞です』以降の坂本慎太郎とかなり近しいのかなと思います。この辺りにはバンド名義でリリースした意義も感じられますね。
坂本慎太郎もやはり日本全国100万人の以下同文にとってヒーローな訳ですから、食べ合わせがいいのは至極当然。ただ、個人的に気に入ったのはそこではなくてですね。ちゃんと「シンガー・ソングライター」してる1枚でもあるんですよ。サウンドやアンサンブルに比重を置きつつ、カネコアヤノが持つ安アパートの匂いとでも言うのかな、そこは失われるどころかむしろ引き立っている感すらあって。それに“日の出”なんて曲は、うっかりポップ・ヒットになりそうなメロディの強さがあったりする訳ですよ。
前述の坂本慎太郎もそうだし、これまた日本全国以下同文がリスペクトしてやまないbetcover!!なんかの文脈に照らし得る1枚でありながら、「いい演奏にいい作曲を乗せれば、それはいい音楽」という当たり前の哲学にも忠実な、その実素朴なロック・アルバムでもあるという。これは皮肉でもなんでもなく、私よりもう少し若い世代、それこそティーンエイジャーの音楽ファンなんかにとって、同じ時代にこの作品があるってものすごく得難い経験だと思うんですよね……
“物語を終わりにしよう”/想像力の血
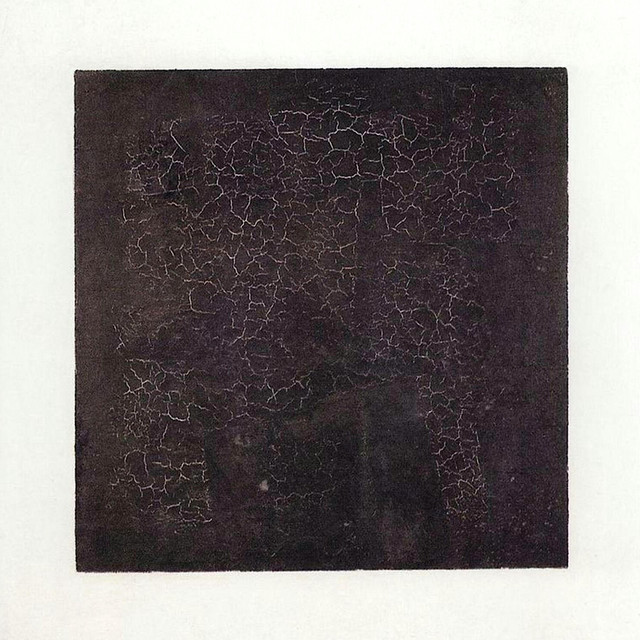
聴いた時は「5月の国産音楽はこれっきゃない!」と思わせてくれた1枚です。もっとも、カネコアヤノがやってくれたので振り返ればワン・オブ・ザ・ベストに留まりはしましたがね。カメラ=万年筆での活動、そしてスカートやKID FRESINOのサポートと幅広い活躍を見せる佐藤優介改め想像力の血の1st“物語を終わりにしよう”。
今名前を挙げたアーティストに共通する、「いや、俺はこれが普通のポップスだと思ってやってますよ」という顔で尖った音楽を鳴らすアティチュード、その文脈の中で語るべき1枚かなと思っていて。仄かにドリーミーな世界観の中で乱反射する音像の情報量が実に多い。決してカオスなアルバムではなく、むしろ端正ですらありつつも、「あ、そっちいくんだ」みたいな意外性が付き纏うようなイメージです。客演の多い作品というのも、この性質に関係している気がしますね。
で、そこに一切のわざとらしさがない。さっき語った、当の本人にとっては真っ当にポップスやってるつもりという意識がこの辺りから嗅ぎ取れます。甘く囁くヴォーカルの控えめな主張も、シンセサイザーをまだら模様に構築したサウンドも、ごくごくナチュラルに聴こえてきますから。ややこしいことをやっているのは確実だけれども、いい意味でのBGM的な馴染みのよさを獲得しています。フィナーレの“そして音楽はつづく”でぐっとポップスの優しさを押し出すのもいい手心ですね。
七尾旅人の“雨に撃たえば…! disc2”を、若さゆえの大胆さではなくキャリアに裏打ちされたバランス感覚で再構築した1枚、そんな風に表現してもいいかもしれません。要するに抜群に緻密で、やりたいことを詰め込んだ、生まれながらのJ-Popカルト名盤。長きにわたってひっそりと愛される作品としてのポテンシャルを感じさせる作品だと思います。
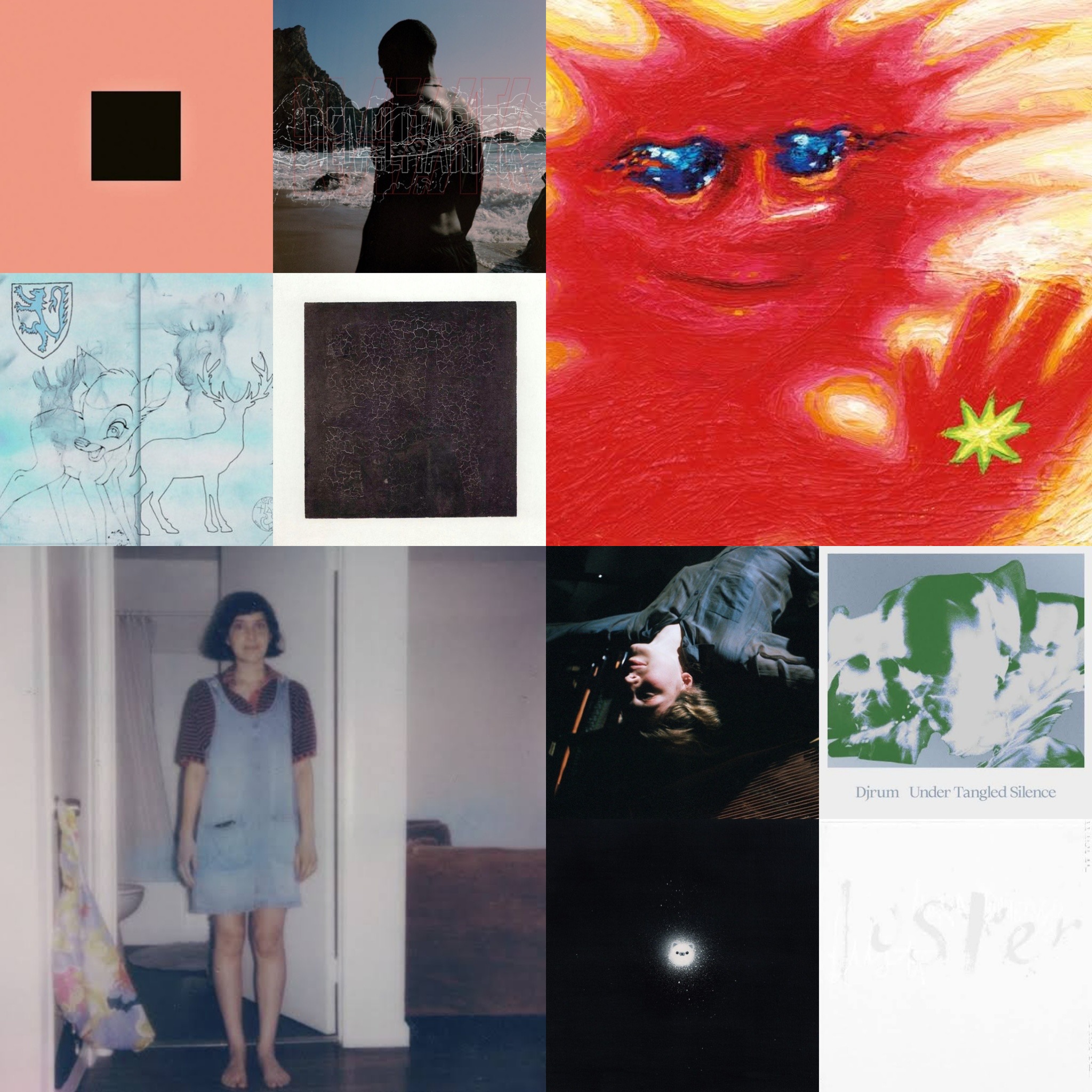


コメント