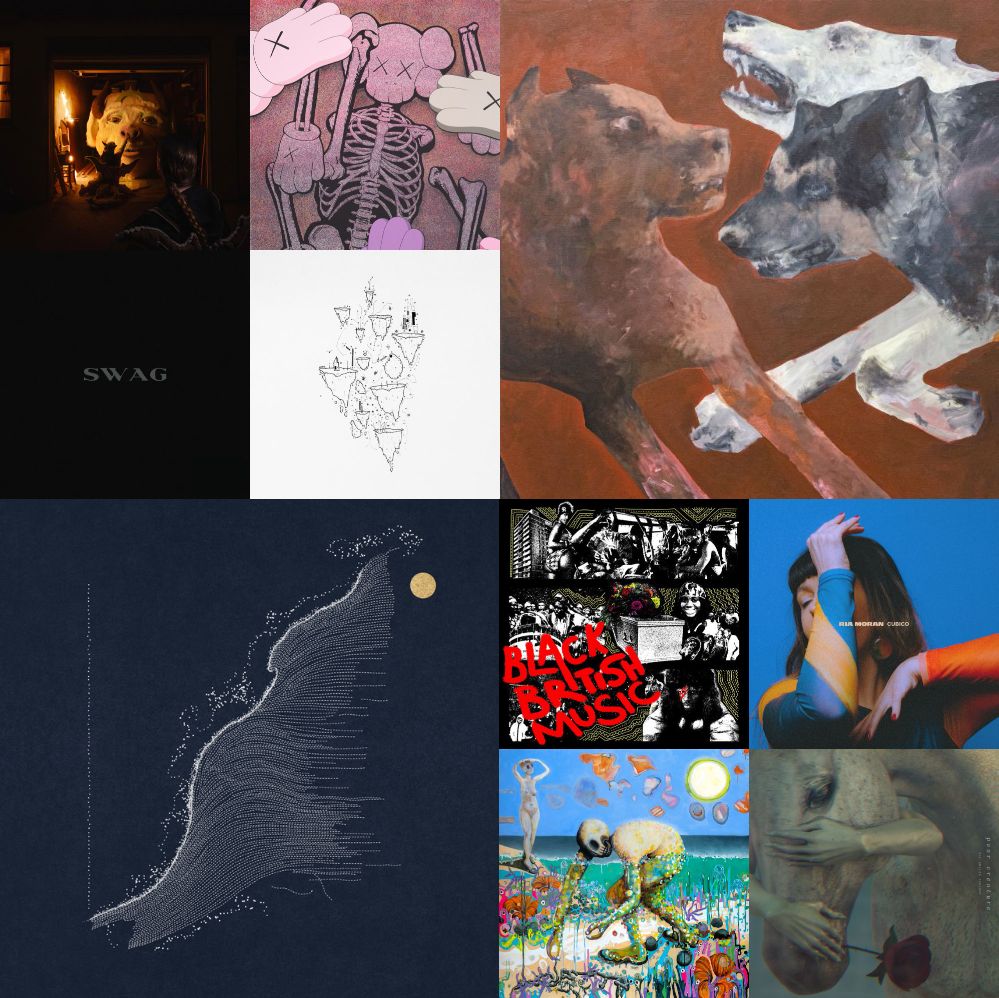
ああ、かなりの大遅刻となってしまいました。今回は「オススメ新譜10選」、約2ヶ月遅れではありますが7月編やっていきましょう。例によってバックナンバーは↓からどうぞ。
遅れてレコメンドしておいて何をと思われるでしょうが、この7月、そして翌8月、えげつなかったですね。個人的には上半期のリリースにもかなり満足していたんですけど、さらにもう1つギアがあがった、そんな印象です。
となると、聴くべき作品も当然多くなるわけで。そうすると必然、情報のチェックも忙しなくなるわけで。かつこっちもこっちで、1960年代を回想したりMJの誕生日祝ったりkurayamisakaでエモがったりと立て込んでおりましたから。ようやく一息ついて、しっかりとレコメンドしていきましょう。
“Vanisher, Horizon Scraper”/Quadeca

流石に7月はこれから語らないことにはね。新譜リリースをアナウンスしてから、私の観測できる範囲でもかなり待ち望まれていた作品でした。ラッパー……と呼ぶことに私はかねてから違和感があるんですが、Quadecaの最新作“Vanisher, Horizon Scraper”。
初めてその名を知ったのは2作前の“I Didn’t Mean To Haunt You”の時でしたが、これにしろ前作“Scrapyard”にしろ、コアなリスナーからの評価が極めて高いのは見ておりました。ただ、どちらも私の年間ベストには入れておりません。イマイチ、私の中で目の合うアーティストではなかったんですよね。ただ、YouTuberを出発点とした白人ラッパーという特異なポジションから、かなり横断的なことをしている野心は理解ししていたつもりです。
偉そうなことを言いますが、その野心がいよいよ私を感動させるものとして結実した、そんな作品です。横断的と言いましたが、本作は音楽ジャンルそれぞれの特質をよく見定めたうえで、それらを容赦なく撹拌しています。エレクトロニカ〜アンビエント、フォーク、ヒップホップ、MPB……単なる音のコラージュではなく、その性質をすら断片化し、作品をその坩堝にしてしまっています。そしてこの破綻は免れないはずの音像を、彼は途方もない壮大さで呑み込み、秩序をもってまとめあげている。これはちょっとえげつないですね。
このブログで何度か使っている「カクテル・ミュージック」という造語、複数の音楽性を独自かつ理論的に調合し、それらを作り手の技巧によってシェークし、マテリアルのキャラクターをいかしつつも全く別のものに引き上げる、という表現技法のことなんですが、その中でもずば抜けた完成度だと思います。そしてこの「カクテル・ミュージック」というのが20’sのキーになると睨んでいるんですが、その点で言えばこの左首、20’sの最重要作品の1つとなるでしょうね。
“Disiniblud”/Disiniblud
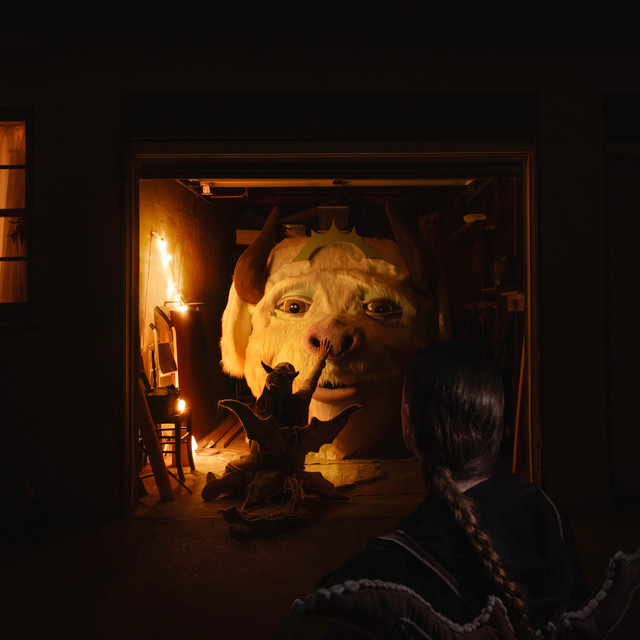
今回はややこしいところから片付けちゃいましょう。Rachika NayarとNina KeithのコラボレートDisinibludによる1st“Disiniblud”。どちらもアメリカを拠点とする実験音楽/現代音楽の人物のようです。はっきり言ってこの領域は無知にも程があるので、客演陣含め初めましてが過ぎるのでちょっと気まずくなっています。
それでも紹介するということは、気まずさや無知の恥ずかしさなんてどうでもよくなるくらい素晴らしい1枚だったということ。ポスト・ロックにポスト・クラシカル、アンビエント、IDMといった如何にもとっつきにくい音楽性の調和として紹介されていましたが、そこから響いてくる音楽はあまりにもノスタルジックで驚かされましたね。物々しいジャケットのイメージに反する清澄さも意外でした。
当然、サウンドの配置は複雑かつ大胆。基調となるのは透き通ったエレクトロニカですね、そこにピアノやギター、あるいはストリングスが装飾として適宜加えられていくんですが、絶えず展開し、やすやすと解決させてくれません。その掴みどころのなさに夢中になるし、歌唱というよりはリアリティを付与するマテリアルとして添えられた肉声のおかげもあって、現実の情景ではなく記憶の回廊を彷徨うような精神的な奥行きと安らぎを与えてくれます。
やってることはかなり難解なはずなんですが、それを差し置いて個人的なものとして聴かせる説得力みたいなものが卓越していると思います。ほら、Quadecaは良し悪しとは別に親密かというとそうではなかったですから。さっき挙げた音楽ジャンル、なんか距離感あるなぁと感じている人にこそ聴いてみてもらいたい作品じゃないかな。ことのほかフレンドリーで、しかしやはり高尚さもあるので、苦手意識を払拭するには絶妙なのではないかと。
“SWAG”/Justin Bieber
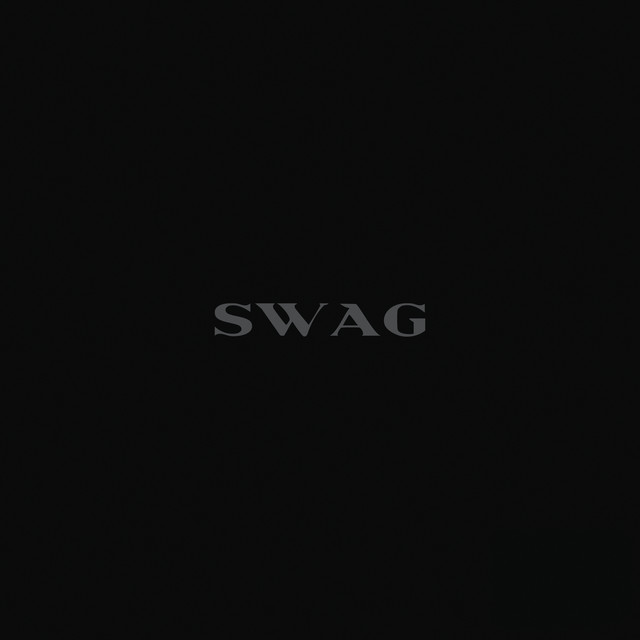
彼の作品をまさか弊ブログで真面目な顔して語ることになるとは、正直私自身思ってませんでした。皆さんご存知のスーパースター、Justin Bieberの4年ぶりとなる新譜“SWAG”。でもこれは、ひところまた話題になっていたポプティミズムへの迎合ではありません。
だって、彼が今回のサプライズ・リリースで手を組んだのがDijonやMk.geeとなれば話は変わりますよ。Bon Iverの新譜にも絡んできた、間違いなくたった今トレンドを生もうとしている系譜(注:この文章はDijonの新譜リリース前に書いていました)な訳ですが、このいい意味での節操のなさ、ちょっとMichael Jacksonっぽくて嬉しくもなります。それは、80’s〜90’sのR&Bが纏っていた類のメロウネスにキャッチーさに照れない正々堂々としたポップ・スターぶりを乗っける姿勢からも感じ取れたりもするんですが。
21曲収録でラン・タイムが54分という、曲単位ならばかなりコンパクトにまとめた構成も気に入ってるんですよ。甘いメロウネスが大味にもなりかねないところを、短編集的に歯切れよく聴かせることで回避してます。“GLORY VOICE DEMO”みたいにフィラー的な楽曲もいい味出しているし、続くアコースティックな“DEVOTION”も如何にもポップ・アルバム中盤にきてほしい質感でね。メインストリームらしくチームアップでの作品なので、どこまで彼の采配かまでは見えてきませんが、アルバムとしてもかなり巧みなんじゃないでしょうか。
なまじJustin Bieberという名前が大きすぎて、ことのほか騒ぎにはなりきらなかった、あるいは「Dijon読んでおいてこれかよ」みたいに言われちゃってた実感もあるんですが、5年後に20’sを振り返る時にしばしば思い出される作品ではないかと思ってます。Dijon/Mk.geeの文脈が今後何某かのシーンを獲得したとして、それをオーバーグラウンドで早くに実践した例としてね。
“Cubica”/Ria Moran

難しい音楽だったりコッテリしたポップスだったりが続いたので、ここいらでしっとりとネオ・ソウルなんてどうでしょう?イギリスの女性アーティストRia Moranのデビュー作“Cubica”。「新譜聴いたなぁ!」という実感こそ先の作品たちより薄いですが、名作ですよ。
女性的なセクシーさという性質に相当に自覚的な作品ですね。磨き抜かれた絹のような光沢のあるシンセサイザーがサウンドスケープの中でひときわ目立っているし、物憂げでもったいぶった歌声も素敵です。どぎついセックス・アピールやあざとさではなく、ミステリアスでツンとした表情を描くのが実に上手い。と言いつつ、比較的甘めに味付けされた“Anything You Desire”のギャップにコロッといっちゃうんですがね。
で、その2つを両輪にした作品ではあるんですけど、流石はソウル、脇を固める演奏も隙がないです。ベース/ドラムがいいのはこの手の音楽なら必須条件ですが、加えてギターが効いてるのが個人的に好きなポイント。シンセがメインになるとギターって必然的に役どころが難しくなるところを、気を利かせた伴奏やフレーズの遊びで華を添えるんですね。フュージョンも彼女の構成要素にあるらしいので、そういう方面からのセンスなんでしょうか。
これはもうソウル好きなら間違いなくドンピシャでしょうし、汗臭さもなくほどよくダウナーなのでダークな音楽が好きという人にも届くと思います。個人的にもかなりメロメロにさせられてますよ。迂闊なラベリングや、ましてや差別にならないように細心の注意は払うべきですが、音楽における性差って大切だと改めて思えた素晴らしく女性的な名盤ではないかな。
“black british music (2025)”/Jim Legxacy

今年はどういうカラクリか、UKヒップホップに言及する機会が非常に多い気がします。何かシーンの変動があるのか、あるいは個人的な感度が今そっちに向いているのか。ということで2作続いて2025年の黒いイギリスの音楽を、Jim Legxacyでその名も“black british music (2025)”。まさに2025年における黒いイギリスの音楽です。
すごく器用なアルバムだなぁというのが第一印象ですかね。基盤は確かにヒップホップなんですけど、例えば“d.b.a.b”なんて曲はかなりアフロなテクスチャが目立っていて、かと思えばDexter In The Newsagentとやってる“dexters phone call”はまるっきりインディー・ロックだし、かなり自由度の高い音楽性じゃないかな。そこにUKのブラック・ミュージックの特徴である淑やかさ、これ男性がやると侘しさみたいなカラーも出がちなんですが、それを纏わせて統一感を生んでいます。
で、その器用さを自分自身で遠ざけようとする技法も聴こえてくるんですね。どういうことかというと、全体的にパッチワークのように継ぎ目がはっきりしているんです。音楽性においてもそうだし、サウンドの質感にしてもハンドメイドな感覚があって、作品にちょっとした歪さ、言い換えればメリハリを与えている。これがさっき触れたUKブラック・ミュージックのナイーヴさが演出する柔らかさや滑らかさに喰らいつくことで、サラッと聴き流すことを許してくれません。ただ、そういう作用を狙ってやっているというよりは、思うままに音楽を展開した副産物のようなものには聴こえてきますね。それもまたインディー精神が感じられていいんですよ。
この前にXではちらっと書いたんですけど、ヒップホップのような「黒い音楽」のUSでの商業的不調(それ自体はトレンドの変化で、いい悪いではなく単なる事実ですが)に対する1つの回答は、UKのようなアメリカ外のブラック・ミュージックがどう受容されていくかにかかっている気がしていて。そういう個人的な眼差しからすると、こういう期待できる才能がUKから生まれてくるのはいい傾向ではないかなとも思っています。
“Bad Dogs”/81355

さてさて、ヒップホップならUSも負けてませんよ。Tyler, The CreatorやFreddie Gibbsといい作品はいくつかありましたが、7月で一番印象に残ったのはやっぱりこの作品です。Jim Legxacy同様、安直にヒップホップと言っていいか微妙なラインではあるかもしれませんが……81355(これでBlessと読ませるようです)の2nd、“Bad Dogs”。
カチカチのバンド・サウンド、それもThe Rootsのような方向性ではなく、あくまで現行インディー的な世界観のそれにラップを乗っけるという、ありそうでなかったスタイルが鮮烈です。だってヒップホップなのに、トラックで一番目立ってるのギターですよ?2曲目のその名も“Guitar”なんて、普通にインディー・リスナーを喜ばせてくれるサウンドです。リズムにしたって、やはり人力特有のムラっけ、それはこの場合ヒューマニティーと同義ですが、を感じてね。
そこに乗っかるフロウも、繊細で優しい質感というのが徹底してます。ヒップホップのマッチョなイメージも近年かなり薄らいではいますが、インディー・ロックに乗せるのであればやはりこのくらい線が細く、そしてスマートであるべきでしょう。かつ、ハーモニー・ワークを多用してしっかり肉声の輪郭を強調しているので、印象がぼやけることもありません。シームレスに繋がる“Fire Over Me”から“JUNO”の展開は、こう言ってはなんですが「歌モノ」としてよくできてます。
私が不勉強なだけでこういうアプローチは他にもあるのかもしれませんが、個人的にはすごくハッとさせられる1枚でした。ああ、ロックとヒップホップの調和って、今やるならこうなんだなと。特にラスト・トラック、グッとダイナミックになる“Bright Side Of The Sun”のパンチなんて、ロックならではのものですから。何かしらのトレンドを生んでほしい1枚だし、そうなるポテンシャルは間違いなくあると思います。
“Let God Sort Em Out”/Clipse
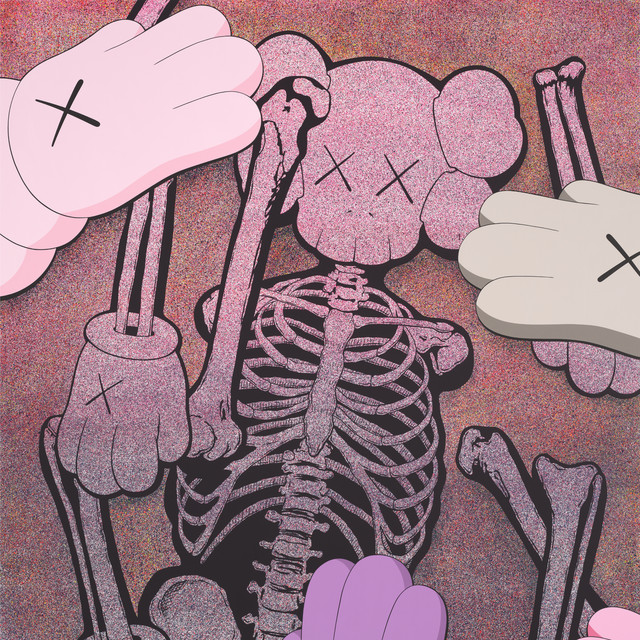
7月はさらにヒップホップを。今回はかなりロック色の控えめなラインナップですが、自然に選んでそうなるというのは個人的に嬉しいことです。体に染みついたロック崇拝から脱却できているということなので。閑話休題、こちらは王道ですね。Pusha-Tとその兄No Maliceによる兄弟ユニットClipseの16年ぶりとなる作品“Let God Sort Em Out”。
かつて彼らをフックアップしたPharrell Williamsをプロデューサーに招いていますが、いやはや、やはり上手いですね。全体的にスモーキーでレトロ、俊敏性はなくとも耳に残るプロダクションが徹底しています。“Chains & Whips”の地を這うようなディープさから讃美歌のような麗らかさを垣間見せる“So Far Ahead”まで、毛色こそ違えどPharrell Williams印な采配がずっと続いていますからね。
で、彼がもう1つ上手いのは、作品の焦点をきちんとラップに合わせているところ。サウンドも素敵なんですけど、Clipseの2人、とりわけPusha-Tのシャープなフロウ、それからKendrick LamarやNasといった「ラップの上手い人」を贅沢にフィーチャリングして活かしきる「ラップ・アルバム」の高揚感みたいなものが充満してます。これまで何度か語っていると思いますが、私個人としては「ラップ」が好きなのではなくサウンドとしての「ヒップホップ」が好きという自認なんですね。そんな私がこんなに「ラップ」で楽しめるというのが何よりの証拠です。
さっき挙げた“So Far Ahead”もそうなんですが、アルバム後半でこういった温かみが広がっていく構造にも飽きがこないんですよね。41分という「名盤」の標準サイズであることも味方して、思わずもう1回聴き返してしまうある種の軽さと親しみがあって。キャリアの長さをしっかりと感じさせる、隙のないヒップホップ作品でした。
“Precipice”/Indigo De Souza

ノースキャロライナ出身の女性アーティスト、Indigo De Souzaで“Precipice”。ジャケットのインパクトに覚えがあったんですが、2021年の“Any Shape You Take”はおそらく当時聴いていますね。まだあの頃はそこまで新譜に関心がなかったので、きちんと記憶に残っていないのが悔しい限りです。こんなに私好みのポップスなんですから。
まずはシンセの鳴り方に好印象を覚えました。個人的にポップスで鳴っていてほしい、ちょうどいい塩梅の軽さというかね。作品にフワフワと漂うような質感を与えているんですけど、エレクトロ作品として向き合えるほど主張する訳でもない、あくまで下地としてのさりげなさがいいじゃないですか。シンセ・ポップの爽やかさからドリーム・ポップの神秘性まで、その領域を悠然と渡ってみせるレンジも魅力的です。
そして歌声もまた面白くてね。“Crying Over Nothing”という曲が分かりやすいかと思うんですけど、やや大袈裟にスケールを大きく歌っています。これがさっき書いたサウンドの軽さの中で際立って聴こえてくるんですよ。かと思えば本作でひときわ静謐な“Dinner”や続くフォーキーな“Clean It Up”という曲では、その世界観に寄り添う物腰柔らかな態度も示していて。サウンドスケープの鮮やかに溺れない、ポップスに大事な歌声での訴求力というものも兼ね備えています。
この前の60’s名曲ランキングだったりMJであったり、個人的なチャンネルがポップなものに切り替わっているタイミングでこの作品に出会えたのもまた嬉しいもんです。きちんと今風のインディーな音をやりつつ、でも根っこのところでは歌声で引っ張る古き良きポップスのメソッドも持っていて。かなりよくできた作品だと思うんですけどね。
“All Smiles Tonight”/Poor Creature

インディーというところでいくと、これもよかったなぁ。LandlessとLankumという2バンドからメンバーが集まって結成されたプロジェクト、Poor Creatureの“All Smiles Tonight”です。Lankumは2023年の“False Lankum”が批評的に注目を集めたことで、記憶に新しいという方も多いのでは。
どちらもアイルランドのトラディショナルな音楽を現代的に再構築するという試みであるからして、本作にもアイルランドの風は紛れもなく吹いています。独特の長閑さがあるヴォーカルの節回しなんて如何にもですよね。でもバックの演奏はかなりドライで、絶えず不穏さがつきまとうアンダーグラウンドなものになっているのが聴いていてスリリングです。3曲目のデュエット“The Whole Town Knows”なんかが好例かな。
伝統的なサウンドの参照って、アメリカにおけるカントリーでも日本における民謡でもそうですけど、いきおいノスタルジーと接続しがちじゃないですか。無論そうした匂いも本作にはあるんですけど、加えて、なんだろうな、ある種の因習めいたものとでもいうのかな、そういう不吉さもあるんです。異郷に感じる疎外感と言ってもいいんですが、それをバンド・サウンドというただでさえ親密になりやすいフォーマットで描いているのも冴えています。
この得体の知れなさが、リスナーの意識を掴んで離さないフックになってるのかなと。フォーキーなものを求めて聴けばバンドの尖り方に驚かされるし、ロックなものを求めて聴けばトラッドな作風に意表を突かれます。そしてその2つを、あえて違和感を含ませて両立させているんですから大したもんです。
“A Dawning”/Ólafur Arnalds & Talos
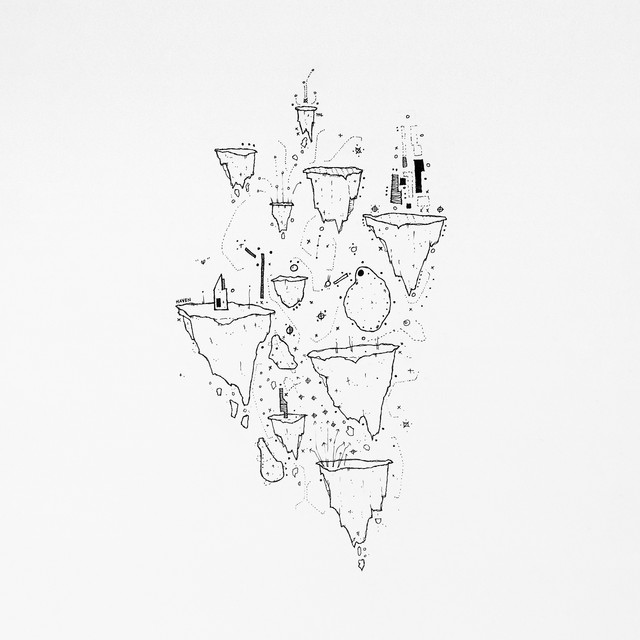
Ólafur Arnalds(ポスト・クラシカルの人物らしいですね)がTalosことEoin French(Poor Creature に引き続き、アイルランドのアーティストです)と共作した“A Dawning”。制作中にEoin Frenchは病に倒れ、そのまま帰らぬ人に。残されたマテリアルをArnaldsが完成まで導いた1枚とのことです。
……今の情報は全て後から調べて知りました。アーティスト名も知らなかったし、なんならポスト・クラシカルがどういうものかいまだによく分かってません。が、これはいいアルバムですね。慎ましやかなピアノと、些細な残響までを拾う鋭い録音、そして神秘的なモード。そこに寄り添う誠実で心細そうなヴォーカルの美しさときたら、かのAntony And The Johnsonの名盤『I Am A Bird Now』から闇深さを葬り去り、清廉な気高さで満たしたような趣があります。
3曲で客演を招いてはいるものの、そのモノトーンは一貫しているし、30分という軽やかさで聴かせてくれるのも見事ですね。これがTalosの遺作となったことを知らなかった時点でも、その沈痛さや穏やかな慈しみというのははっきりと聴き取れるのですから天晴れです。しかも、それはレクイエムのように厳かなだけでなく、子守唄のように柔らかでもあります。締めくくりに流れる“We Didn’t Know We Were Ready”のハーモニーとストリングスなんてまさしくでしょう?
さっきのDisinibludといい、ポスト・クラシカルという私にとってかなり距離のある領域に関連した作品が2枚もキャッチできたというのはなかなか興味深いことです。まあ、こっちはジャンルで語るというよりはもっと普遍的に聴けてしまう類の音楽ではあるんですが。新譜のリスニングって、なんの色眼鏡もかけていない、かけられない状況下での経験だからこそ思わぬ方向に関心が結びつくから面白いなあと改めて感じました。ということで、モチベーションが高いうちに8月編も近日公開いたします。


コメント