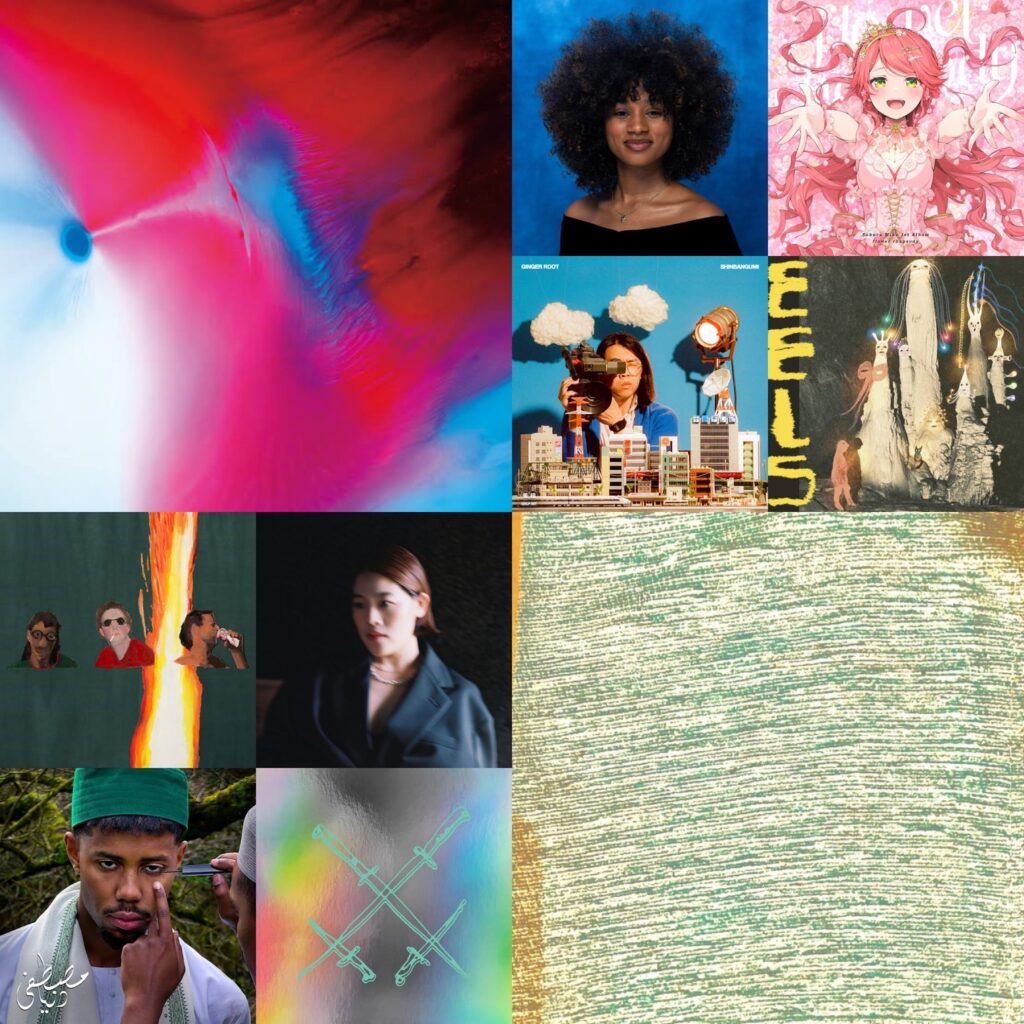
少し間隔が空いてしまいました。今回も月間新譜レコメンド、やっていきましょう。9月編ですね。最早1ヶ月の遅刻など遅刻のうちにも入らんのです。バックナンバーは↓よりどうぞ。
そろそろ年間ベストもちらつく時期になってきましたが、今回紹介する10枚もかなり有力候補になってくる名盤揃いです。例年通りなら聴きこぼしていた作品がだいたい10枚くらい年間ベストに滑り込んでくるので、今のうちから枠を埋めてしまうのは早計と理解はしているんですがね。
そんな訳で早速見ていきましょう。9月のオススメ新譜、こんな感じのラインナップです。
“Cascade”/Floating Points

Pharoah Sandersから宇多田ヒカルまで、ジャンルや国籍を越えて近年の批評的重要作でその名を轟かすプロデューサーのFloating Points。そんな彼のソロ名義での最新作、“Cascade”ですね。実は恥ずかしながら、彼のソロ・ワークを聴くのはこれが初めてで。なんなら宇多田の客演目当てで聴こうとした節もあります。
で、聴いてみたらもう一撃で虜になりました。こんなバッキバキのダンス・ミュージックなんですね……どちらかというともっと音響的な、透明感のあるサウンド・メイクのイメージを勝手に持っていたので面食らいました。もちろん、そういったサウンドの表情もこの作品にはしっかりとありますけど、それ以上に暴力的とすら言えるレベルで本能に訴えかけるビートの主張。これに尽きます。
こういう「踊れる音楽」って、今まで私の中でファンクやソウルみたいなフィジカルのグルーヴにしか見出せない表現だったんです。ハウスやクラブ・ミュージックは、ロックの味付けとして作用しているものでしか摂取できていなかった。そういう私の不見識とそれに伴う偏見を、この作品はあまりに強引にこじ開けてきましたね。もう最初に聴いた時、まんまと部屋の中で暴れ狂っていましたから。ライヴ体験ですらなく、まして未知の音楽領域にある作品でこんな経験をさせられるとは……
この手のジャンルには疎くてですね、いつにまして単なる感想文になってしまったことを恥じつつも、しっかり喰らった記録としてこうして真っ先にレコメンドした次第です。ここであわせて紹介しちゃいますけどJamie xxの“In Waves”なんかも9月リリースの素晴らしいエレクトロでしたから、この辺り是非とも聴いていただきたいですね。
“13” Frank Beltrame Italian Stiletto With Bison Horn Grips”/Xiu Xiu

Jamie Stewartによるエクスペリメンタル・ロックのプロジェクト、Xiu Xiu。こちらも恥ずかしながらこの作品で初めてその名を知ったんですが、2000年代から活動を続けていて、シーンの中ではかなりの要注目アーティストのようです。そんなXiu Xiuで“13” Frank Beltrame Italian Stiletto With Bison Horn Grips”、いやぁタイトルが長い、そして意味が分かりません。
その意味の分からなさはそっくりそのまま音楽にも表れているんですけどね。第一感としては、とてつもなくスケールが巨大でエクストリームなゴシック・ロック。歌われるメロディが中低音を活かしたセクシーなもので、StewartのヴォーカルもANOHNIにも似た鬼気迫る情感を強調するものですから。ただ、ギターにしろエレクトロにしろ、登場するサウンドのテンション感が異様なんですよ。聴いていて一向に着地点が見つからない、まるで膨張し続ける宇宙空間のようです。
こういう作風、実を言うと私あまり好みではないんですよ。結局竜頭蛇尾で終わってしまったり、あるいは耳が慣れると途端に退屈に思えたり、最初の数曲はよくとも全体を見るとかなりリスキーなアプローチですからね。ただ本作に関しては、メロディそのものが存外キャッチーで核が定まっていますし、実験性ゆえに展開される突拍子のなさが果てしなく続くので退屈なんてとんでもない。ラストスパートの“Bobby Bland”なんて、一瞬King Crimsonのインプロビゼーションみたいな表情を見せすらしますから。
そしてフィナーレ“Piña, Coconut & Cherry”が実にカタルシスに溢れていてね。宇宙の比喩になぞらえるならば、その果ての果てへと辿り着いてしまったかのように一気に冷ややかさが充満し、うわごとのように叫ぶヴォーカルを巻き込みながら、作品全体のスケールを思えばあまりにこじんまりと、そして厳かに閉幕……こういう読後感のいいアルバム、堪らないですよ。
“Manning Fireworks”/MJ Lenderman

“Rat Saw God”は昨年の年間ベストの常連でもありました、USインディー・バンドWednesdayのギタリストMJ Lenderman。Waxahatcheeのアルバムに参加したことでも話題になった彼ですが、このソロ作品“Manning Fireworks”もすこぶる名盤でしたね。
WednesdayでもWaxahatcheeでも、カントリーとギター・オルタナティヴの折衷において見事なセンスを発揮した彼ですが、ソロでもその部分はしっかり主張されています。カントリー特有の懐の深さがありつつ、しっかりエレキ・ギターを歪ませる、Wednesdayの時にも感じたPearl Jamの正統後継者的佇まいとでもいいましょうか。その土壌の香りをもっと言うとそれは、インディー・スタイルのBruce Springsteenと表現してもいいのかもしれません。
こういう成分は、彼のメロディ・メイクからも感じられるんですよね。温もりがあって、でもどこか侘しげで。ブリティッシュ・ロックにはない人情味みたいな要素が、本作の印象には強くありますから。そしてサウンドの話に戻ったとしても、10分にわたるクロージング・ナンバー“Bark At The Moon”、これ最後の5分間は延々とギターのフィードバックが鳴っているだけなんですが、シューゲイズのような冷淡さは感じられないでしょう?前半のメロディの部分、あるいは作品全体で印象づけがされているからこそなんですが、こういうテクスチャこそ魅力の一端だと感じます。
この数年で現代最重要のロック・ギタリストとなりつつあるLendermanですが、本作でその才能をまたしても見せつける結果になったのではないでしょうか。8月のJack Whiteの時にも思いましたが、やっぱりギターがカッコいい音楽っていいですよね。2024年でも有数のギター・アルバムと言って間違いないと思いますよ。
“Gap Year!”/Laila!

実父はラッパーのMos Def、そしてTyler, The Creatorが絶賛するというとんでもない経歴を持つニュー・カマー、Laila!の1st“Gap Year!”。顔面アップのアート・ワークは父君の名作”Black On Both Sides”のオマージュでは?と話題にもなったようですね。あんまりそういう血縁とかセレブリティとかに意識を向けるの、個人的にあまり好みではないんですが。
不思議な質感のR&Bアルバムなんですよね。スモーキーに歌い上げるLaila!の歌声にはクラシカルな佇まいがありつつ、生楽器にしろ打ち込みのサウンドにしろシックにまとめられているにもかかわらず、いい意味でリアリティのないドリーミーな景色がそこにはあります。特にヴォーカル処理とシンセサイザーに分かりやすい、残響を意識したプロダクションがそうした距離感を生み出していると思うんですが、こういう音響的に楽しめるソウルって現代的でいいですよね。
そしてこれは残響というキーワードから繋がるものなんですけど、情報量が決して多くない、ここもポイントで。広々とスペースを取ったサウンドスケープがあるからこそ、やや輪郭を曖昧にしてもなお彼女の歌声がはっきり作品の真ん中で主張している。これで本作、全曲彼女のセルフ・プロデュースなんですから驚きですよ。前情報が豪華だったもので、ある程度は業界のパワーというものも介入している作品とばかり思っていました。新人とは思えぬ掌握能力です。
Solangeの“A Seat At The Table”を初めて聴いた時にも似ている、「確かにこのアプローチありそうでなかったな」という思わず膝を打ってしまう巧みさがある1枚なんですよね。今年聴いたソウル/R&Bだと、ちょっと今のところ一段レベルが違う作品のような気がしています。
“Dunya”/Mustafa

あのDrakeに発掘され、2021年の1stミニ・アルバムにはJames BlakeやJamie xxが参加し、作家としてはThe WeekndやJustin Bieberと共演……新人とは思えぬジャンルレスな関心を既に示されているトロント・ベースのアーティストMustafaの1stフル“Dunya”。このやたらめったらゴージャスな肩書きに恥じることない名盤でしたね。
Clairo、Rosalía、Daniel Caesar、The NationalのAaron Dessnerと音楽性の垣根を越えた錚々たる顔触れが客演で参加しているんですが、どうですこの面々、揃いも揃って音楽産業の匂いを感じさせませんよね?それもそのはず、あくまで本作の表現としての誠実ぶりを買っての参加なんですから。Elliott SmithからSufjan Stevens、そしてBon Iverへと繋がっていく内省的なSSWアルバムの系譜を継承したじっくりとした聴き応えが沁みるじゃないですか。
何より彼のソング・ライティング、これがさっき名前を挙げた先人たちにも並ぶほどにとにかく絶品でね。親密な抱擁のように温かく、しかしそこには確かな孤独の表情も滲み、伴奏の弦の響きなんかにはワールド・ミュージックの香りも仄かにあって……そんでもって、そのメロディを紡ぐ歌声がまた格別に相性がいい。わずかに掠れた歌声が切なさとヒューマニティを増幅させていて、うっかりすると涙ぐんでしまうほど琴線を優しく撫でてくる素晴らしいパフォーマンスです。
それでいてさっきも書いたように内省的ではあるんですが、非常に共感性の高い、親密さのある作品でもあります。これが私個人の感覚によるものか、もっと普遍的なものかは判断しかねるんですが、初めて聴いたとは思えないほどにしっくりくる1枚だったんですよね。今年のSSWモノだと、愛着の度合いだけならトップと言えそうな作品です。
“SHINBANGUMI”/Ginger Root

たいへんな親日家でも知られる、中国系アメリカ人のマルチ・インストゥルメンタリストCameron Lewによるソロ・プロジェクトGinger Root。どこか懐かしい(おそらくは日本人にとってはなおさら)ポップネスで根強い支持のある彼ですが、最新作“SHINBANGUMI”も御多分に洩れずといった感の1枚でした。
彼のサウンド・メイクって実に独特なんですよね。聴いていて思わずワクワクする遊び心とカラフルさがありながら、ちょっとビターな味つけもしてあって。前者であればシンセサイザーの使い方やパーカッションの軽快さ、後者であれば殊の外ローファイと言いますか、生音重視のプロダクションが本作ではそれぞれ対応している部分です。それを見事に繋ぎ止めるのがファンクネスなんですが、この実に適切な跳ね方が両者の魅力を損なわずに共存させています。あからさまな70’sの細野晴臣リスペクトの“Kaze“というナンバーなんかに分かりやすいところかな。
そう、この二面性で言うと彼のメロディ・センスや歌声もなかなか面白い。一聴すると愛嬌があってポジティヴ、そしてノスタルジックなんですが、本作におけるヴォーカルのミックスってかなり控えめになっているんですよ。かつ彼の歌声も冷静に振る舞っていて、決してメロディで聴かせようというアルバムにはなっていません。個性だけを見ればシティ・ポップですらあるこの作品から1980年代のコッテリとした香りがしないのはそこのところも大きいと思いますよ。
こんなにいい曲が書けるのに、彼は決してSSWであろうとはしない。コンセプチュアルなアルバムというのが本作のキーワードだったようなんですが、少なくとも耳で拾える情報のうえではその戦略が見事に功を奏していると判断できます。32分というすっきりしたサイズ感の中で、彼の多角的な才能がすべて噛み合った実り多き名作ですね。
“EELS”/Being Dead

昨年アルバム・デビューを果たしたばかりのテキサス出身のインディー・バンド、Being Deadの早速の2nd“EELS”。元はデュオ編成だったところを、本作からは新たにベーシストを加えてのスリー・ピース体制になっているとのこと。去年は音楽をサボりすぎたので1stは存在すら知らず、今回初めて聴くことになったバンドです。
いやぁ、こんなバンドを見落としていたなんて我ながらもったいないことをしました。サーフ・ロックやサイケデリア、あるいは初期ガレージといった60’sのアメリカで芽吹いた諸々の音楽性を、爽やかなバブルガム・ポップと捻くれたインディー・スピリットで包み込んだ見事な逸品じゃありませんか。このあっけらかんとした60’sリバイバルっぷりには、私が昨年から贔屓にしているThe Lemon Twigsにも通ずる魅力がありますよ。もっともBeing Deadは、より現代インディーの高慢ちきなセンスのよさを主張してはいますけどね。
Falcon BitchとGumballというステージ・ネームの2人がバンドの基盤なんですが、この男女混成のスタイルも効いてるんですよ。本作はえらく音がくぐもっていて、この音の荒さも愛おしいまでに60’sライクなんですが、そこに女声が加わると途端にエレガントな響きが生まれて作品のムードが瑞々しくなりますからね。サウンド自体は案外荒々しく無骨とすら言えるこの作品が、トータルとしてソフトに仕上がっているのはそうした要素によるところが大きいと思います。
今後のシーンの動向を占う重要作品という立ち位置ではおそらくなく、先鋭的なインディー・ミュージックを好む方であればきたる年間ベストの候補にはあがらなそうな作品ですらあると思うんですが。やはりパンク以前の音楽がルーツである私にとって、こういう「うん、俺もそれ好きだぜ」みたいな音楽は愛おしく思えてしまってね。前回紹介したThee Heart Tonesのロック版みたいな認識でいます。
“越冬”/越冬

今回は邦楽から3作品紹介するんですが、まずはこの衝撃的なバンドのデビュー作を。「ポストポストポストパンク」を標榜するバンド越冬の1st“越冬”です。今年扱ったdawntや電球もそうなんですが、Xでの評判を見てキャッチできた作品です。ディグを人任せにしているのは積極性が足りないという反省もあるんですが、なにせ皆さんのアンテナが頼りになるもんで。
さて、本作に触れた方が比較対象に挙げていたバンドがもう面白くて。なんてったって裸のラリーズとジャックスですからね。ざらつきと生々しさがこびりついたサウンドには退廃的なサイケがたっぷりと染み込んでいて、もう聴くからにアンダーグラウンドな気配を纏っていやがります。その中でいやにくっきりとしたギターの存在感が強烈で、この辺がラリーズとの類似なんでしょう。上手い具合にノイズを撒き散らす瞬間とヴォーカルに注目させる瞬間が区別されているのが丁寧な仕事ですけどね。
そしてジャックスに関して、ここはもう相当意識してますよね。日本語の響きを重んじた歌詞もそうだし、情念に満ちた歌声もまさしく。本作のハイライト“歪んだ世界”の前半部なんてまるっきり“からっぽの世界”ですから。ただこの曲、「からっぽ」に比して「歪んだ」というだけのことはあり、中盤以降に突然ギターが慟哭するカオティックな表情も持っていましてね。こういうアプローチは当然ジャックスにはなかった訳ですから、ただの懐古趣味ではない、2024年のインディー・シーンによるジャックスの再解釈という字面だけで面白すぎることをしてるんです。
単にギター・オルタナとしても実に趣深い内容のところを、それ以上に日本特有の世界観や詩情によって上書きしていく。betcover!の出世作であるところの『時間』なんかにも共通する、この厭らしさと鋭さの両立というのはひょっとすると今後の国産インディーにおける1つの重要事項なのかもしれません。またしても今後の動向を期待したいバンドが出てきたことは実に嬉しいですね。
“Love Deluxe”/優河

2022年作“言葉のない夜に”で私を含み一気にリスナーの心を鷲掴みにした印象です、女性SSWの優河による最新作“Love Deluxe”。もう彼女の安定感ときたら、カネコアヤノや柴田聡子と並べて、国内シーンで最重要の女性アーティストと認めてまったく差し支えないでしょうね。本作でそのことをはっきりと証明しています。
プロデュースには優河のバック・バンド「魔法バンド」の一員でもある岡田拓郎(ex.森は生きている)が参加しているんですが、この時点でまたしても柴田聡子との比較をしたくはなってしまいます。音楽的にも意識してる部分あると思うんですよね、なにしろしめやかな音響的インディー・フォークだったところから、ベールを纏ったようなミステリアスさをそのままに、電子的ダンス・ミュージックとしての骨格を獲得していますから。まさしく柴田の前作“ぼちぼち銀河”も、そうしたダンサブルな心地よさを押し出した作風でしたよね。
そのうえで、低音を豊かに響かせた優河の歌声が生み出す子守唄のような穏やかさと安心感、これがダンスともフォークともエレクトロとも絶妙な距離感を保ちつつ作品の温度感を決定づけている。フォークの素朴さとはもちろん相性がいいんですが、エレクトロの静けさともしっかりと噛み合っていて、かと思えば歯切れのいいビートに乗っかってもその柔らかさがユニークな化学反応を示しているんですね。音楽的な発展に彼女のキャラクターが振り回されていない、きちんと優河の音楽性として咀嚼されているのが聴いていて伝わってきます。
7月編くらいから弊ブログで定点観測できているアーティストへの言及がぐっと増えてきましたが、その中でも彼女は深化の面白さに関してはズバ抜けている気がします。そしてこの手の作品にありがちな「面白いけど次の作品聴かないことにはまだ判断しかねるな……」というような発展途上感もまったくない。これ、2024年の邦楽ベストの筆頭と言ってもいい傑作だと思いますよ。
“flower rhapsody”/さくらみこ

最後の最後で急に毛色が変わりましたが、素知らぬ顔でいつも通りレビューしていきます。ホロライブ所属のVtuberさくらみこによる1st、“flower rhapsody”です。ただ、この作品を新譜のレコメンドという観点でフラットに語るのはちょっと裏技めいた感覚は正直ありますね。
というのも、これは次元の隔たりを問わずですが、アイドル文化というのは音楽そのものに加えてそのキャラクター性やバックグラウンドも込みで作品になることが多い。そして事実この作品も、これまでの彼女のVtuberとしての活動の軌跡や「35P」と呼ばれるファンダムを大前提にしたハイコンテクストなものです。私はVtuberが好きなのでそこのところを受信できましたが、音楽以外の要素をリスナーに要求する作品を果たして他のアルバムと同列に語っていいものでしょうか?
……まあ、結論としては「知ったこっちゃないわ」ということで取り扱った訳ですが。単純にオタク・カルチャー由来のJ-Popとして秀逸なんですよね。どの楽曲も派手でインパクトがあるんですけど、本作の作家陣を見ればそれも納得、じんややしきん、かいりきベアといったボカロ/アニソンのシーンを牽引する面々ですから。その中でもいきものがかりの水野良樹手がけるオープナーの“SUNAO”と、PENGUIN RESEARCHの堀江晶太(a.k.a.kemu)作曲のフィナーレ“flower rhapsody”が楽曲のプレゼンスとして抜けているかな。それをしっかり開幕と閉幕に配置する構成もベタながらグッときます。
一口にVtuberと言ってみたところで、音楽としてそれぞれのタレントがどういった方向を目指すかは様々で。音楽カルチャーに身を置く人間としては、月ノ美兎の『月の兎はヴァーチュアルの夢を見る』がクリエイティヴィティにおいて一歩抜きん出ていましたが、「アイドル事務所」というスタンスのホロライブの音楽キャリアにおいては、本作は過去にない名作になったと思っています。
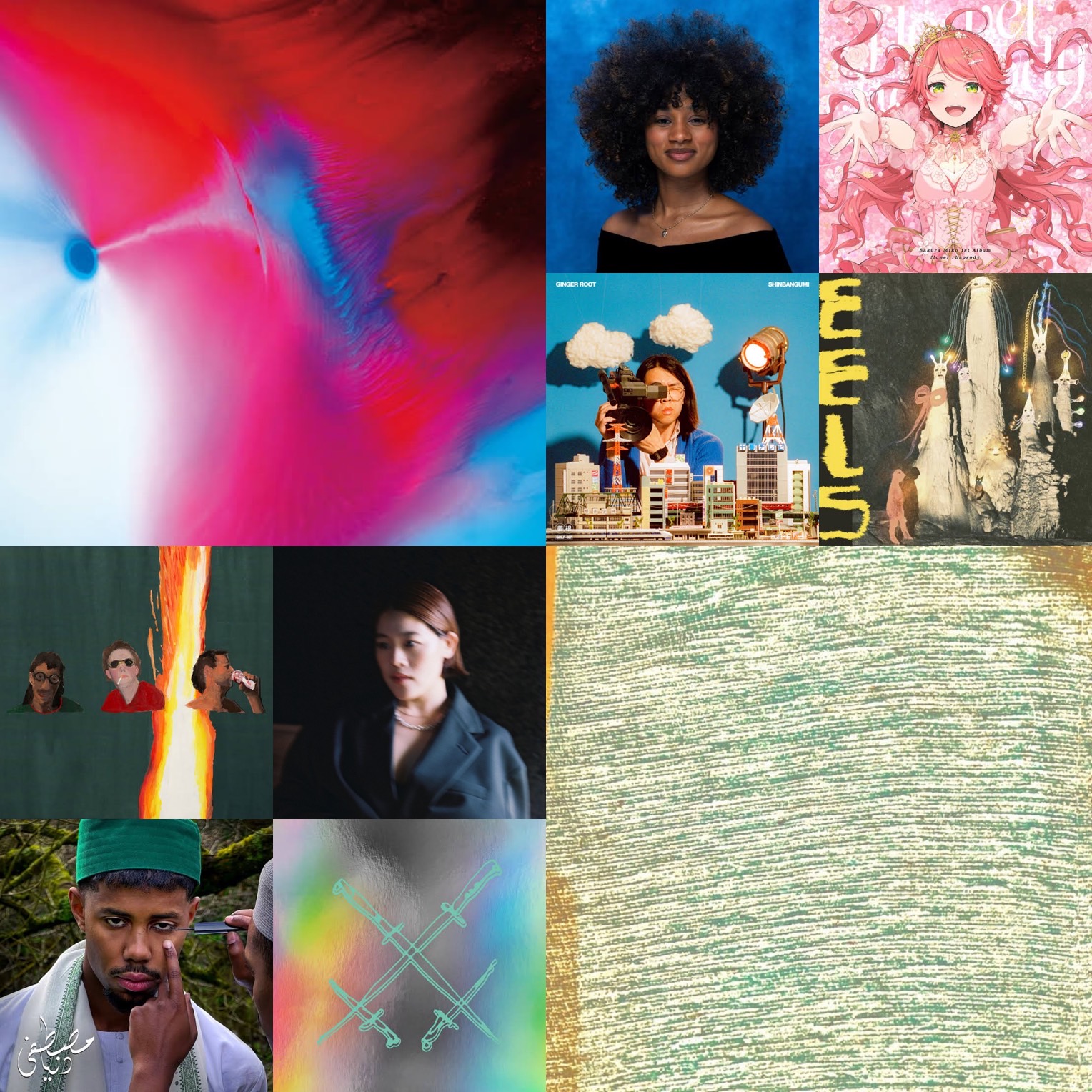


コメント