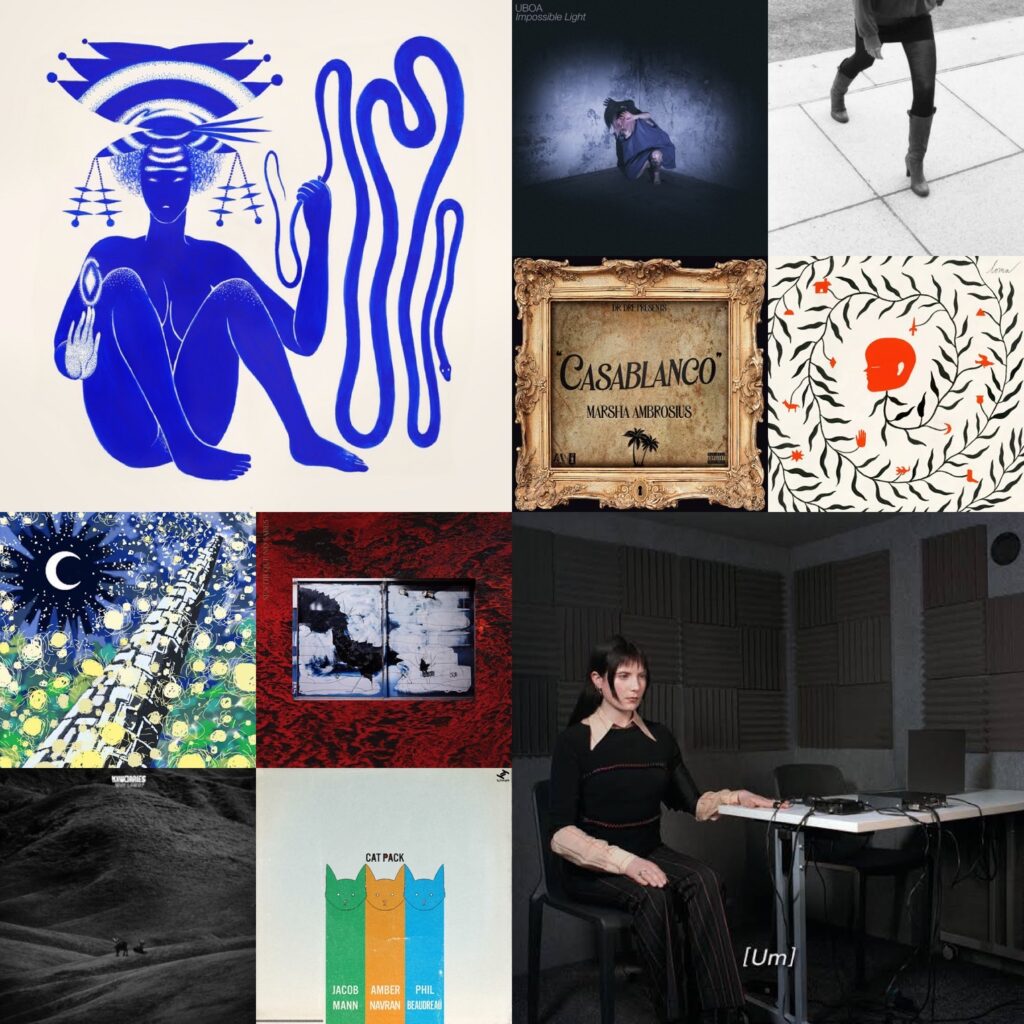
今回も今回とて、目指せリアルタイム更新ということで「オススメ新譜10選」やっていきましょう。まだ6月編ですけどね。バックナンバーは↓からどうぞ。
今回チョイスした10枚、これまでに比べるとちょっとマイナー気味といいますか、誰も彼も大絶賛!みたいな作品は選べなかった印象です。だって先に言っちゃいますけど、Charli XCX選外ですからね。
チャート・アクションでも批評でも、間違いなく2024年の顔になる1枚。そのことは百も承知です。ただあんまりしっくりこないんだよなぁ……何年か前のRosaliaもそんな感じで、あの時は悔しくて悔しくて何度も聴いたんですけどね。もしかすると年間ベストではしれっと登場させるかもしれません。
ちょっと言い訳がましくなりましたかね。あくまで、現時点で私が自信を持って心からオススメする6月のリリース作品は以下の10枚です。早速見ていきましょう。
“Why Lawd ?”/NxWorries

Anderson .PaakとKnxwledgeによるスーパー・ユニットのNxWorries。実に8年ぶりとなったこのユニットの2nd“Why Lawd ?”です。Paakの名前はBruno Marsとのコラボレート筆頭に最近しょっちゅう見かけますけど、ここまで精力的に制作に参加してどれもハイ・クオリティというのは凄まじい。
恥ずかしながら不勉強でKnxwledgeは初めて聞く名前だったんですが、Bandcampを中心に活動するビート・メーカーとのこと。要するに、トラック・メイクやプロダクションにおいてズバ抜けたスキルの持ち主2人の共演ということで。そのスキルは見事本作にも反映されていて、ネオ・ソウルを基調にしたスムースなトラックはどれも抜群に気持ちいいんですが、まとわりつくような粘性を帯びたエロティックな質感が堪らない。
そしてまた、そのトラックを彩るヴォーカルやラップが上質でね……フィーチャリングとしてクレジットされているだけでもSnoop DoggやEarl Sweatshirt、面白いところだとR&Bの大ベテランCharlie Wilsonなんかが参加しているんですが、サブスク上に記載のないものでも名演揃いだと思います。19曲44分と楽曲1つあたりをかなりコンパクトにまとめてある分、トラックに対しての「上物」である声のアプローチでしっかり差別化を図ることでフックが生まれている印象です。
2023年のリリースでヒップホップの元気がなかったのが気がかりでしたし、実際チャート・アクションでもアメリカでのヒップホップ支持って薄くなってきている現状はあるみたいなんですが、今年の作品の充実はかなりいい状況だと思ってます。そして本作も当然、その充実に貢献するに足る魅力的な名盤でした。
“Love Heart Cheat Code”/Hiatus Kaiyote

オーストラリアはメルボルンで結成されたフューチャー・ソウル・バンド、Hiatus Kaiyoteの3年ぶりとなる新譜“Love Heart Cheat Code”。本作を引っさげての来日公演も決定していますね。ここ日本でもコアなリスナーの方は支持している印象で、来日決定も一部界隈がなかなかに盛り上がっていた気がします。
そしてこの作品、来る来日公演が素晴らしいものになることを確約するように鮮やかな名作です。前作”Mood Valiant”は当時の新譜に関する投稿でも扱ったんですが、あちらで印象に残っているアダルティでアーバンな表現力は本作でも健在。デジタルなサウンドも惜しみなく取り入れ、ソウル/R&Bのコッテリした肉体性をそっくりそのまま洗練された洒脱さに置き換えています。ポストRobert GlasperのSteely Danみたいな、そういう現代的な軽やかさ。
そのうえで本作、かなりヴォーカルの主張が強いんですよね。グルーヴに注目させる作風は変わりないんですけど、Nai Palmのハスキーな歌声が随分と前に出てくるじゃないですか。そういう意味ではフィジカルな作品と表現してもいいのかもしれない。ただ、このヴォーカル・パフォーマンスが楽器的に機能しているのが面白いんですよ。ドラムの緻密な展開と交わるように進行して、決して歌声/演奏という対立構造を生んでいない。
結果として、歌声が目立っているのに全体としては紛れもなくHiatus Kaiyoteのサウンドとして帰着している。でもメロディはしっかりと際立っているから、ヴォーカルに意識を向けるタイプのリスナーにとってもすごくフレンドリーでもあってね。いつも通り、そしていつも以上に抜け目のない1枚という感じじゃないでしょうか。
“CASABLANCO”/Marsha Ambrosius

前回のYaya Beyの時かな、今年はあんまりソウル/R&Bをレコメンドできてないなんて話しましたが、6月は形勢逆転です。続いてもブラック・ミュージック、90’sにFloetryというR&Bデュオで活動していたMarsha Ambrosiusのソロ作品“CASABLANCO”。プロデュースはなんとあのDr.Dreですよ。
これまたコッテコテのR&Bですね……一聴して連想したのはMary J.Bligeですけど、あのヒップホップ全盛期の時代の空気をたっぷりと吸い込んで、そのうえでソウル・ミュージックとして吐き出したパワフルな創作とすごく似ています。何につけゴージャスなんですよ。ネオ・ソウルにしろオルタナティヴR&Bにしろ、21世紀以降のソウル/R&Bがやりがちな意図的に装飾を削った隙間に快楽を見出すアプローチとは真逆です。
ドラム/ベースというリズムの肝だけに注目すれば、控えめな印象すらあるんですよ。ヴォーカルを邪魔しない程度に、しかし埋没しない程度に絶妙なバランス感覚で作品を引っ張っていく。アプローチ自体は多分に現代ソウルなんですが、その態度はなんならニュー・ソウルのようでもあって。ただ、そうしたグルーヴの軸が確かであるのをいいことにコーラスやサンプリング、その他諸々上物のサウンドがこれでもかと風格たっぷりに、威厳のある力強さを作品に生み出しています。
そしてそれはもちろん、Ambrosiusの全身からエネルギーを隈なく掻き集めて放たれるソウルフルな歌唱が絶品だからこそ成立するプロダクション。きちんと作品の主役が彼女の声として定まっていないとただの虚仮脅しですからね。そういうヴォーカルありきのソウル作品って、現代ではかえって新鮮にすら聴こえました。
“Catpack”/Catpack

ネオ・ソウル・バンドMoonchildのヴォーカリストAmber Navran、LAで活躍するジャズ・ピアニストのJacob Mann、プロデューサーのPhil Beaudreauのチーム・アップであるCatpackのセルフ・タイトル1st“Catpack”です。また随分と豪華なトリオですね……
空白の中を泳ぐようなネオ・ソウルのグルーヴはMoonchildらしくもあり、その空白を柔らかく満たしていく気品のあるムードは現代ジャズのミステリアスさの翻案のようでもあり、作品に効果的な愛嬌を与えている電子音によるプロダクションはポップス畑でもあるBeaudreauの嗅覚の賜物でもあり……このように、三者三様の個性をきっちりと作品に落とし込んでいる印象です。これだけの才能がぶつかってもなお、歪み合うことなくすっきりと聴けてしまいますね。
ラン・タイムとしても30分未満とかなりコンパクトなのもその軽やかさに一役買っているとは思うんですが、サウンドとしても情熱的な盛り上がりや見え透いて目立つようなタイミングというのはなくて。ひょっとすると地味にもなりかねないところを、サウンドの1つ1つがこだわり抜かれた配置になっているので退屈させてくれません。ビートの抜き方だったりコーラスやシンセサイザーの差し込み方だったり、逐一抜かりないんですよね。
さっきのHiatus Kaitoteにも言えることですが、こういう気配りと計算が感じられる音楽はやはり素敵です。音楽そのものへの理解度と、それをコントロールしながら出力する技巧がないとできない代物ですからね。そうした知性を纏いつつ、聴き味としてはむしろチャーミングですらあるというのがいい意味であざとい作品です。
“Rocky Top Ballads”/Fine

北欧のアーティストを扱うのはこの企画では初かな?コペンハーゲンを拠点とする女性SSW、Fineの1st“Rocky Top Ballads”。今回の国際枠かつインディー・フォーク枠みたいな感じでもありますかね。別に特定のジャンルや国籍に忖度するつもりはまったくないですけど、ここ数回傾向としてそんな感じになってますから。
アンビエントとインディー・フォークが絶妙なバランスで鬩ぎ合う、この数年だとCassandra Jenkinsの2ndがそんな感じでしたけど、この作品は特に前半はもうちょっとアンビエント成分が強めな印象ですね。これはFineの歌声に由来する印象だとも思うんですが、もうとびきり透明度の高い歌声が儚げに広がっていて。それでいてサウンドスケープとしては空間的で曖昧、そしてこちらも澄み切っている訳ですから、本当に息を呑むような美しさ。
そのうえでギターやドラム、それからピアノの輪郭は意外にもクッキリしていて。ここすら溶解するようになだらかだと聴き味としてニュー・エイジとかそっちの方向に接近すると思うんですが、そこはあくまでインディー・フォークらしい実直さの世界観の中でとどまっています。それに楽曲によってはなかなかドラマチックなメロディの運びをするものもあって、決してサウンドだけで完結しているような作風でもありませんし。
質量を感じさせないさらりとしたサウンドスケープに、しっかりと歌モノとしての重たさが乗っかってくる。ポップであることを重んじたい立場としては、その両立が嬉しいところでしたね。日本人にとって北欧の音楽となるとメタルを除けばABBAか90’sのスウェディッシュ・ポップかってな具合ですが、そのどちらにも共通したメロディの上質さをインディー・フォークとして包み込んだ作品です。
“Sentir Que No Sabes”/Mabe Fratti

ワールド・ミュージックということでこちらも紹介しましょう。グアテマラ出身で現在はメキシコで活動するチェロ奏者/ヴォーカリスト、Mabe Frattiの3rd“Sentir Que No Sabes”です。グアテマラってことはスペイン語圏だと思うんですが、てんで読み方が分かりません。
チェロという楽器にフォーカスした音楽を私はほとんど触れてこなかったんですが、ストリングス・フェチみたいなところはあるのでもうドンピシャでしたね。特に低音域において、厳かでノーブルな佇まいがあります。そこに加えて、ギターでいうスクラッチみたいな奏法なのかな?弦を引っ掻くような神経質な音色であったり、たっぷりとエフェクトをかけたエレクトロ調のものであったり、トリッキーな手札も繰り出してきて。
そしてその演奏に華を添えるドラム、これがまた聴きものです。楽曲によってはもう予想だにもしないアクロバティックなビートを提供していますし、かと思えばぐっと引いてチェロや彼女の歌声にスポットライトを譲る、どちらも配慮の行き届いたプレイですね。彼女が即興音楽のシーンに属しているということもあって、こういった音楽の中でのパート間のパワーバランスにすごく意識的だから生まれる配慮だと思います。
彼女のつんとした歌声も作品全体の緊張感をさらに増幅させていて、その節回しにやはり中南米特有のエキゾチックなムードがあるのも嬉しいポイント。総合して、なんとも格調高く気品に満ちた1枚という印象です。しかしなんとも、ワールド・ミュージックになると前提知識が薄すぎるので、どこかできちんと体系立てて勉強しないとならんですね……
“How Will I Live Without A Body ?”/Loma

Lomaの3rd“How Will I Live Without A Body ?”。このトリオ、デビュー作であのBrian Enoに目をつけられ、2ndでは御大と共演も果たしています。ただ、バンド内の関係性が破綻してしまったようで(夫婦だったメンバーが離婚したとかで)、3rdまではずいぶん時間を要してしまいました。
ただ、時間をかけてきた分しっかりとしたクオリティになっています。Enoの名を出してしまうとアンビエントのイメージが強くなると思うんですが、あくまでオーガニックな演奏と淡々としたヴォーカルを軸に拵えてはいます。しかし、その音のそれぞれがどうにも孤立している。通常こうしたアンサンブルには親密さがあって然りなんですけど、あまりに素っ気なくサウンドが広がっているんですね。
その素っ気なさの中にも秩序や調和というのは確かにあって、それぞれが距離を取りつつも配慮をもって結びついています。その接続が生み出す空間の余白に、聴き手をそっと招き入れるような作品でね。そういった空間性という意味では確かに環境音楽的な聴き方はできるのかもしれません。楽曲単位で見てもボルテージが上がる瞬間なんていうのはストリングスやクラリネットみたいなアンサンブルがごく稀に与えるくらいなもので、あくまで粛々と広がる作品ですしね。
それとこの作品、少なくともApple Music上で聴く限りではすごくボリュームを絞ったミキシングになってるんですよね。それがまたさっきも触れた素っ気なさの表情をより強めていて、音量を上げるのが思わず躊躇われるほど的を射たものになっています。残る3作品がかなりヘヴィなものなので、こういうすっきりしたアルバムも拾えてよかったように思います。
“Scattersun”/Fax Gang & Parannoul

ここ数年インディー・ファンにはすっかりお馴染みとなった韓国の宅録シューゲイズ・アーティストParannoul、彼とインターナショナルなコレクティヴのFax Gangの連名によるアルバム“Scattersun”です。Fax Gangの作品にParannoulが客演した過去もあって、それを踏まえてのコラボレート・アルバムとなった経緯があります。
このFax Gangというコレクティヴが、HexDというジャンルを志向するようで。イマイチこの辺のジャンル理解しきれてないんですが、調べてみるとヴェイパーウェイヴ経由のエレクトロニカ・トラックの一種みたいな感じなんでしょうか。サウンドから感じられるわざとらしさ、ナチュラルであることを放棄した硬さみたいな部分がこのアルバムから聴き取れる限りの特質なのかな。
そのサウンドにParannoulらしいアグレッシヴな打ち込みのバンド・サウンドと彼の頼りげがないヴォーカルが溶け合うことで本作のサウンドスケープは生まれている訳ですが、エレクトロのフィールドでも彼の清々しい諦念みたいなキャラクターがはっきり出ているのが面白いと思います。昨年の”After The Magic”で作品に乗せる感情としてポジティヴな方向へ進んだものの、サウンドの過剰さが初期のParannoulを復刻させている感覚もあるような。
Parannoulに関しては8月に個人名義でアルバムを出してますし、あっちはあっちですこぶる好みだったので近いうちにご紹介することになります。それでもなお、ことサウンドの凝りようという意味では正直こちらに軍配が上がりますし、彼のキャリアの中で寄り道という感もない、かなり充実した作品になっているんじゃないでしょうか。
“Um”/Martha Skye Murphy

女優としても活動するイギリス人女性、Martha Skye Murphyの処女作“Um”です。彼女、本作以前にも音楽活動はしていたようで、あのSquidとのコラボレート・シングルなんかがあるみたいですね。このレビュー書くにあたって調べてビックリしました。
閑話休題。彼女の女優としてのキャラクターを知らないのであくまで一般論ですけど、そういうキャリアを辿る場合の音楽性ってウェル・メイドなポップスになりがちじゃないですか。そういう意識で軽はずみに本作を聴いたところ、いやはや痛い目に遭いましたね。とてつもなく緊張感のあるバロック・ポップじゃないですか。穏やかさや温もりなんてものはゆうに通り越し、厳かさや神聖さにまで接近してしまっています。
サウンドの構成要素をそれぞれに取り上げれば、ピアノやストリングスといった嫋やかさに貢献するものは多々あるんですよ。ただそこに通底する広義でのノイズ、それは電子的なものから歪んだギター、あるいは雨音ですらあるんですが、これらが息苦しさを与えていて。そして彼女のか細い歌声は、そうした音像の圧に何一つ関心を払っていない。やたらに飄々と、独自のスピリチュアルな佇まいをもって孤独に響いています。
いやに美しいサウンドスケープで、かつ背中にじっとりと汗をかくような厭らしさがある。まったくベクトルは違うんですけど、この感覚ってあの“OK Computer”でも似たようなものがあったような気がします。あくまで私の感覚のうえで。アルバム作品の聴きやすさみたいなものを重視する質の私ですら、6月の個人的ハイ・ライトはこれっきゃないと思わせる至高の1枚でしたね。
“Impossible Light”/Uboa

最後はこちらですね、オーストラリアのアンビエント/ノイズ・アーティスト、Xandra MetcalfeによるプロジェクトUboaで“Impossible Light”。アンビエントというジャンルは4月編でも扱いましたが、個人的にまだまだ馴染みのない未開の分野ではあります。
アンビエントって、Lomaの紹介でも書きましたが音の密度として疎であることが多い印象なんですよ。その疎なサウンドの余白の中を揺らめくことで快感を得られる、そんなジャンル。ところがこの作品、もう行き場所がないくらいに過密なノイズの連続です。しかもそれが爆撃のようなものであったり、デジタルに加工こそされていますが叫び声であったり、とにもかくにも残忍な質感で。救いのない世界観が延々と続きます。
もちろん全編でそんな過激な音が鳴っている訳ではなくて。音像の運びとしてはこうです。まず柔らかな残響で聴き手を油断させ、そこから無機質なビートとノイズが作品を徐々に支配してゆき、その不快感がピークに達した時の仕上げとして耳を塞ぎたくなる慟哭と爆音がもたらされる。アレです、ホラー映画と同じ構成してるんですよ。だからちゃんとこちらも余裕をもって受け入れることができる、と思いきや毎回ちゃんと不愉快になります。この不愉快さというのは、ことノイズ・ミュージックにおいて褒め言葉ですがね。
ダーク・アンビエントというサブ・ジャンルで紹介されていましたが、このジャンル全部こんな感じなんでしょうか?だとすればものすごく興味ありますし、同時に二度と聴きたくないような気もします。聴いていて集中力を磨耗させる作品なんてのは色々思いつきますが、ここまで精神力そのものを削ってくるアルバムは私の経験でもそう多くないので。
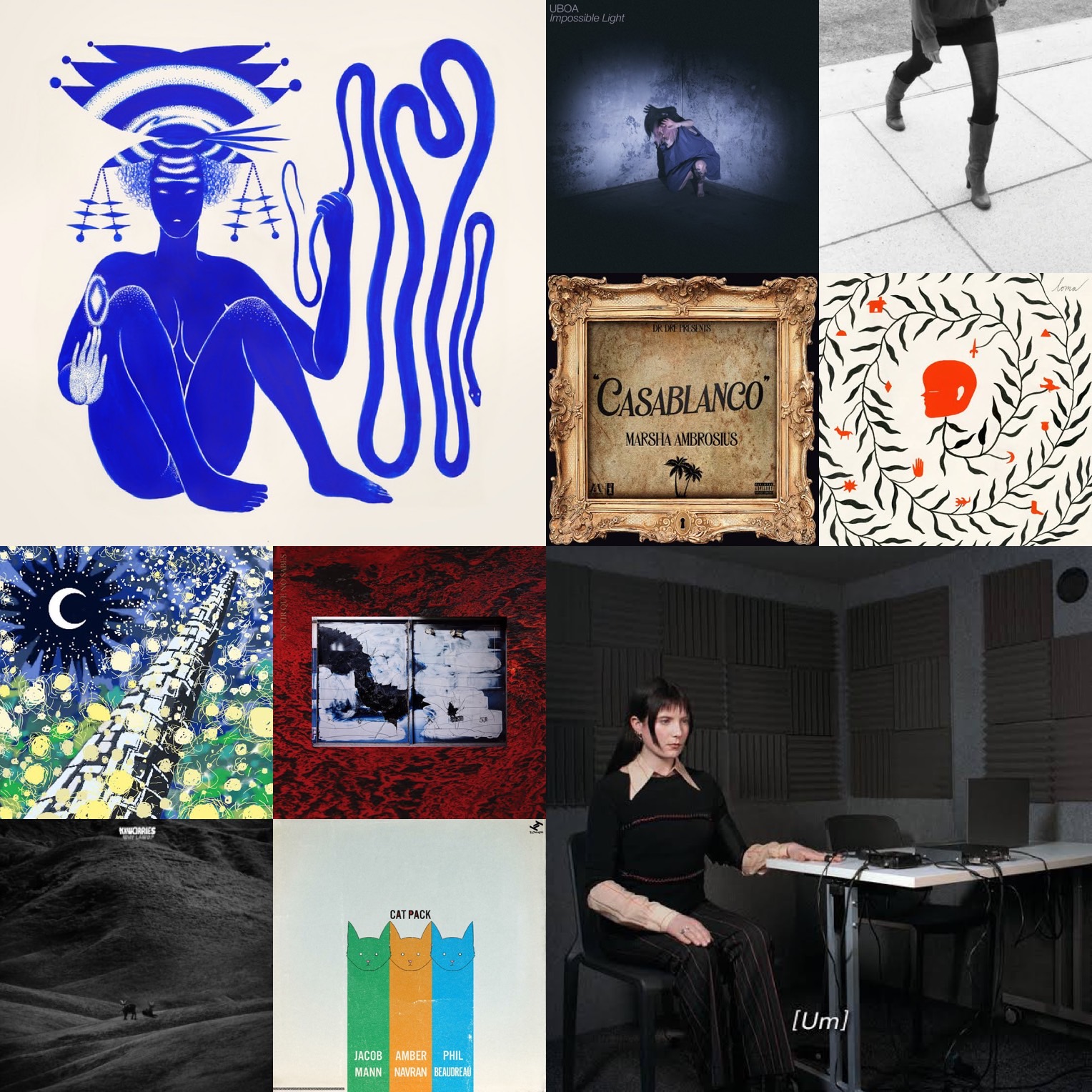


コメント